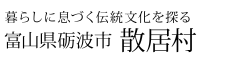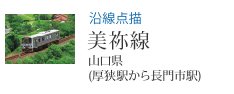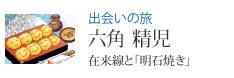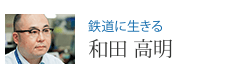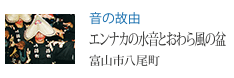まるで大海に浮かぶ島々だ。山の展望台から砺波平野を見渡すと、一面の水田のなかに点々と、おびただしい数の孤島が散らばっているように見える。その一つ一つは「カイニョ」と呼ばれる屋敷林に囲われた家屋敷だ。それは砺波平野ならではの風景である。
砺波の散居村は四季折々の表情を見せてくれる。田に水を張った春、みずみずしい緑の夏、金色の収穫の秋、そして冬の雪景色。「砺波平野の風土と、開拓した多くの先人たちの暮らしの知恵と努力がつくりだした風景です」と話すのは出村忍さん。伝統のカイニョを守るボランティア団体「砺波カイニョ倶楽部」のメンバーだ。

農業用水が幾筋も流れる田園地帯の向こうに望まれる「カイニョ」。この屋敷林には防風防雪のほか生活上大切なさまざまな役割がある。
日本の集落の多くは家々が寄り集まった集村であるのに対し、田畑のなかに家々が分散する形態を散居村と呼ぶ。島根県の出雲平野、岩手県の胆沢[いさわ]平野、そしてここ砺波平野が日本三大散居村といわれ、なかでも砺波平野は最大規模のスケールである。飛騨の山々の水を集めて富山湾に注ぐ庄川と、西の小矢部川がつくりだした大扇状地の眺めは、まったく広々として壮観だ。

カイニョに囲われた民家の周囲四方は一面の田や畑だ。農作業や利水管理が効率良くできるという合理的な発想に基づく。
弥生時代には水田耕作が行われた痕跡があり、奈良時代には東大寺の荘園として、砺波の米が奈良の都に運ばれていた記録が正倉院の史料にも残っている。しかし、庄川は大変な暴れ川で、氾濫する度に家々を流し、膨大な土砂を堆積した。そんな扇状地が本格的に開拓されたのは加賀藩領時代。庄川に堅固な堤防が築かれ、河道が固定した後に多くの人々が入植するようになった。
1619(元和5)年の『利波郡家高ノ新帳』によると、散居村の形態はこの頃には成立していたようで、藩政期を通じて「加賀百万石」の相当の石高を担ったという。出村さんはその成り立ちをこう話す。「最初の頃は、扇状地のなかでも条件の良い微高地を選んで家を構え、家の周囲に田畑を拓いた。家の周りに耕作地があると田植えや稲刈りなどの農作業も水の管理も手近にできて、もっとも合理的で効率が良いからです」。家々が寄り集まる必要がないほど砺波平野は水利も良かったということでもある。

田植えの時期にはどの農家も、家の正面の一番大事な田に「依代(よりしろ)」を立てるのが習わしだ。一年の家内安全と招福、作物の豊作を祈願する。

毎年4月から5月にかけて砺波平野は、赤や白、黄色やピンクなど色鮮やかなチューリップ畑で彩られる。
明治時代までに開拓はさらに進み、大正時代には冬場の裏作にチューリップの球根栽培が始められる。砺波の気候風土が日本一のチューリップ産地として農家に大きな富をもたらした。他にも今日、「となみブランド」に認定されている「庄川ゆず」や「種[たな]もみ」や「となみ野りんご」など特産品のどれもが砺波平野の豊饒[ほうじょう]の恵みである。
そうして昭和期の半ば頃には欧米の農場のように近代的に整備され、用水路が網の目のように整備され幾何学[きかがく]的な美しい景観になった。今日、一面に点在する農家は約7,000戸。「かつては1万戸以上もありましたが、年々減っています。この景観は砺波の生活文化遺産ですから、ぜひ守り通したい」と出村さんは話す。

冬は雪にすっぽり覆われる農家。一面の白銀に凛として佇むカイニョが美しい。
散居村の景観を構成するのは周囲の農村環境と、カイニョで囲われた住居空間だ。南西の季節風から家を守る高木の屋敷林は遠くから見ると小さな森だ。防風、防雪のほかに夏には日差しを遮り気温を下げ、冬には厳しい寒さを和らげてくれる。以前は囲炉裏の薪や生活の燃料として使われたり、また家の修繕、新築の用材としても用いられた。
そして、この屋敷林に囲まれた小さな空間には小動物や鳥や昆虫たちが暮らしている。カイニョと寄り添う暮らしは昔から受け継がれてきた自然循環型の暮らしのシステムであり、多彩な生物とともに暮らす共生の空間でもある。