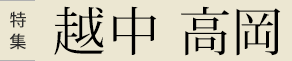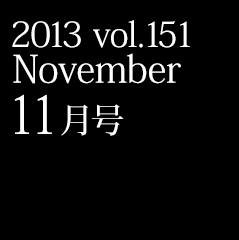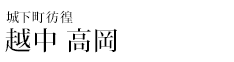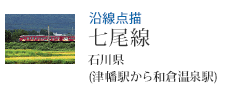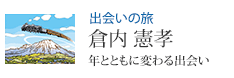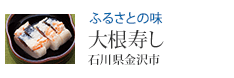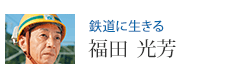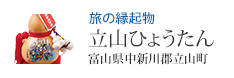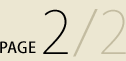
![]()
山町筋から西へ行くと千保川が流れている。鳳鳴橋を渡ると商都とはまったく異なる匠の町がある。金屋町[かなやまち]は高岡銅器発祥の地で鋳物師の町だ。大通りから外れ、石畳の静かな路地に入ると、江戸の空気がいまだに残っている。この風景もまた重要伝統的建造物群保存地区だ。
利長は入城後すぐに、産業育成のために鋳物師を呼び寄せ、土地を与え、諸役を免除するなどの保護をし、鋤や鍬、鍋や釜などの農具や日用品を鋳造させた。やがて釣鐘や仏具、灯籠から茶道具や花器などが造られ、さらには象嵌や彫金技術を加えた装飾性の高い美術工芸品の域に達した高岡銅器は、横浜や神戸を通じて海外に輸出され、商都の経済を支え続けた。
銅器の製造、金属加工は現在も高岡の主産業で、特に釣鐘やブロンズ像は9割を占める。家並みは京町家風で、石畳に面した家は板葺の軒を持ち、「さまのこ」という千本格子の構えのミセ、そして仏間、座敷と続き、中庭を隔てて土蔵があり、その奥が吹場と呼ばれる工房。これが鋳物師の家の特徴である。
金屋町にある店の奥まった工房で、利三郎さんが伝統的な手技で茶釜の風炉を製作していた。高岡銅器伝統工芸士の神初[じんぱち]宗一郎さんは、東京の大学を中退して鋳物師を継ぎ、5代目利三郎を名乗る。「工房の多くは郊外に移ってしまったけど、私はこの場所にこだわり、代々教え継がれてきた手仕事を続けています」。伝統的な茶釜や花器のほかオブジェや創作にも意欲的で、工房では鋳物づくり体験もさせてくれる。
世代を超えて伝統が継承される一方、世界を視野に新しい工芸やクラフト産業の育成に取り組んでいるのが、1909(明治42)年設立の高岡物産陳列所を前身とする高岡市デザイン・工芸センターだ。所長の高川昭良さんは「伝統をつなぐ人、工芸の可能性を拓く人を育て、世界に高岡ブランドを発信したい」と言う。大江浩二さんは市の助成を得て金属工芸を学ぶ。御車山の修理にも関わる彼によれば「伝統工芸の粋を集めた文化財は最高のお手本です」。市内の全小・中学校では「ものづくり・デザイン科」が必修科目になっている。地域の伝統工芸を授業に組み込んでいるのは全国でも高岡が唯一で、2009年からは文部科学省の承認を受けている。

工房やギャラリーが軒を連ねる金屋町の千本格子の町家。店先にはブロンズ像が置いてあったりする。

5代目利三郎の神初さん。茶釜の風炉を仕上げる利三郎さんの五感は研ぎすまされ寸分の狂いもない。これが身体が覚えた職人の技だ。

息を止め、繊細な指先の感覚で、コツコツと金属に命を吹き込む大江さん。象嵌や彫金には修練を積んだ精緻な技術が不可欠だ。

利三郎さんは主に茶道具や花器を造るが、日常的な小物から、現代アートのモダンな作品まで手掛ける。写真は、利三郎さんとプロダクトデザイナー金子良一氏による富士山をモチーフとした作品、アロマ香炉『赤富士・青富士』。

現在製作中の「御車山金具のレプリカ」の象嵌の飾り。大江さんが手掛けた作品だ。道具は専用のものがなく、全て自分の手になじむようにオリジナルで製作すると言う。
町を歩けば各所でブロンズのオブジェに出会い、旅館やホテル、飲食店のインテリアでさえ若手作家らの作品の発表の場であったりするところが、高岡らしい。まさに市ぐるみ、町を挙げて伝統産業を応援している。そんな高岡では、400年の歴史も伝統も決して過去のものではない。
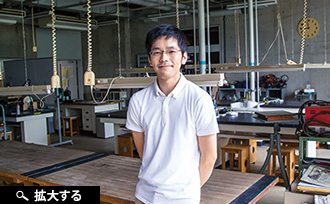
金属工芸の匠を目指して修業中の大江さん。「今はまだまだ習うことが多いですが、高岡職人の伝統技術を受け継ぎ、将来は文化財の修復や修理の仕事に関わってみたい」と語る。

高岡市デザイン・工芸センターの高川所長。「高岡の伝統工芸の技術を軸に、世界を魅了する優れたデザインの、アートなものづくりを目指しています」と言う。