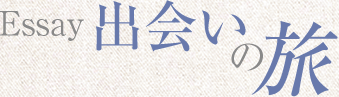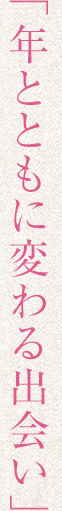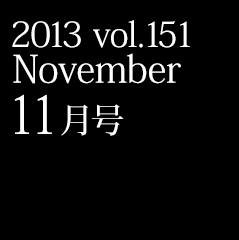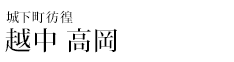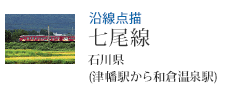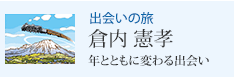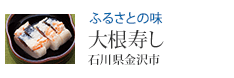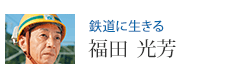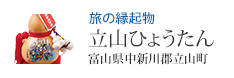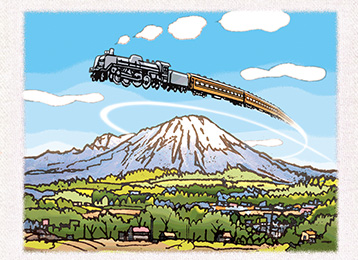
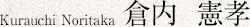
- 住友電気工業名誉顧問。1936年神戸生まれ。1958年東京大学工学部電気工学科卒業、住友電気工業入社。通信関連の研究開発、道路交通管制システムや光ファイバなどの事業開発を担当。1984年から5年間、米国駐在。1991年社長就任、1999年から2003年会長。2006年から6年間、西日本旅客鉄道の社外取締役として取締役会長・議長を務めた。
旅を振り返ると、自分自身の年齢や環境変化とともに出会いも変わってきたと思う。大学入学の頃、全国各地から上京して来た友人達に刺激され、知らない日本を広く見ようと旅に出た。友人の実家を訪ね、車中泊と長距離割引を存分に活用し、出来るだけ遠くに安上がりの旅をした。夏休みには北海道で旭岳や摩周湖、春休みには九州で阿蘇山、耶馬溪にも出かけた。どこに行っても景観は珍しく、長時間の移動も車窓の眺めに飽きることなく、また友人宅での訛りのある温かい応対が嬉しかった。
1958年大阪の会社に就職し、初仕事は当時普及し始めたテレビ放送の送信アンテナ建設工事だった。11月からNHK鳥取局を担当、山陰本線松崎駅近くの温泉に泊まり、鉢伏山山頂に通う日が続いた。屋外に組み立てたアンテナの側で電気性能を測定し、調整するのが仕事だった。寒風の中での作業は厳しかったが、雪が止めば、大山や隠岐の島が見え、山を下りれば、温泉や、かに料理が待っていた。眼下に見る集落や沿線一帯はいずれもこのアンテナのサービス範囲になることも誇らしく思った。
その後、研究部門に配属、当時の電電公社や国鉄との共同研究が始まり、毎月何回か、夜行列車で東海道を往復する生活に入った。出発の直前まで報告の準備に当たり、帰途には寝台で次の構想を練ることが多かった。夜行寝台車による長距離通勤といえば辛く聞こえるが、生活のリズムでもあり、充実感のある旅だった。
「陸の旅」は懐かしいが、「空の旅」も印象深い。まだ海外渡航が珍しい1965年、国際学会での発表の機会があり、その頃、燃料補給のため、南太平洋のウェーク島を経由する便で米国に旅立った。一眠りして機外に目をやると、紺碧の海が見渡す限り拡がり、海面近くには小さい雲塊が点々と浮かんでいた。地球の広さに出会い、人も飛行機も一旦吸い込まれれば、永久に消えると思えた。数年後、米国政府の超高速鉄道プロジェクトへの受託研究提案の出張では、アラスカのアンカレッジ経由で渡米した。窓の外の異様な輝きに惹かれ、外を見ると一面の大雪原に幾重にも山稜が並び、これらに朝日がさし、山稜の上部片面だけが陽を受けてピンク色に明るく輝いている。淡い紫色を帯びた雪原に多くの稜線が輝いている姿は神々の住む世界を連想させ、想像を絶する地球の美しさに感動した。広く美しい地球に、自分の仕事が拡がる夢を感じていた。その後、1980年代には光ファイバ事業の米国展開を担当し、5年ばかり駐在することになった。厳しい技術競争や通商摩擦の渦中で米国内や日米間を頻繁に旅したが、地球の大きさ、美しさは常に心の癒しになった。
ここ数年、仕事を離れてローカル線の旅を妻とともに楽しめるようになった。昨秋、山陰本線で島根から山口を旅したが、台風の接近で観光船の客は少なく、貸し切り同然で仙崎から青海島を巡った。時々くる驟雨の中、高い絶壁の海岸や深い洞窟など、初めて見る絶景に新鮮な驚きを感じた。日本にはまだまだ知らない所が多い。
自宅から5分ばかり歩くと猪名川の堤防に出る。200mほど離れた対岸にはJR宝塚線の電車が走っており、その先、遠くには六甲山塊がある。左手、川下には中国自動車道の猪名川大橋が川を横切っており、長距離トラックの列が行き来している。その上を伊丹空港から離陸した飛行機が西空に向かって上がっていく。乗り物を描いた幼児向けの絵本にありそうな構図である。ここから見る夕空は美しく、毎日変化するのが面白い。散歩道として快適だが、旅の想を練るにも好適である。歩きながら、これからの旅の出会いのことも考えたい。