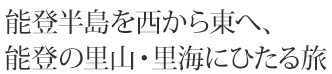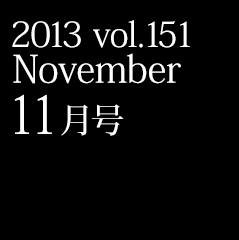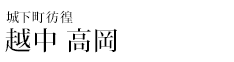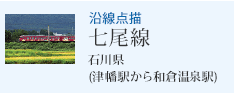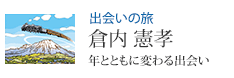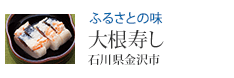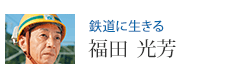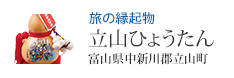七尾線は石川県の津幡[つばた]駅から中能登の和倉温泉[わくらおんせん]駅までの約60キロメートルを走る。能登半島の中央部へと分け入り、1200年の名湯を目指す。この旅では、口能登の「UFO神話のまち」と中能登の「商都」を訪ねた。

夕景の景勝地として知られる千里浜海岸。 写真提供:羽咋市商工観光課
加賀百万石の玄関口、金沢駅から3駅目の津幡駅で北陸本線と七尾線は分岐する。七尾線の起点、津幡駅を離れた電車は「パタッ」と唐突に車内灯が消えた。デッドセクションだ。電車の電化方式の切り替えのことで、北陸本線で利用する交流から、七尾線で使用する直流に切り替える際、一時的に車内が消灯する。
日本海に大きく突き出た能登半島に向かって電車は半島の西に沿って走る。約45分で能登半島の入り口、つまり口能登の羽咋[はくい]駅に着く。半島は口能登、中央部の中能登、そして半島の北は奥能登と呼び分けられている。
駅から西へ行けば千里浜[ちりはま]海岸がある。長く続く砂浜を車でドライブできるのは日本でも唯一、この浜辺だけである。千里浜の砂は粒子が細かく、水分を含むとぎゅっと引き締まり硬くなることから、車の走行が可能になるそうだ。羽咋の海岸は、万葉歌人で越中国守だった大伴家持が、能登一宮の気多[けた]大社に参詣した折に、「志乎路[しおぢ]から 直[ただ]越え来れば 羽咋の海 朝なぎしたり 船梶[ふねかぢ]もがも」と、羽咋の朝の穏やかな海を見て、船があったら漕ぎ出したいと詠[うた]った浜である。とりわけ、日本海の水平線に沈む夕陽の美しさは格別だ。天平の時代に家持が参詣した気多大社は、大国主神が祭神。出雲国からこの地に来臨し、能登国を平定して鎮座したと伝わり、縁結びの神社としても知られる。

田園地帯の中を列車は中能登・七尾を目指して東へと走る。(羽咋駅から千路駅)

創建2100年の歴史を誇る気多大社。能登国の一宮で、国守などが赴任した折、最初に参拝した権威の高い神社だ。

海岸線を車が走る「千里浜なぎさドライブウェイ」。日本で唯一、世界でも3カ所しかないという。
さらに羽咋は、あることで全国的に有名で、一度ぜひ訪ねてみたかった。UFOと遭遇する? 町で、町の一角にある「宇宙科学博物館コスモアイル羽咋」には全国から大勢の宇宙ファンが訪れる。初めて有人宇宙飛行に成功したガガーリンが搭乗した宇宙カプセルや、月面着陸に成功したアポロ宇宙船などの実物大のレプリカが人気を集めている。「宇宙食」は隠れた人気商品だそうだ。
職員の中田昌宏さんによると、羽咋でのUFOの目撃情報は年間約100件。気多大社の古文書には「成山飛行虚空神力自在而」の記録もある。ともかく、付近の空をくまなく見渡してみたが、残念ながらUFOには遭遇できなかった。

「宇宙科学博物館コスモアイル羽咋」。館内には、実際に宇宙から帰還した宇宙船など、貴重な宇宙開発機材を展示している。

「羽咋では、千里浜でのUFOの目撃情報が多いです。口々に、円盤形でオレンジ色の光がジグザグに動いたとおっしゃいます」と、コスモアイル羽咋の職員中田昌宏さんは話す。
羽咋駅を出た電車は海岸線を離れ、羽咋川を渡って中能登に向かい、半島を斜めに横断する。車窓には黄金色の田園風景が広がり、これぞ日本の原風景。この付近には石川県で最大規模の神子原[みこはら]地区の棚田がある。内陸で昼夜の寒暖差が激しい上、清らかな山水で育った「神子原米」は、バチカンのローマ教皇に献上したことで有名で、いまや手に入りにくい人気のブランド米である。
この神子原地区を含めた羽咋市以北の4市5町の「能登の里山里海」は、その地域ならではの伝統文化や風景などを維持保全し、後世に伝えるべき自然として、2011年に「世界農業遺産」に認定された。ここ「能登の里山里海」は世界の財産として認められているのである。
車窓には低く連なる尾根が続き、やがて半島の東の七尾駅に着いた。幾重にも尾根が重なる様子に由来して「七尾」。その山の上には、かつて能登国を治めた畠山氏が築いた七尾城があった。屈指の規模を誇る山城の本丸跡に立てば七尾湾が一望できる。
七尾は国宝「松林図屏風」で知られる長谷川等伯の生誕地で駅前には銅像が立つ。七尾湾に面した町は古い趣のある町並みが残る。御祓[みそぎ]川に架かる朱色の仙対橋を渡ると、小丸山公園に続く商店街がある。一本杉通りだ。北前船の寄港地として栄えたこの七尾の目抜き通りには、国登録有形文化財の商家、和ろうそく屋、醤油屋、茶屋など重厚な構えの老舗が往時の繁栄を物語っている。
「鳥居醤油店」の店主で、現在「一本杉通り振興会会長」を務める鳥居正子さんは「時代とともに、一本杉通りのかつての賑わいも薄れてきました。ですから商店街のみなさんと手を取り合い、みんなで商店街を盛り上げ、活気を取り戻そうと取り組んでいます」と話す。その活動の一つが「語り部処」だ。主人や女将さんが、訪れる観光客に、七尾の伝統や文化を気軽に語ってもてなしてくれる。「語り部処」は現在25店。「能登はやさしや土までも」という古い言葉があるが、優しいもてなしは今も変わらない。
七尾線の終着駅は一つ先の和倉温泉駅。和倉の湯で旅の疲れを癒し、そしてお楽しみはなんといっても能登の新鮮な魚介。風物良し、味覚良しの七尾線であった。

田園風景の中を走るラッピング電車「国宝 長谷川等伯号」。2012年、七尾線電化開業20周年を記念してつくられたもので、他にも「和倉温泉わくたま号」「七尾とうはくん号」「UFOのまち羽咋号」の計4種類が運行している。(羽咋駅から千路駅間)

羽咋市の山間部に広がる神子原の棚田。
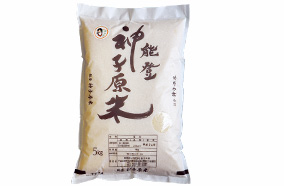
神子原の棚田で採れる神子原米は、もちもちとした食感で冷めても美味しいと評判。

朱色の橋を渡れば600年以上の歴史を有する一本杉通り。文化財指定の建物を含めた50店舗余りの商家や民家が建ち並ぶ。

「鳥居醤油店」の店主にして、一本杉通り振興会会長の鳥居正子さん。「花嫁のれん展」や「語り部処」の立案者の一人の鳥居さんは、「七尾、一本杉通りが大好きです」と話す。



「きもの処 凛屋」の4代目、若林啓さんが渾身の作品と話す『石川の四季』。
「花嫁のれん」は幕末から伝わる能登の「仏壇参り」という儀式に用いるもので、嫁入りの際に花婿の家の仏間にのれんを掛けて、それをくぐることで穢れを払うという。情緒ある町並みが残る七尾の一本杉通りでは、例年4月末のゴールデンウィークから約2週間にわたって「花嫁のれん展」が行われる。
加賀友禅で作られた花嫁のれんは、色柄が華やかで見た目に実に清楚なもので、花嫁のれん展の開催は今年で10年目。通り沿いの商家や民家で150枚以上もの花嫁のれんを公開し、観光客の目を楽しませている。期間中、商店街の通りにはびっしりと人がつめかけて大盛況。今年は8万人もの人が訪れたそうだ。
創業明治40年、「きもの処 凛屋[りんや]」店主の若林啓さんは「加賀友禅は、優雅で華やかであるのが特徴なんです」。「全国的には、“花嫁のれん”といっても知名度はまだまだ低いものです。だからもっと多くの人にぜひ見ていただきたい、知っていただきたいのです。一人でも多くの方に七尾まで足を運んでいただけたら嬉しいです」と言う。一度ぜひ、一本杉通りを訪ねてみてはどうだろう。


「四季の移り変わりの中に、石川県らしい金箔が雪のように舞い、色とりどりの組紐が踊り、さらに桜の舞う様子が花嫁さんを祝い、寿(ことほ)いでおります」と「きもの処 凛屋」の4代目、若林啓さんは話す。

「花嫁のれん展」の開幕行事「花嫁道中」では大勢の市民がかけつけ、花嫁のれんとともに門出を祝う。
写真提供:花嫁のれん展協働委員会