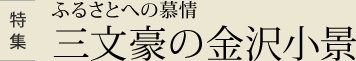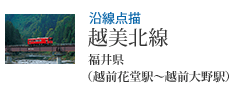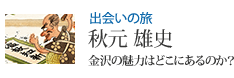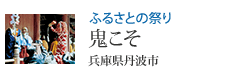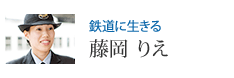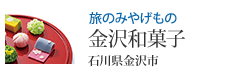![]()
変わりやすい金沢の空はつかの間、雲間から陽が射し込んだかと思うと不意に時雨[しぐ]れる。水分を多く含む大気が、この都市独特の趣きと艶やかさをもたらしているのかもしれない。この金沢に生まれ育った3人の文豪の生い立ちもまた、水と深く関わっている。共通するのは川だ。
金沢城がある小立野[こだつの]台地を挟んで、金沢の市街を2つの川が流れる。川の背後にはそれぞれ卯辰山[うたつやま]と、寺町台地が迫っている。流れが柔らかなことから“女川[おんながわ]”と呼ばれる浅野川と、川幅が広く流れが急な“男川[おとこがわ]”の異名のある犀川で、ともに白山山系に連なる山峡に発して日本海へと注ぐ。


鏡花自身が下絵を書いて指示したという、小村雪岱による『ゆかりのおんな櫛笥(くしげ)集』の口絵。金沢城には天守が描かれ、浅野川、卯辰山が詳細に描かれている。(写真提供:泉鏡花記念館)

卯辰山から眺める金沢の街。ゆったりと蛇行し銀色に光るのが浅野川。右手奥の小高い台地が小立野台地で、その向こう側には犀川が流れる。
泉鏡花、徳田秋聲は浅野川近くで生まれ、卯辰山とともに河岸の風情は2人の原風景である。浅野川を見下ろす卯辰山の展望台に建てられた秋聲の文学碑には、川端康成の「おぼえ書」として、秋聲の文学的意義を讃え「日本の小説は源氏にはじまって西鶴に飛び、西鶴から秋聲に飛ぶ」と刻まれている。
秋聲は浅野川近くの横山町に、明治維新後の没落士族の家に生まれた。生活は困窮し、浅野川周辺を転々と移り住んだという。秋聲が描くのは社会の現実だ。自身のこと、庶民の暮らしを、現代のノンフィクション小説にも通じるリアルな筆致で描き、生涯に600余の作品を残した。
ヒューマニストとしても知られる秋聲は、『挿話』でひがし茶屋街の女性を味わい深く描き、『死後』では父親を、『蕈[きのこ]』では母の死の顛末を克明に描いた。代表作には『あらくれ』『光を追うて』などの傑作があるが、「動かない真実」を「飾りなく」書くという自然主義作家の地位を築いた『黴[かび]』に、浅野川周辺の風景をこう描写している。
「其処は川を隔てゝ直ぐ山の木の繁みの見えるところで、家の周を取り繞[めぐ]らした築土の外は田畑が多かった。…刺戟[しげき]の多い都会生活に疲れた尖った神経が軟らかいブラシで撫でられるやうであった…」。この景観は田畑こそ少なくなったが、趣は今もほとんど変わっていない。
そして金沢市街を流れるもう1つの川、犀川に架かる犀川大橋のたもとの雨宝院[うほういん]で育ったのが室生犀星だ。「ふるさとは遠きにありて思ふもの そして悲しくうたふもの」と、故郷を断ち切れない若き日の哀切を詠った犀星は、『抒情小曲集』の「犀川」で「うつくしき川は流れたり そのほとりに我は住みぬ」と犀川への深い愛情を詠う。
私生児として生まれ、不遇の少年時代を過ごした犀星を慰めたのは、広々とした犀川の風景であり、せせらぎの川音だった。俳人、詩人として犀星はたびたび犀川を詩のモチーフとし、自伝的小説にも描いている。『性に眼覚める頃』では、犀川の水を汲んでお茶を立てる場面から書き出し、「庭から瀬へ出られる石段があって、そこから川へ出られた」と続ける。
上京し、小説家として成功した犀星は、40歳以降はほとんど金沢に戻ることはなかったが、51歳に帰郷した折の講演会では故郷金沢をこう話す。「郷土が私の仕事をたすけてくれているのであります。…裏町とか、川べりにある町の姿なども、いつも書くことがなくなると、眼にうかんでくるのであります」と。
そして、三文豪のなかでも、金沢の風土性と美意識を「もっとも色濃く身につけているのは泉鏡花ではないでしょうか」と話すのは、生家跡地に建つ『泉鏡花記念館』の学芸員だ。

ひがし茶屋街にある「志摩」の室内。通りを歩けば今も三味線、太鼓、唄の素囃子が聞こえてくる。浅野川の近くに生まれた泉鏡花と徳田秋聲にとって、ひがし茶屋街は少年時代から身近な世界だった。2人は後年、茶屋街を描いた作品を残している。(写真提供:金沢市)

金沢市郊外の金石(かないわ)海岸。この風景は犀星文学の原点。金石海岸を舞台に小説も書き、郷愁と哀愁あふれる『抒情小曲集』をまとめた。