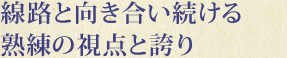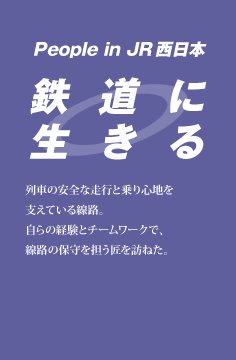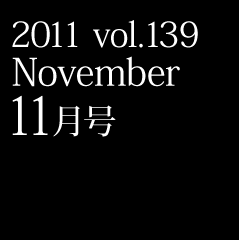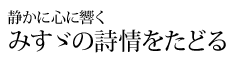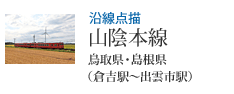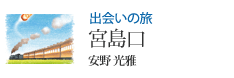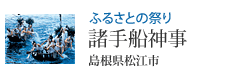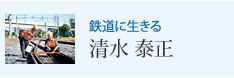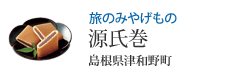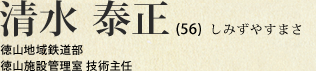

ゲージを用いて行う「分岐軌道狂い検査」。わずかな誤差が列車の乗り心地に影響を与えるため、調整は1mm単位で行う緻密な作業だ。
山陽本線・岩徳線合わせて延長130kmの線路を保守管理している徳山施設管理室。清水はここで技術主任として、主に軌道検査や軌道補修の作業に従事している。保守管理する区間は、山間部あり、沿岸部あり、またダイヤモンドクロッシングと呼ばれる軌道が複数交差する特殊な分岐も存在する。列車の走行の安全性や乗り心地を決定づける線路、わずかな異変も見逃すわけにはいかない。
「軌道検査では、徒歩による検査が欠かせません。片道4km、往復で1日8kmを2人1組で歩きながら軌道の歪みやたわみ、損傷などがないかを検査します。レールを固定するボルトやナットにゆるみはないか、目で見て、疑わしい箇所があればハンマーで叩いて耳でも検査します。ただ軌道のすべてをハンマーで叩いていては時間がいくらあっても足りない。やはり難しいのは、異常か正常かの一瞬の見極めで、どこを、どう見るか、そこで経験が問われます」。
日々の軌道検査の結果をもとに、レール交換やマクラギ交換など大がかりな工事も行われるため、常に検査の精度を高い水準で保つプロの視点が重要となる。レール交換箇所の選定から工事計画書を策定するのも清水の役目だ。
「レール交換をする場合は、予算調達から工事の完成まで2年はかかります。だから2年先を見通して、今見ているレールの交換が必要かどうかを判断しなければなりません」。時間の経過とともにレールがどのように変化するのか、その予想にマニュアルがあるわけではなく、どれだけ現場を見てきたかという経験値がものを言うのである。

作業前の点呼では、お互いの装備の確認から、作業内容の確認、待避のルール確認などを行う。
清水が入社したのは1974(昭和49)年。国鉄時代の小郡[おごおり]保線区に配属されて以来、37年にわたって保線の仕事に従事し経験を重ねてきた。
「技術的なことは、経験を重ねることで身につきます。しかし、保線の仕事でやはり一番大事なのは安全の確保です。現場は列車が走る危険と背中合わせの場所にあります。事故や労災を起こさない・起こさせないが基本ですが、若手の社員は線路の恐さを知らない。だから我々の体験を伝えていくことで安全への意識づけを徹底しています」。
工事で使う道具の一つをとっても、重量がありケガをしやすい。検査や補修作業を行いながら、清水は若手や他の作業員たちの動きにも目を光らせる。
「事故やケガは、気のゆるみから発生します。気のゆるみは“慣れ”から生まれます。作業に慣れ、無意識に作業をやり出した時が一番危ない。だからお互いが常に注意し合って気のゆるみを防ぐこと、チームワークが何より大事になります」。

イヌクギと呼ばれるレールの部品をハンマーで打ち込む。重量がある道具の扱いは、ケガがないようベテラン作業員が指導する。
保線の仕事は検査も補修も、チームでの仕事が基本となる。現場で安全が保たれ、ベストのチームワークが発揮できるよう、清水には常に心がけていることがある。
「この仕事は時間との勝負です。日々の業務でも、線路閉鎖が必要な大きな工事の時でも、時間内で終わらせなければなりません。しかし、人は強制されても嫌になるだけで動きません。リーダーが率先して動かなければチームとしていい仕事ができない。入社間もない頃、それを教えてくれた先輩に本当に感謝しています」。
チームとして安全に、かつ完全に仕事をやり遂げるために、リーダー自らが率先して動く。その信条は37年経った今も変わらない。
技術主任の清水にとって、保線の現場は技能教育の場でもある。日照りの中、雨や雪の降る中、現場で汗や泥にまみれながら自らが培った技能を若手に伝えていく。口で言って分からなければやって見せる。
「私が若い頃は、大声で怒鳴られながら仕事を覚えました。しかし今は時代が違う。リーダーの行動や仕事ぶりを見せることが一番の教育です」。
若手が仕事に集中し、一つひとつの作業を理解してくれることが何よりうれしいと清水。今日もまた、保線のプロとしての技術と心得が現場で引き継がれている。

若手が作った作業確認書や工事要求書に不備がないか確認する。