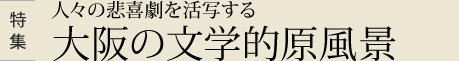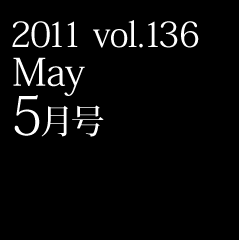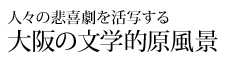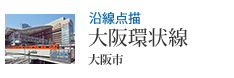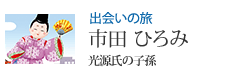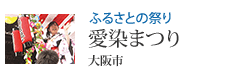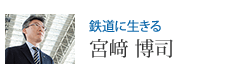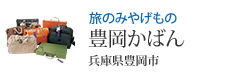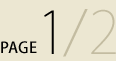
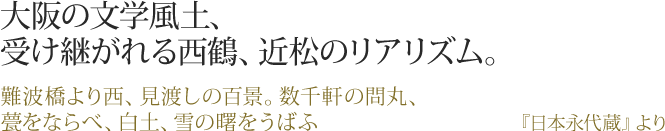
大阪市天王寺区城南寺町に楞厳寺[りょうごんじ]という寺がある。織田作之助が生まれた生玉町や、のちに青少年期を過ごした上汐町もすぐ近くだ。この寺の境内に織田作之助の墓があり、いまも「オダサク」を慕って訪ねてくる人が少なくない。
作之助は1947(昭和22)年、人気作家としてこれからという33歳の若さで、入院先の東京で客死した。さぞ悔しかったにちがいない。井原西鶴(1642から1693年)を尊敬し、『西鶴新論』で西鶴を「大坂で生まれ、大坂で育ち、大坂で書き、大坂で死に、その墓も大坂にある」と書いた作之助には、西鶴のようにならなかったことが心残りだったはずだ。それほど作之助は大阪の風土にこだわった。
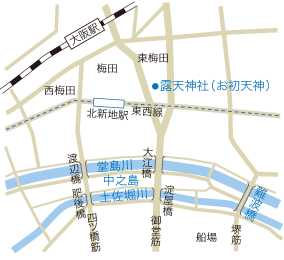
井原西鶴は大阪の文学の源流といわれ、同時に近世日本文学の先駆者の一人だ。その西鶴を生んだルーツが江戸期の大坂の土壌にある。幕府は大坂を直轄地とし、町衆に自治を委ねて経済活動を奨励した。日本中の物産と富が大坂に集まった。そうして「武家の江戸」や「公家の京都」に対して、建前や堅苦しさにとらわれない、自由で闊達な商都の文化が醸成された。
大坂では、成功するのも身を潰すのも己の才覚しだい。そのためには建前よりも本音。なりふりや美醜、対面などにかまってはいられない。そんな富に狂騒する人々の姿を間近に見て育ったのが井原西鶴で、『日本永代蔵』は現在の中之島界隈を舞台に描かれた。中之島を挟んで流れる堂島川と土佐堀川には諸国の蔵屋敷が並び、北浜界隈には豪商の屋敷が軒を連ね、陸は人馬が絶えず、川には無数の荷船が浮かぶ…。
その風景は「金が金を呼び、金が金を生む」という、まさに大坂の繁栄の象徴。西鶴は「金銀を溜むべし。是[これ]、二親の外に命の親なり」という。家柄や格式ではなく、才覚でのしあがっていく人々の逞しさと欲に翻弄される悲喜劇を、西鶴はノンフィクションのような筆致で活写した。観念やイデオロギーにとらわれず虚飾なく冷徹に描くリアリズムは、作之助の作品にも通じ、後の大阪の多くの作家にも受け継がれている。

近松門左衛門とともに大坂文芸の創始者といわれる井原西鶴。「金と欲」に振り回されて生きる人々の逞しさを冷徹な視線で描いた。 (生國魂神社境内の井原西鶴座像)

生國魂神社(大阪市天王寺区)の境内で、西鶴は1日1夜で4000句の矢数俳諧を興行した。近松作品『曾根崎心中』、「生國魂の段」の舞台でもある。
![]()

大阪キタの曽根崎お初天神通り。写真すぐ右手が「露天神社(つゆのてんじんしゃ)」、浄瑠璃『曾根崎心中』を機に「お初天神」と呼ばれるようになった。

「お初天神」の境内には、「曾根崎心中 お初 徳兵衛 ゆかりの地」の碑とともに、二人の像が奉納されている。
そして西鶴と並ぶもう一人の源流が、近松門左衛門(1653から1724年)。人間の内面と浮き世の「もののあはれ」を描いた近松は、大坂の風俗を背景に人情の機微、葛藤や悲しみを見続けた。名作『曾根崎心中』は実際にあった事件を取材し、浄瑠璃に仕立てあげて道頓堀の「竹本座」で初演した作品で、近松は「虚実皮膜論」という芸術論を展開し、「虚構と事実の間の微妙な境界の部分に芸術の真実がある」とした。作之助の作品もまた「虚実皮膜」であり、ほとんどの作品には自身の投影か、あるいは実在のモデルがいる。
西鶴と近松の二人を源流として描かれた作之助の大阪。しかしその一方で、谷崎潤一郎が『細雪』や『春琴抄』で描いた船場界隈の佇まいもまた大阪であり、そこには近松に通じるような耽美な世界がある。谷崎は関西の風俗、風物、自然、料理までを、まるで絵巻物のように繊細かつ格式高い文章で綴っている。作之助と谷崎の大阪を読み比べてみるのも面白い。