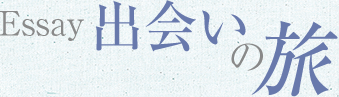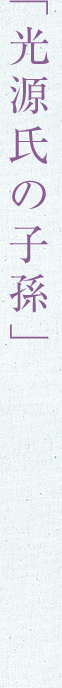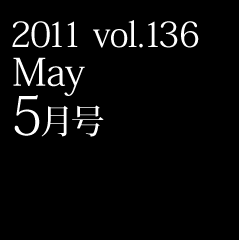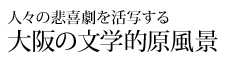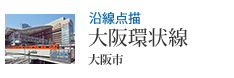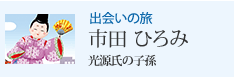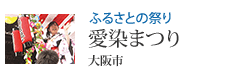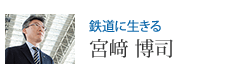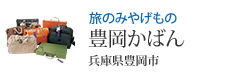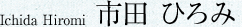
- 京都府立大学国文科卒。京都市在住。OL、女優を経て服飾評論家に。1993(平成5)年にサントリー緑茶CMでACC全日本CMフェスティバル賞を受賞、メモリアルアートの大野屋、セサミンなど数々のCMに出演。テレビ朝日系列・東映「京都迷宮案内」で10年間田舎亭のおかみ役を演じるなど、テレビ、雑誌などで京都を紹介。世界106都市で「きものショー」を開催したり、『源氏物語』を紹介するなど、日本文化を世界に発信している。京都市観光協会副会長、京遊学舎主宰、大谷大学生活創造学科講師。
甚大な災害に心を痛める一方で、しかし日本再生のためにそれぞれの役割を果たさねばならないと思う。
思えば私は、四十年を超える日々、日本国内のみならず、世界の町や村をゆく旅人でもあった。
きものの展示会や講演会。そして、世界の民族服の研究とコレクションには、地図に名前の載ってないような村も訪ねた。
アフリカやアラビア半島の小さな村でも、その独自の言語は、同行の通訳すら通用せず、どこへ行っても最後は日本語、という旅をつづけて来た。
そんな旅人の私も塒[ねぐら]は京都にあり、その暮らしも六十年を超える。
私は講演の時など、自分のキャッチコピーを「大阪生まれのあかるさと、京育ちの品の良さ」というと、みんな笑ってくれるが実は本当なのだ。
「ひろみさんに 元気をもらいました」「ひろみさんは 笑顔が良い」などとほめてもらえる。
これは大阪の特性ではないだろうか。そして京都。私が品が良いかどうかは別にして、都のあった京都は何かと得をしている。ところで京都は年間五千万人の観光客を迎えているが、毎年どこかのお寺が本邦初公開としてお宝を見せてくれる。
いったい、どれだけのお宝があの白い塀の中にねむっているのか。京に住んでいる私ですら、京の冬の旅、夏の旅などにつられて、歴史を生きぬいた宝物を、まさに初めて目にするのだ。
年賀状のそえ書きにこう書いてあった。
「今度、金戒光明寺、養源院など行きます。ついでにあなたのところへも連絡します」と書いてあった。
「ハハーン」、NHK大河ドラマ「江[ごう]〜姫たちの戦国〜」がらみだと思いつつ、うちはついでかと笑った。
六十年を超える京の暮らしには、古風が生きている。
昭和四十年頃まで我が家は中京の格子戸の京町家だった。
小さな庭の北側に戸袋があって、夏は冬の戸障子を入れ、冬はよしずなど夏の戸障子を入れ、暮らしの中に季節毎のしつらえが生きていた。
床の間には季節毎のお軸がかかっていた。正月は、日の出とか富士山。
或る時「それ桔梗か?」と言ったら、母は「アホやな、鉄線花[てっせんか]やがな」と言った。いつか、ポーランドのクラクフ大学に行った時、キャンパスにあふれ咲いていた鉄線花を見て、あの小さな家の床の間を思い出した。
自宅が四条新町の放下鉾[ほうかぼこ]の近くだったので、七月の祇園祭は、暑さとおはやしとざわめきで、一学期の学期末試験は地獄だった。
祇園祭も葵祭も千年を超す祭だ。
天皇家の式服、束帯[そくたい]、十二単[じゅうにひとえ]も千年を超す衣装だ。
世界中のロイヤルコスチュームで、千年間形の変わらないロイヤルコスチュームを持っているのは日本だけだ。きわめてめずらしい。
こわすのは一瞬だけど、守り伝えてゆくのが大変なことだ。
先日、京都駅からタクシーに乗った。
「あ、市田ひろみ先生や」
私が乗るやいなや、
「先生、昨日えらいひとに乗ってもらいました。光源氏の子孫の人ですねん」
「光源氏?実在した人じゃないわよ」
「いや、それが違いますねん。まぁ源氏物語にくわしい人で、廬山寺[ろざんじ]、嵯峨野、宇治まで行きました」
おじさんのハイテンションは続く。
それにしても人の良い運転手さんを二日間で洗脳した旅人も大したものだ。