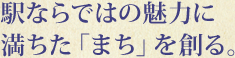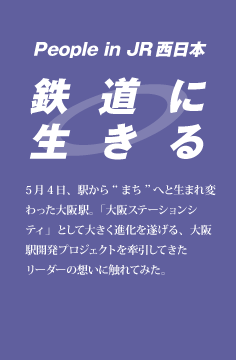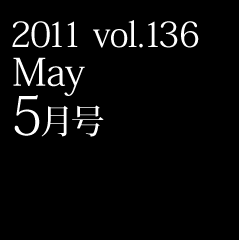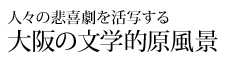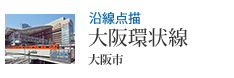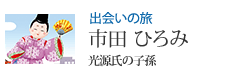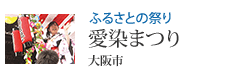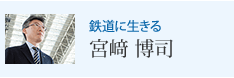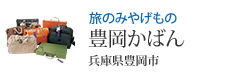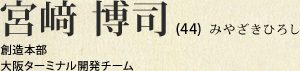
総事業費約2,100億円、延べ床面積53万平方メートル余、工期7年をかけた大阪で最大の開発プロジェクトがついに完成した。宮﨑が大阪駅開発プロジェクトに参画したのは、6年前の2005(平成17)年7月。以来、プロジェクトチームの中心として、工事関係者、駅ビル会社、社外の専門家、入居テナントなど関係各所との企画実現に向けた調整をはじめ、広報活動などを一手に担ってきた。多くの人や組織が関わる大規模プロジェクトである。参画から今日まで、宮﨑はどのような思いで仕事を進めてきたのか。
「これだけのプロジェクトになると、意見の対立もあります。そんな時は、意見が対立する根本原因は何かを考えてきました。ものごとの表面的な部分の解決ではなく、根本の課題を解決するとうまく進むことがあるのです。そのために、各部門やグループ会社それぞれの立場や思いを理解し、多角的にものごとを眺めるように努めてきました」。

スタッフとプレゼン資料作成の打ち合わせ。プロジェクト遂行は、綿密なコミュニケーションが基本。
宮﨑は大阪駅開発プロジェクトに参画する前、2002(平成14)年からの3年間、岡山駅の商業施設開発プロジェクトに携わっている。この時の経験が「ものごとを多角的に見る、それぞれの思いを理解する」ことの原点になったという。「駅にある商業施設だからこそ、他とは違う価値が生み出せるはず。お客様にとって、またテナント様にとって意味のある商業施設はどうあるべきか、何が必要なのか。それぞれの立場から大事に考えました」。岡山駅のプロジェクトでは、郊外にあった地元で評判のテナントを誘致し、その魅力を鉄道ネットワークを通じて全国にPRすることができた。また、土産物の店舗が並ぶエリアに書店を配置したことで、それまで商業施設に立ち寄らなかった通学や通勤のお客様が立ち寄ってくれるようになった。
「何のためにこの施設はあるのか。しっかりと目的を定めることで、あるべき姿が明確になると思います。大阪駅の場合は、駅であると同時にまちでもある。遊ぶ、働く、憩う。利用者それぞれの視点から、笑顔が集うまちの姿を描いてきました」。

「普段使う駅でありながら、ここ大阪ステーションシティに来ることが楽しみ、お客様にそう思っていただけると確信しています」と話す宮﨑。
駅ビル内に誕生する広場の演出も手掛けている宮﨑。そこには、買い物で訪れたお客様、オフィスエリアで働く人たち、そして単に駅をご利用される方にも、この新しいまちのなかに自分だけの居心地のいい場所、憩いの場を見つけてほしいという願いがある。
「大阪ステーションシティには人々が集う広場を8カ所設けています。広場のデザイン監修は、デザイナーの水戸岡鋭治先生に手掛けていただきました。先生をはじめ、多くの専門家や人の縁によってプロジェクトは支えられています」。
数えきれない人、専門家が携わるプロジェクトである。開発チームの若手のスタッフに対しても、きちんと相手の話に耳を傾けることや、自分なりの解決案を考えることを常に求めてきた。
「たとえサブ的な立場であっても、自分が主役のつもりで努力を重ねていると、いつか主役を任される時が必ずくる」。自身の経験でつかんだ真実を、若手スタッフたちに伝えることも宮﨑が掲げたミッションのひとつだ。
「開発、工事に携わる人たちが世界一の駅を創ろうと、誇りを持って創り上げたまちです。ここを訪れる全ての人に、大阪駅が変わった、好きになったと必ず言っていただけると楽しみにしています」。プロジェクトと歩んで来たリーダーの言葉は確信に満ちていた。


大阪ステーションシティをデザイン監修した水戸岡鋭治氏と一緒に「風の広場」の工事の進捗、仕上がりを確認する。