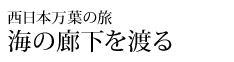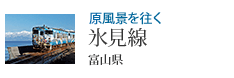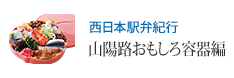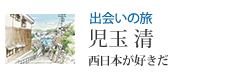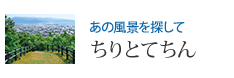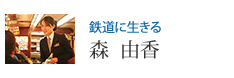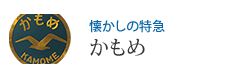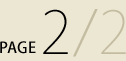
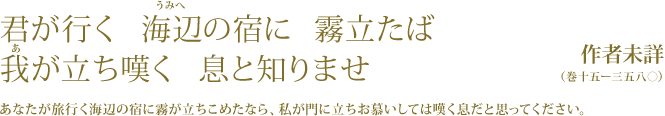
遣新羅使人は、関係が悪化する新羅との厳しい外交交渉を担い、奈良の都を発った。任務は多難で、それゆえ日本海の荒海の向こうに赴く夫を想う妻の嘆きは痛々しい。ふたたび夫と会えることを唯一の希望として、妻は別れの悲しさを「霧」に託して詠んだ。その胸中は「もし海辺の宿に立ち寄って霧が立つことでもあれば、それは恋しいあなたを想う私の嘆きのため息だと思ってください」。
遣新羅使人である夫は海路、いくつもの難所を過ぎて、島々が点在する瀬戸内海を西へと進んで行く。瀬戸内海は、現在では風光明媚の代名詞だが、古代の航海者にとっては危険な海だ。島が無数にあり、風も潮も複雑で速い。岩礁も多く、船が座礁することも度々で、帆と櫂で進む船は漂流することも多かった。そうした困難を重ねつつ、船はやがて風早[かざはや]の港に寄港した。

風早は現在の東広島市安芸津で、緩やかに湾曲する三津湾の西に位置する。三津とは御津とも書き表わし、国や地方官営の港だった。遣新羅使一行は、久々にくつろいだだろう。陸から見る多島海の風景は穏やかで心が和む。そして出航の日、風早の浦には霧が立ちこめている。
夫は、都に残した妻の姿を思い浮かべた。「そうだ、この霧は私を想って都で嘆き悲しんでくれる妻のため息なんだ」。霧に託して夫は妻を、妻は夫を想う。対句でなる夫婦愛の讃歌だが、遣新羅使人の多くは帰らぬ人となった。この歌の夫婦が再会できたのかどうか、それを思うと切ない。


海の廊下を約1カ月かけて渡り、遣新羅使人一行は筑紫国に着く。そして博多湾の西の唐泊[からどまり]に停泊し、ここを故国の最後として玄界灘を新羅へと船出するのだ。漂流もした瀬戸内海の航海も苦難だったが、ここから先は異境であり、日本海は“魔界”だ。
すでに台風到来の季節。荒れ狂う波頭は壁のようにそそり立ち、風は船をなぎ倒すほどに猛威をふるう。大波にのみこまれ、消息を絶つ船も少なくない。そんな荒れ狂う海を目の当たりにした遣新羅使人一行の悲壮な顔が想像できる。「もはや家族と再会できないかもしれない」。絶望とともに、脳裏には都に暮らす妻や家族の姿が浮かぶ。
歌は玄海灘に乗り出した「志賀の荒尾」という水夫を詠んでいる。志賀とは博多湾の北に突き出た志賀島で、「鴨」とは船の名。「也良の防人」とは、博多湾に浮かぶ能古島[のこのしま]の北端の也良岬。ここに防備の見張り台が設けられ、防人が置かれていた。ここからは博多湾が一望でき、晴れた日には対馬まで見渡せる。歌は荒海に消息を絶った荒尾を想う。

「こんな晴れた日には帰ってくるように思われる。いやきっと帰ってくる」という一抹の希望を託した歌だ。遣新羅使人たちの妻や家族、大海で消息を絶ち、帰らぬ人を待つさまざまな人の願いが詠みこまれている。そんな歌にこめられた思いは、1300年の時を超えて現代人の心を打つ。細やかな心情を、自然や風物に託して詠った万葉歌は、今も変わらない日本人の心の原風景をとどめている。
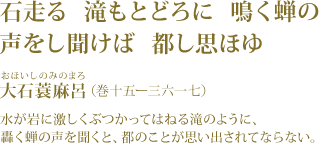
上の歌は巻十五に納められた、「安芸の国の長門の島にして磯辺に船泊りして作る歌五首」のうちの1首で、遣新羅使人が長門の島に停泊したのは夏も盛りを迎える頃だった。激しく降りそそぐ蝉しぐれに、詠み人は遠く離れてしまった都への郷愁を募らせる。
長門の島とは、現在の倉橋島。呉市の南、音戸[おんど]の瀬戸の対岸に横たわる島で、松林が美しい桂浜からは岩国や周防大島が見渡せる。古代から渡来人が住み、遣唐使船などの建造が盛んであった。航海の途中には、ここに停泊して船の整備や修繕を行った。

音戸の瀬戸を渡る復元された遣唐使船
(写真提供:長門の造船歴史館)

倉橋島桂浜の万葉歌碑

鳴きしきる蝉