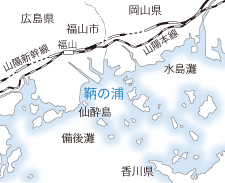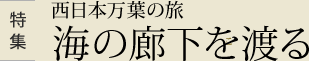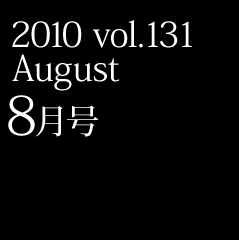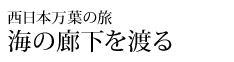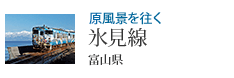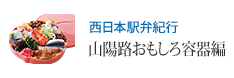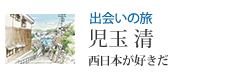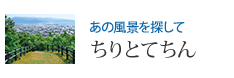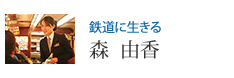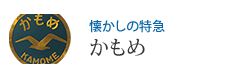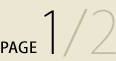
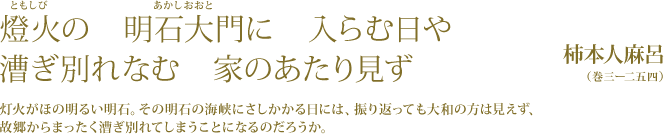
奈良の都を旅立った遣新羅使人の一行は、難波津[なにわづ]の港から船出した。現在の大阪市中央区辺りで、ここから船は途中、潮待ち、風待ちを繰り返して“海の回廊”を九州筑紫へと航海した。約1カ月という長旅だ。
大阪湾の北岸を西に進み、難所の明石大門[あかしのおおと]にさしかかる。両岸が迫った所を「門[と]」といい、船上から見る明石海峡はまさに巨大な門だったに違いない。都から遠く離れた辺境で、行く手の大門はまるで魔物が口を開けて待ち構えているようだ。

明石海峡より望む、播磨灘に沈む夕日。
海上に闇が迫り、激しい潮流がうねりとともに波を逆立て翻弄される船。そんな怖れが望郷の想いを駆り立て、家族のもとへと心を向かわせる。振り返っても都はもう見えない。「ああ、これでもう故郷に戻れないかもしれない、家族ともう会えないかもしれない」。今生の別れを覚悟し、都や家族に別れを惜しむ。
この歌は柿本人麻呂が官人として任地へ赴く折に詠んだものだが、遣新羅使人たちは人麻呂のこの歌を古歌として船上で朗唱したという。彼らの心中も同様であっただろう。遠く東の空を眺める遣新羅使人の姿が浮かぶ。故郷の土を二度と踏めなかった人も少なくない。
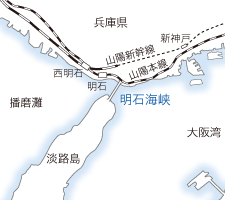
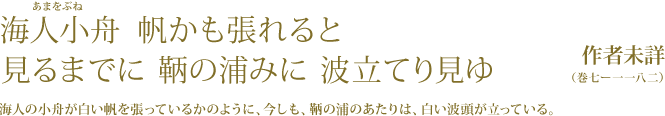
鞆の浦は、仙酔島や弁天島を間近に望む瀬戸内海屈指の景勝地だ。しかし鯛網漁でも知られる鞆の浦の沖合の備後灘は、瀬戸内海の東西の潮流が激しくぶつかりあうところで、昔も今も航海の難所だ。少し風が吹けば海上には白い波頭が幾重にもたち騒ぐ。潮の干満の差が大きく、潮の満ち引きによって、西行き、東行きを決め船出した。
遣新羅使人が乗った船も、風と潮を待って鞆の浦の港に船泊まりした。沖に目をやると、白い三角波がまるで小舟が白い帆を張ってでもいるようだ。遣新羅使人の目には恐怖に映ったに違いない。吠える風の音、白く泡立つ海を前に、行く手の航海への不安や心細さがいっそう募ってくる。逃げ出したい気分だっただろう。なんとしても航海の無事を祈らずにはおられない。そして上の歌に続く歌として、鞆の浦の美しい風景に託して無事の帰還の願いを詠んだ。
ま幸[さき]くて またかへり見む ますらをの 手に巻き持てる 鞆の浦みを(巻7ー1183)。「帰りにふたたび、鞆の浦の美しい風景を眺めてみたい。そのためにもどうか無事に帰還できますように」と、歌には切々とした気持ちが込められている。新羅までの先々、まだまだ長い困難な航海を思えば、焦燥と不安が募ったに違いない。