|
北陸の名湯、山代温泉の歴史は約1300年前に、僧行基[ぎょうき]が白山への登拝の途中に開湯したと伝えられる。この山代温泉を、福田大観[たいかん](のちの魯山人)が初めて訪ねたのは1915(大正4)年の秋、32歳の時である。大柄で、白絣の着物に絽の羽織を身につけ、頭にはカンカン帽をかぶり、素足にぞうりという出で立ちだった。

大観はこの頃、書家、篆刻[てんこく]家(落款印や看板などの印章を作る工芸美術家)として、一部の粋人の間で注目されていた。京都や長浜、鯖江の豪商に招かれ、食客としていくつも額を手がけて高く評価されていたのだ。そんな大観の才能を見抜いた一人が、細野燕台[えんだい]という金沢の実業家で、茶人であり漢学者、書や絵にも優れた文人だった。

そんな燕台の招きで、大観は金沢の細野家の食客として逗留し、燕台に伴って訪れたのが山代温泉だ。山代には、燕台の茶人仲間で趣味を同じくする旅館の旦那衆がいて、それぞれの旅館の看板を大観に彫らせるため引き合わせたのだった。

滞在するにあたって宿舎としたのが「吉野屋」。創業200年以上という由緒ある旅館で、大観のために主人が隠居所として建てていた別荘を仕事場兼住まいとして提供した。大観はここに腰を据えて刻字看板の仕事に励む。この別荘は現在、魯山人寓居跡「いろは草庵」として公開されている。

ベンガラ色の壁をした草庵は、いかにも茶人好みである。玄関を入ると囲炉裏の間、隣の中庭に面して柔らかな光が射し込む明るい部屋で、大観は分厚い木の版面にノミをふるった。それは強情なほど力強く、大胆で個性的な字体だ。同じ湯[ゆ]の曲輪[がわ]にある旅館「あらや滔々庵[とうとうあん]」や「白銀[しろがね]屋」でも、大観は堂々とした刻字看板を制作しているが、文字の部分を浮き出す陽刻彫、反対に文字を彫り込む陰刻彫など、それぞれ書体も異なって独創的だ。ほかに絵や書なども残しており、大観と縁の深い旅館では作品を見ることができる。

山代温泉で約半年を過ごし、その間、趣味人の旦那衆と草庵の囲炉裏を囲み、北陸の海や山の美味とともに酒を酌み交わして毎夜のごとく、芸術から料理の話など、さまざまなことを語り合ったという。稀代の趣味人と交わったこの山代温泉での滞在が、大観の感性を触発し、美意識に強い影響を与えたに違いない。自然美礼讃を信条とし、生活の中にこそ真の芸術が必要であるとする「雅美生活」という、魯山人がかたくなに追求した独自の美意識である。
|
|
 |
|
 |
|
| 魯山人が旅館「吉野屋」の依頼で彫った陽刻彫の刻字看板。魯山人の彫りの特徴は、垂直にノミを突き落とし、字は堂々と力強く立ち上がる。 |
|
 |
|
| 写真上は魯山人が寝間として使っていた居室。写真下は玄関横の囲炉裏の間で、吉野屋の主人をはじめ山代温泉の旦那衆がこぞり、美術談義に花を咲かせた。 |
|
|
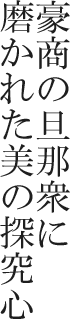 |
|
 |
|

福田大観、のちの魯山人が刻字看板の仕事のため寄宿した「いろは草庵」。外観はベンガラ色で、内部には茶室があり、茶人好みのしつらえとなっている。 |
|

「いろは草庵」の前の通り「湯の曲輪」を行くと、山代温泉の共同浴場である「総湯」が建つ。ここは旧吉野屋旅館があった場所。 |
|