|
 |
 |
堤から眺める錦川は穏やかな表情である。広い河川敷は、夏の夜は涼を求める人びとで賑わう。ところが、雨期や台風時には想像を超えて形相を一変させる。大きな河川がほかになく、上流の中国山地の山々に降る雨はことごとく錦川に集まり、大量の土砂や流木を伴って下流へとかけ下る。橋などいともたやすく流し去ってしまう。

岩国藩にとって、「流されない橋」は積年の悲願であった。悲願の達成に挑んだのが3代藩主広嘉[ひろよし]である。岩国藩は小藩ながら、文武両道と人材の育成に励み、製紙や山林の開墾、干拓事業などで産業を奨励し、勤倹貯蓄を美風とした。そんな藩風が、不落の橋の研究を邁進させたのだろう。広嘉は向学心厚く、科学や技術にも興味を示した。参勤交代の江戸の帰路、名橋の誉れ高い甲斐国の橋脚のない猿橋の構造を見聞するために寄り道をしたと言われるほど研究に熱心だった

そんな折、父広正が苦心して架橋した橋が洪水で流された。広正も藩民も悲しみ沈んで呆然と流れさる橋を眺めるだけだった。広嘉はいよいよ本格的に不落の橋に挑み、児玉九郎右衛門という大工棟梁を甲斐や長崎に向かわせ、橋の形状や構造の調査を命じる。

ちょうどそんな頃、広嘉は独立[どくりゅう]という明国から渡来した禅僧と出会う。病弱の広嘉は、病気治療のために独立を長崎から招いたのだが、独立から『西湖遊覧志』という書物を見せられ、即座に「これだ!」とひらめく。

西湖は中国浙江省杭州の名勝だ。その西湖には、小さな島から島へと6つの石のアーチ橋が連なり架かっている。広嘉は絵図に食い入り、橋の連なりに合点した。猿橋は橋脚のない木の橋だが、川幅がまったく違う。石造りのアーチでは錦川の川幅は広すぎる。やはり木の橋…。広嘉は気がついた。流されない橋の要は「橋脚が流されないこと」である。桁の橋では錦川の洪水に耐えることはできない。広嘉は西湖の6つの架け橋から、木橋でも流されない橋の着想を得たのだ。

不落の橋はそうして実現へと向かう。大工棟梁、九郎右衛門に設計を命じ、錦川に島に代わる堅牢な石組みの橋脚を築き、1673(延宝元)年に五連のアーチ構造の橋が遂に完成した。藩主広嘉、大工九郎右衛門、そして完成を待ちわびた岩国の人びとの感動は想像するに難くない。しかし、完成8カ月で、悲痛の叫びも遠く橋は濁流に呑み込まれた。土砂が堆積した川床は地盤が緩く、敷石が水勢で掘り起こされて橋台が崩壊したのだ。その後、川床に石を敷き詰め、水の勢いを弱め、橋台をさらに強固に改良した。

橋は翌年に再建。工期はわずか5カ月(創建は3カ月)。完成の折には、架橋に関わった者は褒賞を賜ったという。以来、錦帯橋は美しい姿を錦川の川面に映しつづけている。橋長193.3m、幅約5m、最高部12m。世界で最も美しい木の橋と称賛されている。しかし、錦帯橋の本当のすごさは「構造の独創性と、日本の伝統的な木造技術の創意工夫の巧みさです。工法の確かさは現代の技術をもってして改善の余地はありません」と、代々、大工の家系として錦帯橋を守ってきた海老崎粂次[くめつぐ]さんは話す。
|
|
 |
|
 |
|
| 錦帯橋を渡ってすぐの吉香公園の入口に建つ3代藩主広嘉像。 |
|
 |
|
| 「錦帯橋春景図」。葛飾北斎など多くの絵師、画家が錦帯橋の四季を描いている。錦帯橋は四季それぞれに美しい。
(作者不明・江戸時代/岩国徴古館蔵) |
|
 |
|
| 岩国城址に残る築城時の石垣。錦帯橋の橋脚は築城の石組みの技術を応用している。橋台は真上から見ると上流に対して、船の舳先のように尖った紡錘型をしている。水流の勢いをそぐ働きをする。 |
|
|
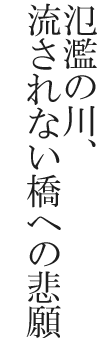 |
|
 |
|

錦川の河畔は全国的に知られた竹林の名所。護岸補強のために江戸時代から竹林が管理されていた。 |
|

橋板には、鍛冶師、白鷹幸伯さんが鍛練した釘が使われている。この釘は寺社建築の名棟梁西岡常一氏が「千年の釘」と呼んだことで知られる。 |
|

平成の架け替え工事で棟梁を務めた大工、海老崎さん。錦帯橋を知り抜いた棟梁の口ぐせは「手間をかけんと納得できる仕事はできん。効率至上主義はいかん」。 |
|