|
石見銀山の歴史は神屋寿禎が開発に着手した1526(大永6)年からおよそ400年間である。江戸中期以降は鉱脈が乏しくなり産出量が激減した。その後、明治、大正時代には民間会社が鉱山経営に乗り出したものの、1923(大正12)年に輝かしい鉱山の歴史は幕を閉じた。やがて銀山は山中に埋もれ、石見国の政治・経済の中心だった大森の町も世間から忘れられ、過疎の町と化していく。若者は町を離れ、高齢化が進み、空家が目立つようになった。

町に住む人々の中には「何もない田舎」「廃虚の町」などと揶揄されて心を傷めた人は少なくない。しかし結果として、「今日までいたずらな開発が行われなかったのが幸いだったのです」と大森町文化財保存会会長の吉岡さんは話す。やがて郷土を愛する住人の中で「大森の町はこれからどう生きていくべきか」を模索する動きが芽生え、そうして、石見銀山遺跡や町並み保存をめざして「大森町文化財保存会」が生まれた。それは1957(昭和32)年のことで、町内の全戸が加入していることに驚かされた。戸数約250、人口450人の町が大田市と協力して改修保存した家屋は130棟以上にもなる。

かつての代官所、郡役所が解体されようとした時に、住人全員が保存を願い、建物は無償で観光開発協会に払い下げられた。改修が施された建物が現在の石見銀山資料館である。同じように、かつての裁判所は町並み交流センターに生まれ変わり、町内でひときわ目立つ熊谷家の屋敷は、造りは昔のままに新しく甦った。住む人の中には個人的に空家を購入して改修保存している人もいる。人びとの努力はそれだけではない。銀山遺跡周辺の草刈りや掃除も定期的に行っているのだ。そういう努力が伝統の佇まいを守りつつ町並みを文化的な景観にし、埋もれた銀山を貴重な歴史遺産に変えていった。

町が魅力を取り戻すと、地元に残る若者や、都会から移住する若者が増えた。自然とともに時間がゆっくり流れる大森の町に惹かれて暮らすようになった外国人、創作活動の場とするアーティスト、大森を拠点に事業を展開し全国に向けて生活情報を発信する人もいる。そういう新しい風が、町の新しい歴史を刻み始めている。そしてそこに住む人々に共通しているのは「私たち大森の住人、一人ひとりが歴史をつくっている」という意識だ。少なくとも彼らがこれからつくろうとしている歴史とは、都会的な時間で流れるものではない。

石見銀山生活文化研究所の松場さんはこう話す。「スローフードがイタリアの小さな町に端を発したように、この大森の小さな町が人と環境が共生して暮らす一つのモデルとして、世界にメッセージを発信できるような、素朴だけれど人びとが協力しあえるような、そんな町であってほしいと思っています」。

世界遺産登録で石見銀山遺跡が認められた評価のなかに「環境との共生」「文化的な景観」がある。銀山の産業遺跡としての価値もさることながら、日本の原風景を感じさせる山や森や川、そういった素晴らしい自然と共生しながらスローに生活する暮らし方の中にこそ、訪れる者を惹きつける大森の魅力が隠されているのかもしれない。 |
|
 |
|
 |
|
| 国の重要文化財である熊谷家住宅。熊谷家は年寄役で、大森町内で最大規模の住宅。建物は文化年間(1804〜1817年)に建てられたもので、平成13年から5年をかけて保存修理された。写真下は熊谷家住宅の玄関・土間。 |
|
 |
|
 |
|
| 石見瓦の家並みが美しい大森地区の伝統的な歴史景観。左の山に突き出て見えるのは大森の地名の由来にもなった楠の大木。 |
|
 |
|
| 代官役所跡にある石見銀山資料館。もとは郡役所で解体されるところを町の人々の要望で保存された。 |
|
|
|
|
|
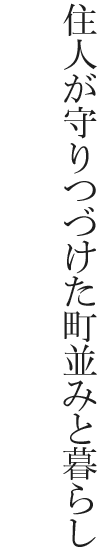 |
|
 |
|

羅漢寺には、銀山で亡くなった大勢の鉱山労働者を弔い供養するため、25年をかけて造られたという五百羅漢の石像が安置されている。 |
|

代官所付近を流れる銀山川。のどかな山里の風景だが、銀山が最盛期の町は人馬の往来が昼夜絶えない賑やかさだった。 |
|

訪れる人のために路上には大森地区の地図が描かれている。 |
|
 |
| 大森町の呉服商だったご主人の故郷に戻り、この地に住みながら独自の視点で生活提案を全国に発信する石見銀山生活文化研究所・所長の松場登美さん。「ゆっくりと流れる時間の中で、自然と共生する大森の暮らし方を、ブームに左右されずに守っていきたい」と話す。 |
|
|