|
飛鳥時代を通じて王宮は2度、明日香の地を離れる。飛鳥板蓋宮の後に難波長柄豊碕宮[なにわながらとよさきのみや]に遷都し、中大兄皇子は近江大津宮にて天智天皇として即位する。再び王宮が明日香の地に戻り、飛鳥浄御原宮に置かれるのは壬申[じんしん]の乱後、大海人皇子[おおあまのおうじ]が天武天皇に即位する673年だ。『日本書紀』には「浄御原は岡本宮の南に宮室を営む」とある。持統天皇の宮でもあった伝承の場所は香具山を望む田園のただ中で、確かな所在はまだ明らかになっていない。

発掘とは史実を解き明かす作業であり、藤原宮[ふじわらのみや]を現代に甦らせたのも、史実の検証と発掘の成果である。大和三山に囲まれたほぼ中央の位置にある藤原宮は、飛鳥時代後期の694年に明日香の地から遷都した新しい王宮である。藤原京を計画したのは天武天皇だ。唐の長安に倣って中心に大極殿を据え、南北に朱雀大路が貫く。条坊制によってつくられた日本で最初の本格的な計画都市で、為政者の律令国家への情熱と意図を明確に示している。調査によって宮域はほぼ1km四方だったと判明しているが、京域の全貌はまだ正確には特定されていない。その後の平城京や平安京にも劣らない規模だったと推定されている。

しかし、この藤原京は、持統・文武・元明天皇3代のわずか16年で終焉し、710年に平城京に遷る。遷都と同時に飛鳥時代は幕を下ろすことになるが、興味深いのは、藤原京と平城京がつくられた場所の相互の位置関係である。平城京は、藤原京の朱雀大路の北方向の一線上に合致するという点である。さらにいえば、この線を南に辿っていくと、その先には天皇陵をはじめとする古墳が密集する“王墓の地”につながるというのは単なる偶然だろうか。世紀の大発見と騒がれた高松塚古墳もその線上にほぼ重なる場所に位置している。この高松塚古墳、そしてキトラ古墳の発見は、千数百年の時を超えて甦った古代と現代をつなぐロマンとして多くの人びとの関心を集めている。壁に描かれた極彩色の人物像や神獣、星宿図などの芸術的水準の高さに言葉を失った。被葬者は謎だが、発見で明らかになったのは東アジアの文化的な影響を強く受けていたことだ。

石舞台古墳も飛鳥の象徴である。その巨石は大地に根を張ったように威風堂々として、見る者を圧倒する。石舞台古墳は7世紀はじめの上円下方古墳で、その巨大さと、巨石を組み上げた古代人の技術に驚かされる。現在の姿は、古墳を覆っていた封土が幾歳月の風雪ではぎ取られ、地表に露出したものだが、この石舞台のある島庄[しまのしょう]という場所は蘇我氏と関係が深い地であることから、馬子の墓ではないかといわれている。

明日香村一帯には、謎めいた石の構造物や異形の石造物が路傍に数多くある。ユーモラスな表情の石の像、奇妙な面貌の石の像、幾何学文様が彫られた巨石、それぞれが男、女の石像、山王権現、亀石、猿石、二面石、酒船石などと名付けられ、造られた時代も目的もはっきりと分からない。

石造物は不思議な笑みを浮かべ、ただ黙ったまま時空を超えてそこに在りつづけている。好奇心を駆りたてる古代への入り口が、まだ土の下には数多く眠っている。人は、そんな飛鳥に魅かれて出かけるのだろう。

取材撮影協力:明日香村教育委員会文化財課、桜井市教育委員会文化財課、橿原市教育委員会文化財課、宮内庁書陵部畝傍陵墓監区事務所 |
|
 |
|
 |
|
| 写真は公園として整備されている藤原宮跡に大極殿をCGで再現。豪壮な建造物で藤原京の壮大な都市の全容を想像させる。(写真提供:橿原市観光課) |
|
 |
|
| 聖徳太子生誕の地で、自ら建立した橘寺には二面石[にめんいし]がある。表は笑い、裏は怒りの表情。 |
|
 |
|
| 7世紀の造作と考えられる亀石。飛鳥には不思議な石造物が数多くある。 |
|
|
|
|
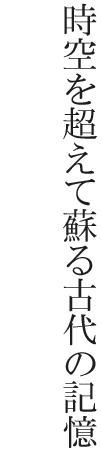 |
|
 |
|
 |
| 石舞台古墳の玄室は長さは約8m、幅3.3m、高さ4.7mもある。巨石を組み立た当時の技術の高さに驚かされる。 |
|
 |
| 吉備津姫王墓[きびつひめのおおきみのはか]の敷地内に鎮座する猿石。4体ある石像はそれぞれの姿から、女、山王権現、僧、男と名づけられている。 |
|

抽象的な文様が施された酒船石。酒や薬をつくるのに用いられたといわれる。小高い丘陵の上に無造作に置かれているように見えるが、丘陵は人為的に盛土したものという。 |
|
|