|
 |
 |
明日香は和みに満ちた里村だ。風景を彩る山野、川も田畑も大和棟の集落の佇まいもたおやかで、ゆったりと時は流れる。のどかなこの風景の中に、1300年以上も前の栄華の跡が眠っている。「飛鳥を訪れるのは幻を見に行くようなものだ」といわれたりもするが、想像力を逞しくすれば、訪ねる先々で飛鳥時代が立ち現れる。甘樫丘も風光を楽しむだけの展望台でないことが分かる。

甘樫丘は、飛鳥時代前期に主導的な役割を果たした蘇我氏が邸宅を構え、周囲に柵をめぐらせて軍事上の要害とした天然の城塞跡である。飛鳥時代とは政争と政変の激動の時代でもあった。『日本書紀』では時代前夜の552年に仏教公伝を記している。仏教は最新の外来文化で、仏教をめぐって崇仏派と排仏派に分かれて国内は激しく衝突した。外来文化を積極的に取り入れて新しい国づくりを推進しようとしたのは、新興の一豪族だった蘇我氏、そして厩戸皇子(後の聖徳太子)だ。排仏派は名門豪族の物部氏だったが、抗争の結末は蘇我氏が物部氏を滅亡させ、その後の政治の実権を掌握する。

これを機に、蘇我稲目[そがのいなめ]、馬子、蝦夷[えみし]、入鹿[いるか]の4代におよぶ蘇我氏全盛の時代を迎える。飛鳥時代の幕を開けた推古天皇は蘇我氏の外戚である。日本最古の仏像、飛鳥大仏を安置する飛鳥寺も、仏教とともに伝来した渡来の技術と多くの匠らが建立した豪壮な大寺だったが、それは蘇我氏の権勢を誇る氏寺でもあった。こうして飛鳥時代には東アジアの技術や文化を政策的に受け入れつつ、仏教文化を基調とした飛鳥文化が育まれていく。

蘇我氏の権勢は絶大であったが、それがために歴史上有名な造反劇が勃発する。645年の大化改新である。主役は中大兄皇子[なかのおおえのおうじ](後の天智天皇)と中臣鎌子[なかとみのかまこ](後の藤原鎌足)で、舞台は飛鳥板蓋宮[あすかいたぶきのみや]の大極殿[だいごくでん]。廷臣が居並ぶ席で中大兄皇子は剣を抜き、入鹿に襲いかかった。他方、甘樫丘の蘇我氏の邸宅も中大兄派に包囲され、蘇我本宗家の栄華はここに潰える。皇極[こうぎょく]天皇は孝徳天皇に譲位し、中大兄皇子を太子とした新政権が誕生する。年号も新たに定めることとなり、「大化」とした。大化改新がめざしたのは、唐の律令制度にもとづく中央集権的な政治体制の確立である。官僚体制を整え、公地公民制、中央集権的地方行政、班田収授法、新税制など、新しい国のしくみを細部にわたって規定した「改新の詔[みことのり]」は、その後の日本の国家体制の根幹となった。

歴史的な政変の舞台となった伝飛鳥板蓋宮跡が、明日香村岡という里にある。発掘調査の後、埋め戻された宮跡は整備されて広々とした田園に囲まれている。この岡の地は、舒明[じょめい]、皇極、斉明、天智、持統の5人6代の王宮が置かれた場所であろうとされているところで、飛鳥岡本宮、飛鳥板蓋宮、後飛鳥岡本宮、飛鳥浄御原宮[きよみはらのみや]があった。これまでの発掘調査によって、この一帯には宮殿のほかに、渡来の技術や知識を取り入れて建てられた大規模な建造物や石敷広場、池泉庭園、寺院の伽藍や塔が聳える豪壮な都であったことが明らかになってきている。

今はのどかなこの場所に、いくつもの巨大な建造物からなる都市空間があった。これらの王京を総称して「飛鳥京」という。京とは、宮が置かれた都市、つまり首都であり、皇極天皇は飛鳥京のようすを歌に詠んでいる。「人多[さわ]に 国には満ちて あじ群[むら]の 行き来は行けど …」。都には人が満ち満ちて、まるで鳥の群れが騒ぐように賑やかであると。この歌から、華やかな王京の通りを大勢の人が賑やかに往来しているさまが伺える。 |
|
 |
|
 |
|
| 伝飛鳥板蓋宮跡。中大兄皇子と中臣鎌子が蘇我入鹿を暗殺した舞台。 |
|
 |
|
| 大官大寺跡。道の先に見えるのは甘樫丘。朝廷の寺として格式の高い寺だった。今は面影はないが、壮大な敷地に法隆寺五重塔の2倍半もある九重塔があったといわれる。 |
|
 |
|
| 川原寺跡。川原宮の跡に建てられた天皇の菩提を弔うための寺で、飛鳥三大寺の一つに数えられた大伽藍を擁した大寺だった。 |
|
 |
|
| 聖徳太子生誕の地に建つ橘寺。聖徳太子創建七カ寺のひとつ。創建当時は66の堂塔坊舎をかかえていたと伝わる。境内には飛鳥石造物の「二面石」が立つ。 |
|
|
|
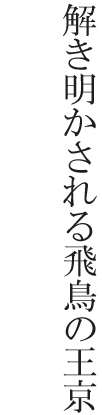 |
|
 |
|
 |
| 飛鳥寺に安置されている釈迦如来像、飛鳥大仏は飛鳥時代の姿そのままの最古の仏像。飛鳥寺は蘇我氏の氏寺として百済の匠のさまざまな技術を結集して建造された。仏教伝来と蘇我氏の権勢の象徴。 |
|

飛鳥川上流の周囲をなだらかな山々に囲まれた地に飛鳥稲淵宮跡がある。棚田の景観が美しい。 |
|
|