 |
 |
 |
 |
大和朝廷が成立したのは
現在の奈良県南東部といわれる。
桜井はその交易の中心地として
古代から栄えた。
万葉の風景を残す山の辺の道の
南の起点となる桜井を訪ねた。 |
 |
 |
 |
 |
 |
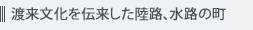 |
桜井線は奈良〜桜井駅間を、奈良盆地の東を南北につらなる山々に並んで走る。車窓から眺める風景は『古事記』に記される青垣の山々だ。その山麓を縫うようにつづくのが日本最古の道の一つといわれる山の辺の道である。

この道の南の起点は桜井駅だ。桜井は古代、日本の中心的な役割を果たした土地である。初期大和朝廷が成立したところともいわれる交易の要所だった。桜井を中心に主要な街道が東西、南北に通じていた。東は伊勢に至り、西は葛城を経て河内、難波へ。南の山田道も万葉古道の一つで飛鳥京に通じた。そして山の辺の道は北方の奈良に通じるが、都が平城京に遷るまでは桜井をめざす上りの道だった。

そして水路も重要な交通網で、町の北を流れる初瀬川(大和川)が大陸のさまざまな文化をもたらした。難波から舟で川を遡上し、辿り着いた渡来人が上陸したと伝えられている川堤には、仏教伝来地を示す石碑が立っている。 |
 |
 |
 |
 |
| 大神神社近くの高台から大和平野を望む。海に浮かぶ島のようにぽっこりと頭を出しているのが大和三山で、右に耳成山、中央に畝傍山、左側のなだらかな丘陵が香具山。 |
 |
 |
いくつもの街道が交差する桜井は古代より人や物が行き交う町。現在でも万葉の歴史を訪ねて多くの人が訪れる。 |
 |
 |
初瀬川(大和川)のほとりに立つ仏教伝来之地碑。百済の王の使節が訪れ、日本に仏教を伝えた場所といわれる。 |
 |
 |
山の辺の道は桜井から奈良まで南北約30kmにおよぶ古道。なかでも三輪山麓に沿って歩く桜井から天理までは大神神社をはじめとする社寺や古墳群など、伝承にちなむ場所が数多く点在し、万葉の面影を感じさせる。 |
 |
 |
 |
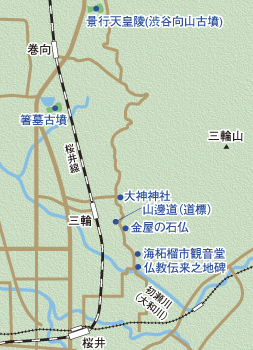 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
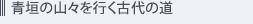 |
駅前の通りを過ぎて、初瀬川と名前を変えた大和川に架かる橋を渡った辺りから山の辺の道はいよいよ古道の雰囲気を色濃くしてくる。大和棟の小さな集落の辻に「海柘榴市[つばいち]跡」と書かれた標識が立っている。この辺りは、6世紀にすでにその名が記されている日本で最古の市場「海柘榴市」がたった場所とされている。

その村はずれには、釈迦如来像と弥勒菩薩像の金屋[かなや]の石仏があり、日本でも指折りの名石仏だという。果樹を栽培する畑の傍を通る道端に、小林秀雄の筆で「山邊道」と書かれた小さな石の道標がいかにも慎ましやかだ。途中に、万葉集の歌を刻んだ石の道標が置かれ、その素朴さが山の辺の道の興趣をそそらせる。

山裾を這い上がる風が気持ちよく、果樹畑や竹林、雑木林、農家の庭先を通って時に細く、時に曲がりくねってつづくのどかな道を歩くと、自然に気持ちが和らぐが、素朴な疑問が一つあった。平坦地でなくどうして山腹を這う道をつくったのだろう。この疑問に対して、こんな説がある。

古墳時代(3〜7世紀)以前の縄文、弥生時代の大和盆地は湿潤で沼沢も多く、平地部ではかえって往来が困難なため、山麓の道が重要な交通路だったのだろうという。記紀以前の古い道なのかもしれない。 |
 |
| 山の辺の道の南端、街道が交差し、初瀬川(大和川)も近い金屋地区には日本最古の市といわれる海柘榴市[つばいち]があり、交易と交通の要所としておおいに賑わったという。街道沿いには現在でも風情のある町並みがつづく。 |
 |
 |
| 金屋の集落のはずれに祀られている金屋の石仏。祀られている2体の石仏は右が釈迦如来像、左に弥勒菩薩像といわれる。 |
 |
 |
| 古道の佇まいを残す山の辺の道を歩く。道脇に立つのは小林秀雄の書による「山邊道」の道標。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
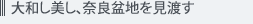 |
桜井駅から距離にして約5km、緩やかな勾配の山道をのんびり1時間も歩くと、そこは「三輪さん」と呼ばれて親しまれる大神神社[おおみわじんじゃ]の神域だ。三輪山は、聖なる山として崇められるご神体で、大神神社は日本最古の神社の一つといわれる。歴史家の説によれば、三輪信仰は縄文時代まで遡るだろうという。三輪山近くにある、前期古墳時代の墳墓としては最大規模とされる渋谷向山[しぶたにむこうやま]古墳、箸墓[はしはか]古墳が傍証の一つになっている。

古墳の規模からして、少なくとも三輪山の裾野一帯に大きな政治勢力があったことは容易にうかがえる。おそらくそれは、後に飛鳥時代を築く統一国家の基盤となる勢力だったのではないだろうかと、つい想像力を募らせてしてしまうのは、たおやかな風景のせいかもしれない。山の辺の道はこの辺りでは標高も高く、展望が開け、平らかな奈良盆地が手にとるように見渡せるのだ。

大和三山の向こうに、城壁のように連なるのは二上山、葛城山、そして金剛山。ふと路傍の石碑に目をやると『古事記』の一節が刻んであった。「大和は 国のまほろば たたなづく 青垣 山ごもれる 大和し美し」。まこと、大和し美し。大神神社の参道を下りると三輪駅だ。山の辺の道は、古代を垣間見せてくれる散策の道である。 |
 |
| 日本最古の神社と言われる大神神社。後ろにそびえる三輪山(写真下)を御神体としているため、古来より本殿がない。 |
|
 |
| 大和三輪の名物は手延べ「三輪素麺」。農家の庭先で素麺を寒気に晒す風景は三輪山麓一帯の冬の風物詩で来歴は大神神社に由来するほど古く、山麓の集落には昔から代々の素麺をつくる家が多い。龍見製麺所の龍見昭さんも息子さん夫婦を含め、家族ぐるみで伝統の手延べ素麺をつくっている。「最近は生産者もずいぶん減りましたわ。伝統の三輪素麺を守っていかなあかん思うてます」と語る。 |
|
 |
 |
 |
|
 |