|
萩をめざして中国山地から流れ下る阿武[あぶ]川は、日本海にそそぐ直前、橋本川と松本川に分かれる。萩は、その二つの川に挟まれた中洲を中心に形成された、毛利氏36万9千石の城下町である。

萩を語るには、関ヶ原に遡らなければならない。1598(慶長3)年、豊臣秀吉の死によって国内の政治情勢に変動が生じ、やがて1600(慶長5)年の関ヶ原の戦いへとなだれこむ。徳川家康が率いる東軍と、石田三成を主将とする西軍との天下分け目の決戦である。

広島城に本拠を置き、中国8カ国、112万石を領する毛利輝元[てるもと]は、避けることができない二者択一を迫られた。家康と対峙する理由を持たなかったが、五大老に任じられ豊臣家へ節を守るという武将としての義理や太閤秀吉への恩愛など、複雑な心境に決着をつけられないまま輝元は出陣したのだろう。

豊臣政権の五大老は、徳川家康、毛利輝元、前田利家、宇喜多秀家、小早川隆景(死後上杉景勝)だった。この五大老のうち家康を除く4人の動きを見ると、前田利家は関ヶ原役前年の1599(慶長4)年に死亡しているが、あとの3人はいずれも西軍に属することとなった。このとき薩摩の島津も西軍についている。

東軍10万、西軍8万が激突した関ヶ原の戦い。源平の対立以来、日本の政権争いは東西対決の形で展開されているといっても過言ではない。平氏を倒した東国勢の源氏を祖とする徳川東軍が、関ヶ原で西軍を打ち負かし、そして二百数十年後に、またもや東西対決となり、今度は西国の薩長同盟(毛利・島津)が徳川の東軍を打倒し、武家政治は終焉することとなる。

関ヶ原に破れた大坂方は家康と和睦を結んだが、西軍についた大名の改易、減封の処置が次々と発せられ、毛利は中国8カ国から萩に移封された。112万石から36万9千石に転落した毛利氏は、主要な家臣団を連れて広島から萩に移ってきたが、家臣たちの俸禄も大幅な減石になるという、一大緊縮財政に直面することになったのである。輝元は困惑し、「とてもこの微禄ではやっていけない。大名であることを返上する」と、異例の上訴を考えたといわれている。

萩築城の縄張り初めは、1604(慶長9)年に行われた。当時まだ海に孤立した指月山[しづきやま]を取り込んでの築城は、埋め立てからはじまる難工事だった。突貫工事で築城を急ぎ、山と海と2本の川という天然の要害に、石垣と堀を加えた城郭を完成させたのは4年後の1608(慶長13)年だった。築城と同時に城下の町割も進められ、整然とした城下町が三角洲を中心に形成されていった。 |
|
 |
|
 |
萩城下町絵図〈1742〜47(寛保2〜延享4)年〉
(萩市郷土博物館蔵)
萩の城下町がほぼ完成した頃の絵図で、2つの川に挟まれた三角州地帯を中心にした町割りが克明に描かれている。 |
|
 |
| 明治初年の萩城。天守閣は5層で高さ15.6m。この城を中心に防備を考えた城下町が形成された。 |
|
|
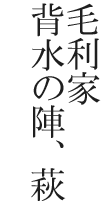 |
|

萩城跡。萩城は1874(明治7)年に破却され、現在は石垣、天守の台座が当時のようすを伝える。 |
|

外堀に架かる平安[へいあん]橋。かつては城下町から三の丸へ入る橋であった。 |
|
 |
|

三の丸(堀内地区)を東西に貫く道。沿道には広大な上級武士の屋敷が構えられていた。 |
|

旧厚狭毛利家萩屋敷長屋。厚狭毛利[あさもうり]と呼ばれた一族の屋敷の一部。萩に現存する武家屋敷の中でも最大の長屋で、全長51m。部屋数だけで19室残る。 |
|

堀内地区に残る口羽家[くちばけ]住宅の母屋。座敷と奥座敷の間にある2畳ほどの「相の間」と呼ばれる空間は、主人の警護のために家来が身を隠していた場所と伝えられる。 |
|