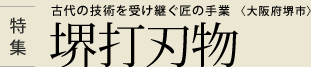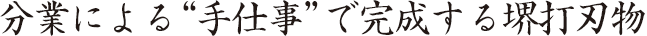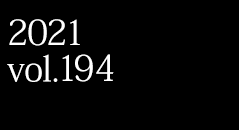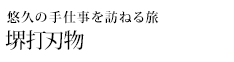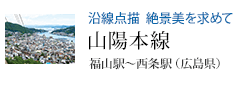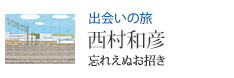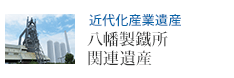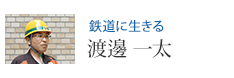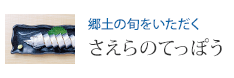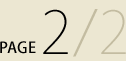
堺の中心地は南北に「大道[だいどう]筋」、東西に「大小路[おおしょうじ]筋」が走り、それを基軸に碁盤目状に区画されている。かつて町名の数は400町ほどに及び、タバコ包丁の製造は7町だけに許された。そのタバコ包丁を機に発展した堺の包丁は「鍛造[たんぞう]」「研ぎ」「柄付け」の職人の手を経て、完成する。この「分業制」が堺打刃物の特徴で、鋭い切れ味を支える真髄だ。
堺市の北部、大道筋を西に折れた柳之町に「田中打刃物製作所」がある。「カーン、カーン」。力強いハンマーの音が住宅街に響き渡る。轟々と炎の燃えさかる炉の前で、赤々と発色した金属に睨みをきかせているのは、鍛冶屋と呼ばれるこの道50年の伝統工芸士 田中義一さんだ。「炎の色を見てね、地金(軟鉄)と刃金(鋼[はがね])が一体化するように温度を調節してる」と田中さん。加熱しては叩き、加熱しては叩く。金属の質が変わり組織が密になり、耐久性が生まれるという。約1000℃の炎を見て対話するように、黙々と一連の動作を繰り返す。

約1000℃に加熱した金属を動力ハンマーで叩き、包丁の形に引き延ばす「鍛造」という工程。


「堺打刃物いうのはよく切れて、長く使える。これに尽きるんです。そのためには、“素材”と“手間”を惜しんだらあかん」。そう話すのは、4代目主人の義一さん。左は5代目義久さん。

包丁を木製の型にはめ、粗い目のグラインダーで全体を荒く研ぐ「荒とぎ」工程。

杉の木製の回転木砥で研磨する「木砥あて」工程。金剛砂を包丁に塗り、きめ細やかな裏面にする。

包丁の刃先を研ぎ、刃をつけていく「本研ぎ」工程。刃をひきながら、包丁の小刃をつけていく。

さまざまなグラインダーにかけ、包丁の厚さや歪みを調整する森本さん。課題は機材のメンテナンスで、修理も自分で行っている。30cmの包丁で、一日20本ほど研磨する。

創業1805(文化2)年の堺刀司 和泉利器製作所。玄関横には江戸時代に造られた店灯が掛かる。社屋には包丁資料館があり、堺打刃物など堺に関する多くの資料が展示されている。

「忙しい時期は一日500〜600丁は仕上げます」。堺刀司 和泉利器製作所のブランド「堺刀司」の包丁を仕上げる柄付け職人の若井さん。
「鍛造」の工程は「火づくり」した後、「火入れ」で地金(軟鉄)と刃金(鋼)を重ねた金属をハンマーで打ち延ばし、包丁の原型を成形する。赤みを帯びた包丁を藁の中に入れ、徐々に熱を冷ます。常温の包丁を再び叩き、鍛えることで“歪み”を除く。そして、約800℃に加熱した「焼き入れ」を行い、一気に水の中で急冷する。刃金の硬度を高めるためだ。170℃で再び加熱し、自然に冷ますと刃金に「粘り」が生まれ、欠けにくい刃に仕上がる。
鍛えられた包丁は、「研ぎ」職人の手に移る。南庄町に作業場を構える「森本刃物製作所」には巨大なグラインダー(砥石)が数台設置され、どれも用途が異なるという。鍛冶屋から預かった包丁を手に作業場に現れたのは、伝統工芸士の森本光一さん。「このままでは全然、切れへん。鍛冶屋の“しごと”を引き出すのが、研ぎの仕事」。回転するグラインダーの前で火花を散らしながら包丁をミリ単位の厚さで調整し、研磨する。「これ、見てみ」、刃には美しい波紋が浮かんでいた。「包丁は見た目も大事。こうした作業は手仕事でないと難しい。そやから職人がいてる」と森本さんは胸を張る。かつては効率化を図るため機材の導入を試みたが、打刃物は機械だけでは精緻な作業は難しく、だからこそ現在も手仕事を続けている。「研ぐと刃に熱が加わって鋼が伸縮する。包丁が曲がるんや」。わずかな“歪み”も微細に調整し、最後の完成品となる「柄付け」に仕事を託す。
大道筋沿いに、豪壮な白壁の商家が見えてくる。「堺打刃物」の看板が軒先に下がるのは、創業から200年を超える「堺刀司[さかいとうじ] 和泉利器[いずみりき]製作所」だ。江戸時代には、「堺極」のタバコ包丁を製造していたという。この老舗で、「柄付け」の仕事を見せてもらった。「カンカンカン」。軽快なリズムで、柄をはめ込んでいくのは職人歴45年の若井進さん。「音を聞いてます。叩く強さを調節してね」。接着する糊などは一切使わない。包丁本体と柄との歪み、バランスを瞬時に判断して完成させる。その動きには無駄がなく、正確無比な匠の技だ。堺刀司 和泉利器製作所は堺打刃物をコーディネートする卸問屋だ。鍛冶は誰で、誰が研いだのか。それを見極め、需要に応じた販売を心がけている。量産品に比べ、堺打刃物は高価だ。それは品質にこだわる堺打刃物製造販売の矜持だ。
軒先の行灯に導かれるように、まだ若いお客さんが訪れた。「まずは使ってみて」と店員が呼びかける。それぞれの職人が口にしていた言葉だ。今も頑なに分業と手仕事にこだわる堺打刃物には、職人たちの自信と強い思いが込められていた。