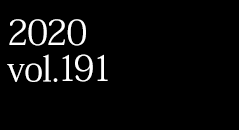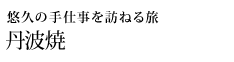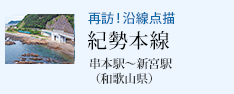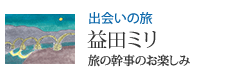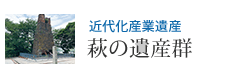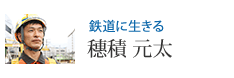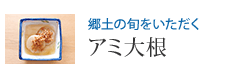紀勢本線の串本駅から新宮駅まで41.6km。
紀伊半島南端の勝浦、那智を経て、
「記紀神話」ゆかりの新宮をめざす。

本州最南端にある潮岬灯台。約30mの断崖に建つ白亜の灯台は、1873(明治6)年に初点灯した。

鋭く切り立った岩礁地帯「海金剛」は、朝鮮半島の「金剛山」にちなんでいる。映画『海難1890』のロケ地になった。
紀勢本線といえば、なんといっても黒潮に洗われた険しい岩礁の熊野灘。太古から続く景勝美は昔も今も変わらない姿を見せる。
今回の旅の起点は串本駅だが、その前に駅から東に位置する和歌山県最大の島、紀伊大島を訪れた。大島の周囲のほとんどは断崖絶壁だ。中でも大島の東端には、荒波によって造り出された「海金剛[うみこんごう]」の巨岩は迫力満点で、ここは映画の舞台にもなった。
近くには「トルコ記念館」があり、大島はトルコと大きな関わりがある。1890(明治23)年、熊野灘を航行中の巡洋艦「エルトゥールル号」が台風により大島の樫野埼沖で座礁した。その時、大島の住民たちが総出で駆けつけ、69名の命が救われた。当時のオスマン帝国は島民の献身に大恩を感じ、教科書にこの出来事を記したという。現在の日本とトルコとの友好関係のきっかけとなり、今年は救出から130年を迎える。

旧オスマン帝国皇帝の特使一行を乗せた軍艦「エルトゥールル号」の乗員を追悼したトルコ軍艦遭難慰霊碑が大島の東端に建つ。

駅舎内に観光案内所が併設されている古座駅。観光案内所ではレンタルカヌーの営業のほか、カヌーの関連商品や雑貨品なども販売されている。

太地町にあるくじらのモニュメント。ザトウくじらの親子がモチーフで、夜にはライトアップされる。

太地町には、ペンキの塗られた格子戸の民家が点在する。ペンキ塗りの文化は、太地を出た北米移民や捕鯨船の乗員が海外から持ち帰ったものという。
さて、“本州最南端の駅”串本駅に戻り出発進行。列車は隣の紀伊姫[きいひめ]駅を過ぎ、古座[こざ]駅へ。駅舎内には観光案内所を兼ねたカヌーのショップが併設されている。周辺を流れる古座川はカヌーのメッカで知られ、全国方々から清流下りに人が集まるそうだ。その川沿いを遡り、古座川峡に入ると奇岩や巨岩が点在している。上流に行けば、国の天然記念物指定の「一枚岩」が見上げるようにそそり立ち、存在感を示している。
列車は古座川を渡り紀伊浦神[きいうらがみ]駅を過ぎると、車窓からは玉ノ浦の水平線に険阻な岩礁が見えてくる。太田川を渡り、下里駅を通過するとまもなく太地[たいじ]駅だ。
駅に降りると、ホームに描かれたくじらたちが迎えてくれる。太地は「くじらの町」で知られ、駅の東方には漁師町が広がっている。町内にはくじらの博物館や、くじらの骨で作った神社の鳥居などくじらとの密接な関わりを示す建物が点在する。県道沿いの岩門をくぐると、格子窓にペンキの塗られた民家が続く。太地から海外へ移った移民や船員たちが、持ち帰った船用のペンキを家の外壁に塗り、潮風から家屋を守ったそうだ。

古座川峡の南紀熊野ジオパーク

日本最大級の規模を誇る「一枚岩」。巨大な岩壁には、一枚岩を守る犬の民話があり、毎年、4月と8月に巨大な守り犬の影が出現する。

奇岩や巨岩が点在する古座川峡。写真は滝の落差が約8mの「滝の拝」。
熊野の山々の中央に位置する大塔山に源を発し、熊野灘に注ぐ古座川の流域は約60km。その流域に広がる古座川峡にはさまざまな奇岩や巨岩、そして滝が点在している。
上流には高さ100m、幅500mの巨大な「一枚岩」がそそり立つ。1400万年以上前の火山で形成された巨大な岩壁だ。支流沿いには、荒々しい岩場に囲まれた「滝の拝[はい]」と呼ばれる滝が轟々と流れている。鮎釣りの聖地でも知られ、夏には滝壺に鮎が密集するという。いずれも「南紀熊野ジオパーク」のジオサイトで、2014(平成26)年には国内の地質遺産「日本ジオパーク」に認定された。

列車は王子ヶ浜海岸を車窓に走る。(三輪崎駅〜新宮駅)
串本駅から約40分で紀伊勝浦[きいかつうら]駅だ。那智勝浦町は「生まぐろ水揚げ日本一」を謳う“まぐろのまち”。駅から南にまっすぐ行くと勝浦漁港で、水揚げされた天然生まぐろをどこよりも早く味わえる「勝浦漁港にぎわい市場」が隣接している。「勝浦は冷凍しない生まぐろへのこだわりがどこよりも強い。はえ縄漁法なので鮮度は格別です。環境にもやさしく、そこを大事にしたい」と、勝浦市場市場長の太田直久さん。町内には「生まぐろマップ」が設置され、周辺にまぐろ関連の店が約40軒。店を巡るのもいい。
列車は進路を北に向け、那智川を渡れば那智[なち]駅だ。駅からすぐの補陀落山寺[ふだらくさんじ]はユネスコの世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に登録された古刹で、補陀落信仰の拠点だ。「補陀落」は観音菩薩が降臨する霊場であり、熊野では南海の彼方に理想郷があると信じられていた。補陀落山寺は命を賭した補陀落渡海の出発点で、ここから観音浄土を求めた僧が海へ送り出されたという。
そこから那智川に沿って西に遡れば、森閑とした杉木立に石段が続く「大門坂[だいもんざか]」に入る。熊野古道だ。熊野詣により平安貴族も歩いた霊験あらたかな古道は、熊野那智大社や西国三十三所一番札所の那智山青岸渡寺[せいがんとじ]、そして那智の大瀑布へと誘ってくれる。
列車はさらに北上し、紀伊佐野駅、三輪崎[みわさき]駅を過ぎると車窓には美しい王子ヶ浜海岸が広がる。終点の新宮駅は、まもなくだ。

「生まぐろ水揚げ日本一」の勝浦漁港。「紀州勝浦産生まぐろ」は全て、はえ縄漁法による天然モノ。市場長の太田さんは、「今年は本まぐろの水揚げが好調です。本まぐろ以外にも、勝浦の“さくらびんちょう”はオススメです。ぜひ、“生”の味を楽しんでください」と話す。


那智勝浦町が発行する「生まぐろマップ」。勝浦漁港の周辺には、まぐろを扱うお店が多数出店している。

補陀落山寺の「補陀落渡海」は一種の捨身行で、その昔ここの僧が那智の浜から観音浄土をめざして海を渡った。


熊野三山へ続く巡礼の道「熊野古道」の大門坂。かつて坂の上に大きな門があったので、この名がついた。

新観光名所 勝浦漁港にぎわい市場


勝浦漁港で水揚げされた生カジキまぐろを燻製した「海の生ハム」。写真右は、醤油や塩なども全て和歌山県産にこだわったまぐろの缶詰。
勝浦漁港に隣接する「勝浦漁港にぎわい市場」は、勝浦観光の拠点の一つとして2018(平成30)年にリニューアルオープンした。施設入口には、同年に勝浦漁港で水揚げされた過去最大の魚体を誇った450kgの本まぐろの等身大モニュメントが迎えてくれる。施設内では水揚げ直後の天然生まぐろがすぐに味わえるほか、海産物の加工品(海の生ハム、まぐろの缶詰)や紀州の地酒、みやげ物など8店舗で直売されている。
施設奥にはブースが設けられ、そこでは「まぐろ解体ショー」が連日開催。即売会も行われている。

神倉神社の境内からは、新宮の市街地と熊野灘が見渡せる。境内は、“パワースポット”としても人気だ。

神倉神社の“ゴトビキ岩”に降り立った熊野の神々を祀った熊野速玉大社。山麓に設けた新しい宮として“新宮社”とも呼ばれる。「新宮」の由来とされている。
新宮市は「熊野三山」の一社、熊野速玉大社[くまのはやたまたいしゃ]の門前町として栄えた。駅前商店街を抜け、さらに西へ行くと熊野川を背にした朱色の熊野速玉大社が鎮座する。大社は「新宮[にいみや]」とも呼ばれ、その元宮となるのが神倉[かみくら]神社だ。大社からほど近くにあり、鳥居の先には見上げるほどの石段が延びる。敷かれた石段はゴツゴツとして歩きにくく、肩で息しながら一歩一歩登る。高さ約100mの断崖に拝殿に寄り添った巨大な岩が姿を現した。御神体の「ゴトビキ岩」だ。この巨岩に熊野の神々が降臨し、「神の磐座」として崇められてきた。また、毎年2月には白装束の男たちが松明を手にこの石段を駆け下りる「お燈祭[とうまつり]」が催される。約1800年続く勇壮な火祭りは、見応え十分だ。
紀伊半島の縁を走る約40kmの再訪は、自然の景勝美や世界遺産を巡る見どころ、食べどころいっぱいの旅であった。

熊野の神々が宿った“ゴトビキ岩”

熊野信仰の原点である神倉神社の“ゴトビキ岩”。この巨岩に、熊野の神々が降り立ったと伝承されている。

神倉神社の参道。鎌倉積みの石段の最高傾斜角は45度で、約500段続く。
神倉神社は、神倉山の中腹に鎮座する熊野速玉大社の摂社だ。御神体の「ゴトビキ岩」には熊野の神々が降臨され、『日本書紀』では神武天皇が登った天磐盾(アマノイワタテ)であると伝えられている。
「ゴトビキ」は熊野の方言でヒキガエルをさし、巨岩の形がそれに似ていることにちなんでいる。苔むした自然石が武骨に並んだ石段は急峻で、その数は538段。この石段は、鎌倉時代に源頼朝が寄進したものと伝えられている。
高台の境内からは新宮の町並みが一望できる。