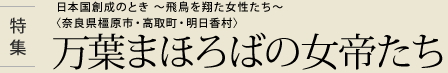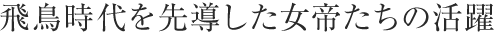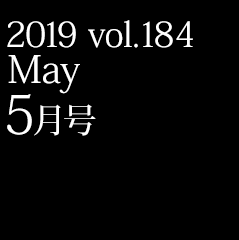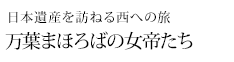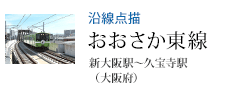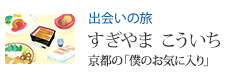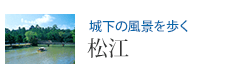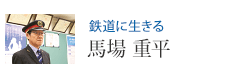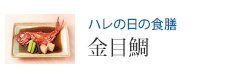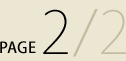
甘樫丘はただ見晴らしのいい丘ではない。蘇我氏の大邸宅があり、かつ軍事的要害だったという。周囲を睥睨[へいげい]する軍事拠点としてこれ以上の好適地はなく、蘇我氏はここを拠点に推古天皇亡き後、再び息を吹き返し、権勢をほしいままに国を支配した。馬子はすでに亡く、その子蝦夷[えみし]と孫の入鹿が台頭した。
舒明[じょめい]天皇(34代)の崩御の後、皇后であった皇極女帝(35代)が飛鳥板蓋宮[いたぶきのみや]で即位した。中大兄皇子、大海人皇子の母でもある。しかし、その裏では蘇我氏が権謀をめぐらし、専制を強めていったため、国の改革は滞った。
中大兄皇子、中臣鎌足はこれに反発し、645年についに板蓋宮にて蘇我入鹿を殺害する。「乙巳[いっし]の変」と呼ばれる事件だ。入鹿のはねられた首は現在の飛鳥寺の首塚まで飛んだと伝えられ、甘樫丘の屋敷は焼け滅ぼされて、ここに蘇我本宗家は滅亡する。
皇極天皇は事変の責任をとり、弟の孝徳天皇(36代)に譲位するが、その死後、斉明女帝(37代)として再び即位する。これを重祚[ちょうそ]という。一方、時代の主役となった中大兄皇子らは、豪族たちのこれまでの既得権を剥奪するような新しい国の仕組みを細かく規定し、一大改革を果敢に断行した。
「人民の管理」、「土地の管理」、「税金の管理」の3権を国家に集中させたのである。この乙巳の変後の一連の政治改革が「大化改新」であり、この改新がその後の日本の国家体制の根幹となった。斉明天皇は渡来の技術を導入しつつ、飛鳥板蓋宮から飛鳥川原宮に遷し、大規模な運河や建造物をつくるなど国土の整備に邁進した。

飛鳥寺の傍、田畑の中にぽつんと佇む蘇我入鹿の首塚。板蓋宮ではねられた首はここまで飛んだとされている。背景は甘樫丘。

皇極・斉明天皇は雨乞いなど祭祀を執り行う司祭者だった。この酒船石遺跡(亀形石槽)は祭祀を行った遺跡といわれている。さまざまな建造物を造り、渡来の土木技術で国土を整備した。

甘樫丘の東麓にある斉明天皇時代の水落(みずおち)遺跡。『日本書紀』には、中大兄皇子が初めて造った漏刻(ろうこく:水時計)と記される。

橿原市藤原京資料室に展示された藤原京の巨大な再現模型。中央の大極殿を中心に東西南北に通りが設けられいる。整然としてしかも大規模な条坊制の都だ。往時の人々の賑わいが伝わってくる。

藤原宮跡の花畑

藤原宮跡整備協力委員会の福田茂さん。ボランティアで藤原宮跡に花畑をつくるなどして環境保全に尽くしている。「ここはどこを掘っても遺跡が出ます。本当に日本の遺産です。なんとしても守っていきたいです」と言う。
ほどなく古代史上最大の内乱が勃発する。「壬申の乱」は天智天皇(38代:中大兄皇子)の後継を巡る、子の大友皇子と弟の大海人皇子との政争で、大海人皇子側が戦いに圧勝し、弘文天皇(39代)の後、天武天皇(40代)となって飛鳥浄御原[きよみはら]宮を設けた。この乱で、改革の反対勢力だった豪族たちは一掃され、天武天皇の前にもはや敵はいなくなる。
天皇の称号を最初に用いたのは天武天皇だというのが今日では有力な説である。その天武天皇と関係が深く、飛鳥文化を語る上で見落とせない女性が、斉明女帝時代から宮中に仕える巫女的な歌人、額田王[ぬかたのおおきみ]だ。天智、天武に通じた複雑な人間関係は万葉歌にも詠まれている。
天武天皇を皇后として補佐したのは天智天皇の第二皇女で、後に持統女帝(41代)となる 野讃良皇女[うののさららのひめみこ]である。新しい宮都の造営をとりわけ夢見ていた天武天皇は夢半ばで崩御し、この夫の無念を継いで持統天皇が取り組んだのが藤原京の造営だ。中国の都に倣[なら]った条坊制の広大な都であった。現在、その発掘調査は全体の3%といい、京域の全貌は正確には判明していない。
野讃良皇女[うののさららのひめみこ]である。新しい宮都の造営をとりわけ夢見ていた天武天皇は夢半ばで崩御し、この夫の無念を継いで持統天皇が取り組んだのが藤原京の造営だ。中国の都に倣[なら]った条坊制の広大な都であった。現在、その発掘調査は全体の3%といい、京域の全貌は正確には判明していない。

高松塚古墳壁画(国宝)。極彩色に描かれた女官たち。描かれたのは藤原京の時代。額田王も宮中に仕えた女官で、おそらくは壁画のような“飛鳥美人”だったのだろう。
持統天皇は、ほかに隋や唐に倣って進められてきた律令国家への歩みを自らの手で一気に加速させた。その政治手腕と実行力は驚くべきものだが、藤原京はわずか16年で平城京へと遷都され、飛鳥時代118年の幕は閉じる。今はただ広大な広場にしか見えない藤原京のすぐ間近に天香具山が横たわっている。
思わず口をついたのは、持統天皇の有名な万葉歌だ。「春過ぎて 夏来[きた]るらし 白たへの 衣干したり 天[あま]の香具山」。その天香具山も、畝傍山、耳成山も飛鳥時代と変わらず、その姿は今もたおやかで優雅な万葉の風景だ。明日香の土の下にはまだ語られていない物語が眠っている。それを想像すると一木一草の風景まで歴史が匂いたってくる。