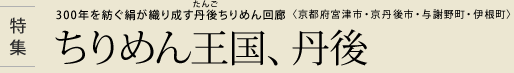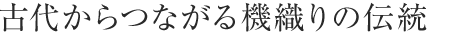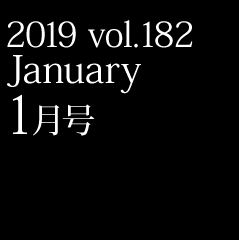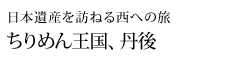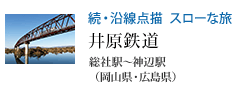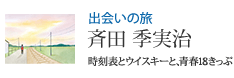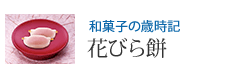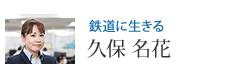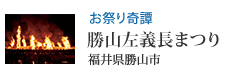宮津市の旧三上家住宅。糸問屋のほか酒造業、廻船業などを営んだ豪商宅。北前船の寄港地で宮津は丹後ちりめんの流通拠点として大いに栄えた。花街であった新浜地区には京都祇園に劣らない数の芸者衆がいたそうだ。


京丹後市峰山町の禅定寺には、丹後ちりめんの始祖の一人、絹屋佐平治が奉納した最初に織った「縮み布(丹後ちりめんの原形)」が寺宝として保存されている。
その伝説を裏づける史実が出ている。京丹後市峰山町にある扇谷遺跡から糸を紡ぐ紡錘車[ぼうすいしゃ]、今市墳墓群からは絹糸が出土。さらに国内有数の古墳である大田南5号古墳からは「青龍三年(235年)」の鏡が出土し、絹織物も検出されている。また正倉院御物に、739(天平11)年に丹後国から献上された6丈(約18m)の「 [あしぎぬ]」(粗い糸で織られた絹布)が残っている。
[あしぎぬ]」(粗い糸で織られた絹布)が残っている。
 とは、古代日本に存在した絹織物の一種。官人僧侶の制服などに用いられた。『日本書紀』では和訓は「ふとぎぬ」と記している。このことから古代から丹後地方では絹織物が生産されていたことが分かる。南北朝時代(1336〜1392年)に書かれた『庭訓往来[ていきんおうらい]』には丹後国の特産として「丹後精好[せいごう]」という絹織物が記されている。
とは、古代日本に存在した絹織物の一種。官人僧侶の制服などに用いられた。『日本書紀』では和訓は「ふとぎぬ」と記している。このことから古代から丹後地方では絹織物が生産されていたことが分かる。南北朝時代(1336〜1392年)に書かれた『庭訓往来[ていきんおうらい]』には丹後国の特産として「丹後精好[せいごう]」という絹織物が記されている。
波静かな丹後の海、宮津湾と阿蘇海を割くように、一筋の松林がすっと伸びている。歌人の与謝野鉄幹はその光景を「たのしみは大内峠にきはまりぬ まろき入江とひとすぢの松」と詠んでいる。大内峠から見る天橋立は、写真でおなじみの飛龍観や傘松公園から眺める風景とは異なり、横真一文字だ。栗田半島を背景に清々しい風景が広がっている。
天橋立にはこんな伝承がある。『丹後國風土記[たんごのくにふどき]』逸文[いつぶん]によると、天橋立は伊射奈藝命[いざなぎのみこと]が天と地を往来するための梯子[はしご]で、伊射奈藝命が寝ている間に倒れて現在のような姿になったという。他にも丹後地方には大陸との交流に関わる神話や古代からの伝承が多い。その一つが機織りを伝えたという羽衣天女[はごろもてんにょ]伝説である。
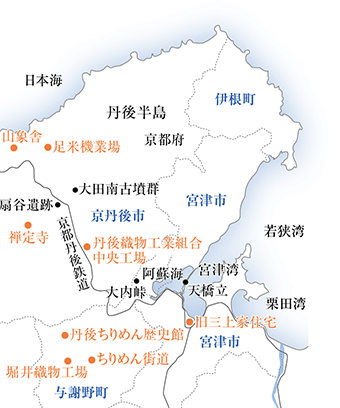
絹織物は丹後地方に脈々と継がれた伝統だったが、今日の「ちりめん」の歴史は戦国時代の末、天正年間(1573〜1592年)だ。中国から技法が堺に伝わったことに始まる。京都西陣は堺から技術を導入し、やがて西陣から各地に広まった。丹後では1720(享保5)年に、西陣に学んだ峰山の絹屋佐平治がちりめんの技術をもたらした。
同じ頃、加悦[かや]の木綿屋[もめんや]六右衛門が、手米屋[てごめや]小右衛門、山本屋佐兵衛の2人を西陣に修行に行かせた。この4人が「丹後ちりめん」の始祖とされ、たちまち農家の副業として丹後地方一円に広まっていった。1730(享保15)年には西陣は大火で多くの織機が消失し、丹後への依存がいよいよ高まり、西陣を脅かすまでの生産地になっていく。
ちりめんは正しくは「縮緬」と書く。縮とはちぢみ、緬は細糸や軽いなどを意味する。経糸[たていと]には撚[よ]りのない糸を、緯糸[よこいと]に強い撚りをかけた糸を交互に織っていく。織り上げた後、精練[せいれん]と呼ばれる行程で、湯で煮て生糸のタンパク質を取り除く。すると生地が縮み、表面に「しぼ」という細かな凹凸ができ、柔らかな肌合いが生まれる。
この「しぼ」が生み出す繊細な感触と、陰翳に富んだ美しさがちりめんの特徴だ。江戸時代には峰山藩が手厚く保護奨励し、丹後地方の特産品として全国にその名を知られるようになる。物流の拠点だった宮津の民謡、宮津節はこう唄っている。「二度と行くまい丹後の宮津、縞の財布が空になる…」。商談の宴会は連日だったようだ。


昭和初期のノコギリの歯のような三角屋根のある織物工場特有の建物が残る。

大内峠からの景観とは対照的な雪舟観付近から見た天橋立の夕景。雪舟筆、国宝『天橋立図』は想像的にこの付近の上空から鳥瞰的に描かれている。
京丹後市網野町の(株)アシヨネは、旧名を足米機業場[あしよねきぎょうじょう]といい1830(天保元)年創業の現存する最古の機業場だ。家系は平安末期から鎌倉初期に遡る士族。「景気のいい話は祖父の代まで、今は昔語りです。しかし、この丹後ちりめんの伝統と品質を途切れさせることはできません」。江戸時代にこの地に移って機業場を営み8代目という足達新介さんは、そう話してくれた。

京丹後市網野町の足米機業場の糸繰り作業。ガチャガチャという機織り機から繊細な紋ちりめんが織り出される。丹後ちりめんには1,000種以上もの柄があるという。