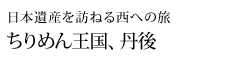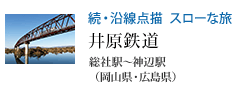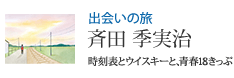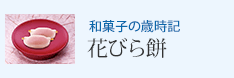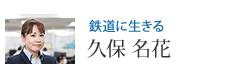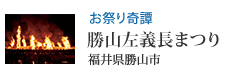白い餅皮の下から、淡い紅色がほのかに透ける。
その名も風雅な「花びら餅」は、迎春菓にふさわしく華やかさとゆかしさを纏[まと]っている。平安時代の年始の儀式から変化を重ね、茶道の隆盛とともに正月行事を飾る銘菓となって今に至る。茶文化が暮らしに息づく島根・松江に、その由緒をたずねた。

季節感あふれる生菓子が店頭に並ぶ松江市内の彩雲堂本店。

年中行事を彩る和菓子の中でも、新年の祝いに用いられる「花びら餅」は、とりわけ雅な由緒を誇る。その起源を辿ると平安時代の御所の正月行事にまで遡り、神前にお供えする鏡餅に原形があるという。宮中では、白木三宝に紅白二段の鏡餅をのせ、その上に葩[はなびら]という薄く白い円形の餅と、紅色の菱形の餅をそれぞれ12枚重ね、これを「菱葩[ひしはなびら]」と呼んだ。さらに砂金袋の形をした餅をのせ、一番上には海老、周囲には柚子や橙[だいだい]などの果実を配して昆布を垂らしたものが正式な鏡餅とされたそうだ。この鏡餅とともに、白い葩と紅の菱餅を重ねたものを三宝に12枚並べ、各々その上に「歯固めの儀」で用いる搗[かち](勝)栗や榧[かや]の実、竹皮で包んだ飴、押し味噌、年魚(鮎)などをのせて飾るのがしきたりであった。「歯固めの儀」とは、固いものを食べて長寿を願う新年の宮中行事をいう。この鮎が江戸時代の初めには厄除けの意味合いのあるごぼうに変わり、味噌をぬって菱葩の上にのせたものが宮中正月宴の初献に饗され、また天皇からの正月恩賜の配り物に使われた。
「宮中雑煮」ともいわれたこの菱葩は、やがて一人の茶人によって、茶菓子として広められていく。裏千家十一代玄々斎宗匠は、宮中献茶の際に拝領した菱葩を、代々御所の餅座を預かる川端道喜に初釜用の菓子に創らせた。以降、宗家初釜の主菓子として定着するとともに、現在、全国各地の菓子司に受け継がれるさまざまな「花びら餅」の起こりとなった。

本場京都の白味噌の風味を消さず、まろやかな味わいの味噌餡に仕上げるには、練り上げた白餡に味噌を加える頃合いを見極めるのが大切という。

外皮の餅は、搗餅(つきもち)であったが、求肥が多く用いられるようになった。ごぼうは土中に深く根を張ることから、家の基になるといわれる縁起物の食材。

不昧公がよく茶事を催した茶室「明々(めいめい)庵」。茅葺きの入り母屋造りで、茶室の定石にとらわれない不昧公好みの設(しつら)いとなっている。
水の都と謳われる松江は、松江藩城下の風情を色濃く残し、藩政時代から受け継ぐ文化が暮らしに融け込んでいる。松江を代表する文化といえば、茶の湯と和菓子。流儀・作法にこだわらず、日常のさまざまな場面でごく自然に薄茶に親しみ、四季折々の菓子を楽しむ。その源流には、地元の人々から今も「不昧公[ふまいこう]」と慕われる松江藩七代藩主松平治郷[はるさと]の存在がある。自ら不昧流茶道の祖となり、身近に茶を嗜む習慣を広めた人物だ。松江では、茶の湯に欠かせない和菓子をつくる職人の技が磨かれ、京都、金沢に並ぶ菓子どころとしての文化も同時に育まれた。
1874(明治7)年創業の「彩雲堂[さいうんどう]」は、不昧公時代の銘菓「若草」を地域の古老の言い伝えをもとに復古・再現した老舗として知られる。季節の風物詩を盛り込み、職人の技巧と感性から生み出される四季折々の生菓子は、目、口ともに肥えた松江の人々を魅了する。「花びら餅」は、昭和の頃から受け継がれている伝統の迎春菓。店の歳時記の中で、新しい年の初めに登場する縁起物だ。彩雲堂では、「雪平[せっぺい]」という六分立ての卵白を加えた求肥[ぎゅうひ]※の生地に、食紅で染めたなめらかな白味噌の餡を絞り、香気あるごぼうの蜜漬けを挟んで二つ折りに仕上げる。求肥の柔らかさの加減、白い生地から美しく透けた餡の色合いなど、職人には細部にわたって熟練の技が必要とされるそうだ。あしらいも個性的な正月だけの和菓子は、新春のお茶会やおもてなしの席に華やぎを添える。
※白玉粉や餅粉に水飴や砂糖を加えて練り上げ、薄い餅のようにしたもの。