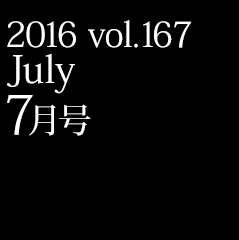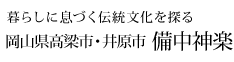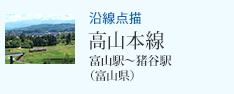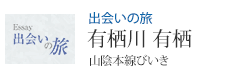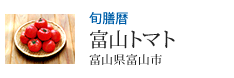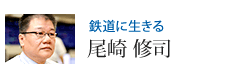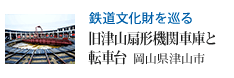北陸新幹線の金沢開業から1年。
これに伴い富山駅も多くの乗降客で賑わい、
乗り継いでいく列車の旅の楽しみ方も増えた。
今回は富山駅から高山本線に乗って
飛騨の山々へと分け入った。
沿線の見どころは劔、立山の大パノラマだ。

富山駅構内にあるガラスを床に散りばめたフロア・シャンデリア。床のタイルは岩瀬の砂浜をイメージしている。

呉羽山公園展望台からの眺望。晴れた日には富山市街地からでも立山連峰の大パノラマが望める。

富山駅に乗り入れる路面電車。新幹線改札口を出た正面に駅があり、乗り継ぎの便がとても良い。
北陸新幹線の金沢開業から1年が経過した。利用客数は1,000万人を突破し、富山駅の乗降客数も増え続けている。真新しい新幹線の高架駅設置に伴い、在来線も高架化が進み、高架下には富山名物となったモダンな路面電車も乗り入れている。駅前の風景も街の賑わいも見違えるほどだ。
新幹線開業で富山は旅の選択肢が増え、そこで注目されているのが高山本線。岐阜駅まで225.8kmの長大な路線だが、奥飛騨観光の中心地となる高山駅までは特急「ワイドビューひだ」で約90分。3月のダイヤ改正で接続が改善され、実に利便性が向上した。今回の旅は岐阜県との県境までの36.6kmの区間で、乗車時間は1時間ほどだが、素晴らしい風景との出会いがある。富山駅2番線のホームを後に、列車は南下しつつ飛騨山地の山峡の目的地、猪谷[いのたに]駅へと走り出した。

神通川に架かる登録鉄道文化財「新神通川橋りょう」。1908年(明治41)年に架橋された6連のトラス橋。
ほどなく新神通川橋りょうを渡る。この橋は1908(明治41)年に建設された当時の姿をとどめ、登録鉄道文化財に指定されている。車窓の右手に見える小高い山は呉羽山[くれはやま]で、富山ではこの山を境に西側の呉西[ごせい]と、東側の呉東[ごとう]では文化が変わると言われる。一例は食文化、西は関西風で東は関東風だそうだ。列車は富山湾へとゆるやかに傾斜する富山平野の広々した風景の中を走る。

1994(平成6)年にオープンした「富山ガラス工房」。富山のガラスは富山の薬と深い関わりがあり、明治から大正期に、富山は薬瓶製造で全国のトップシェアを誇った。一般向けのガラス制作体験コースもある。(写真提供:富山ガラス工房)
多くの人が下車する婦中鵜坂[ふちゅううさか]駅の周辺には企業や工場が集まり、近年は富山大学の附属病院もあって富山市のベッドタウンとして開発が進んでいる。ここで下車し「富山ガラス工房」に立ち寄るのもいい。富山のガラス工芸は全国的に有名で、工房では作家の育成やガラス製品の普及に努めている。


「富山市天文台」の大型天体望遠鏡は国内最大級で、毎週水曜から土曜の夜には観測会が行われる。写真左は、富山市天文台から撮影した夏の天の川。
次の速星[はやほし]駅では「富山市天文台」を訪ねた。国内の公開天文台では3番目に古く、国内最大級の天体望遠鏡を備える。月のクレーターや土星などの天体観測のほか、立山連峰の様子も日々観察しホームページで紹介しているそうだ。

車窓から広々とした井田川沿いの田園を見渡す。(速星駅〜千里駅)
速星駅を過ぎた辺りから、車窓の向こうに素晴らしい風景が目に飛び込んできた。広がる緑の田畑の向こうに残雪の劔、立山連峰の一大パノラマが展開した。なんと贅沢な車窓の風景だろうか。その雄大な眺めはまさに感動だ。

300年余、踊り継がれる「おわら風の盆」。(写真提供:富山県観光連盟)
千里[ちさと]駅を過ぎると、旅の中間点となる越中八尾駅だ。八尾の名は、飛騨の山々から越中へと幾重にも尾根が重なる様子に因む。古く、八尾村の家々は段丘の下にあったが、1631(寛永8)年の井田川の氾濫で甚大な被害を被り、それ以降は段丘の上に人家が建てられた。

八尾町を代表する景観として知られる、河岸段丘上の石垣の町並み。
駅からは上り勾配の坂道が続き、やがて急斜面に築かれた石積みが見えてくる。まるで城郭のようだ。石積みは切り立ち、高台に家々が建ち並ぶ。養蚕と和紙で繁栄した八尾町だが、全国的に名が知られるようになったのは毎年9月に開催される「おわら風の盆」。3日間で約20万人の観光客が訪れる。
八尾の11の町でそれぞれに伝わる衣装に身を包み、編み笠を深く被り、三味線、胡弓、太鼓の音に合わせ、ぼんぼりが照らす町内を徹夜で唄い、舞う。見物客で前に進めないほどの賑わいぶりで、期間中は臨時列車まで運行される。作家・高橋治の著書『風の盆恋歌』では「年に3日だけ、別の町になってしまったような興奮が来る」と描かれている。この日は親類縁者が一堂に集い、八尾を離れて都会で暮らす人たちも帰省するのだそうだ。

神通川の流れと幾重にも重なる山並みが形成した神通峡。初夏の新緑、秋の紅葉の景勝地で知られる。
越中八尾駅を後に列車は東に進路を変え、神通川の支流の井田川を渡る。東八尾駅を過ぎてトンネルに入り、抜けると再び神通川と出会う。笹津[ささづ]駅を過ぎると深山幽谷の気配がさらに濃くなる。蛇行を繰り返す神通川に、寄り添うように走る列車から眺める神通峡の渓谷美は、沿線の見どころでもある。
越中八尾駅から約25分で今回の旅の終着、猪谷駅だ。富山・岐阜の県境でJR西日本とJR東海の境界駅。猪谷は飛騨街道の関所が置かれた交通の要衝で神岡鉱山への中継地として栄えた山峡の町だ。廃坑の地中1,000mにニュートリノ研究の施設「カミオカンデ」「スーパーカミオカンデ」がある。富山駅から高山本線の列車に乗れば、旅の楽しみはさらに増えること請け合いだ。

猪谷駅前にある猪谷関所館では、関所の役割や猪谷の町の変遷について知ることができる。

富山県と岐阜県の県境に位置する猪谷駅。

井波の彫刻、高岡の彫金、城端の漆工をあしらった豪華絢爛な曳山。富山市八尾曳山展示館には実際に使用する曳山3基が常設展示されている。

「日本の道100選」に選定されている諏訪町本通り。石畳に格子戸や白壁の町家が並び、今も江戸時代の佇まいを残している。
越中八尾は浄土真宗・聞名寺[もんみょうじ]の門前町で、河岸段丘の石積みが特徴的な坂の町だ。「日本の道100選」に選ばれた坂道の両側に古い家並みが続く端正な町の佇まいが、独特の情趣を漂わせている。

毎年5月3日に行われる曳山祭。富山藩の御納所として栄華を極めた町人文化の象徴で、曳山神事として伝承されている。(写真提供:越中八尾観光協会)
飛騨往還の中継地であった八尾は、交通、交易の要所として繁栄した。特に「蚕都」と呼ばれるほど養蚕と製糸で潤ったほか、越中和紙の産地としても全国に知られた。その八尾の栄華と町衆の心意気を現在に伝えるのが「曳山祭」だ。江戸時代中期、藩主から譲り受けた雛人形と役者を曳山に乗せて町中を曳き廻したことに始まるそうだ。

富山市八尾曳山展示館の楠さんは、「特徴といえば豪華すぎる曳山に尽きます。八尾商人の豊かな財力があっての曳山ですから」と話す。
5月3日の祭りの日には、井波の匠の技が随所に施された豪華絢爛な6基の曳山が町中を曳き廻される。曳山を間近に見ると、精緻で複雑な彫刻、豪華な彫金に目を奪われる。曳山を常設展示する富山市八尾曳山展示館の楠純太さんは、「曳山には御神像がおられます。八尾の町に高い建物がないのは御神像を見下ろさないためです」と話す。確かに時代劇のセットのように、町のどの通りにも高い建物がない。曳山祭とともに町の美しい佇まいを守り続けることは、八尾の人々の流儀なのだろう。



![越中八尾[えっちゅうやつお]、20万人が訪れる「おわら風の盆」](img/area_sttl02.gif)