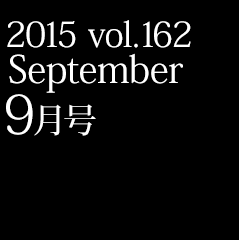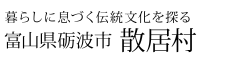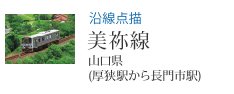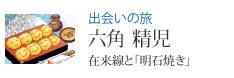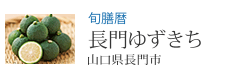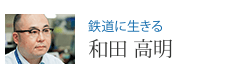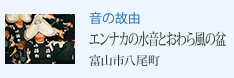![]()


越中八尾[やつお]は、古くから飛騨地方から日本海へと抜ける交通の要衝で、養蚕と商業の町として繁栄し、町筋を拡大していった。井田川の河岸段丘の町は坂が多く、道筋ごとの家々の軒下には「エンナカ」と呼ばれる水路が流れる。冬の屋根雪を流す土地の知恵だ。
この地で江戸時代から続く祭りが「おわら風の盆」だ。元禄期に始まったとされ、盂蘭盆会[うらぼんえ](旧暦7月15日)に行われていたものが、やがて9月1、2、3日に行う「二百十日」の風の厄日に「風の盆」と称する祭りになったといわれる。「おわら」の語源は諸説あるが、「おわらひ(大笑い)」がいつしか「おわら」と唄われるようになったともいう。
哀調を帯びた三味線と胡弓、太鼓の音色に合わせて艶のある唄が入り、編笠に揃いの法被と浴衣姿の男女が優美で格調高い踊りを披露しながら、坂の町を流していく。
祭りの時期には哀調漂う「おわら風の盆」の旋律が「エンナカ」の清らかな水音と相まって、八尾の町は旅情緒が高まっていく。
※一部の端末ではご利用になれない場合があります。ご了承ください。