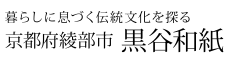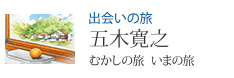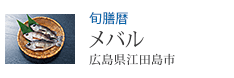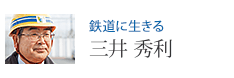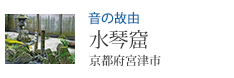京都府綾部市黒谷町、土地のお年寄りに言わせると「丹波のどんつき」。山峡に身を隠すような黒谷集落の佇まいは、鉄道や国道がすぐそばを通っているとはいえ、隠れ里の雰囲気を漂わせている。
冬は寒さが厳しく、雪も積もり、谷は深い霧で覆い包まれる。そんな集落には800年ほど前から語り継がれる平家の落人伝説がある。「身を隠した落人が、山に自生する強い繊維の楮の木と谷川の水で、生計のために製紙の技を子孫に残した」と黒谷和紙協同組合理事長の林伸次さんは話す。紙が中国から日本に伝来したのは聖徳太子の時代だ。
国道から伊佐津川に架かる黒谷橋を渡ると、黒谷川に沿って狭く曲がりくねった道が一つ、ゆるやかな勾配で上流へと続く。瀬の浅い清冽な水流に沿って人家が並び、川の対岸の各家には小さな橋が架かっている。民家の裏は急斜面の山が迫り、谷間に農地はほとんどない。

集落の奥に熊野神社が集落を見守るように鎮座する。社殿も境内も立派で、村の人が大切に手入れをしていて清楚な雰囲気が漂う。
しかし、紙作りには格好の場所だ。「楮の木が自生し、冬が寒く、清らかで冷たい水が紙作りの条件ですから。水が冷たく、寒ければ寒いほど上質の美しい紙ができます。自然に慈しまれて紙は育まれるのです」と林さん。黒谷の和紙は、江戸時代には山家[やまが]藩に奨励されて大いに発展した。
強くて丈夫なのが特徴で、京の都や大坂という大消費地を控え、呉服を保存・保管する「たとう紙」や「値札」、襖紙や障子紙、傘紙や提灯紙などが多く作られ重用された。村中が家族総出で紙を作り、いつしか「紙漉きの村」と呼ばれるほど、誰もが紙作りに携わっていた。

漉かれた紙は1枚1枚板張りされ、日当りの良い山の南の斜面で天日干し。作業するのは大阪から移住した山本朋伸さん。決して機械で乾燥させない。「日に当てることで丈夫な美しい紙になります。ただし天候に左右されます」と話す。
1872(明治5)年の職種調査の記録によると、黒谷村76戸のうち紙職は67戸。それが1950(昭和25)年には50戸、1985(昭和60)年には32戸と年々減少していく。近代から現代へと生活様式が変わるにつれ需要は激減。日本中の産地も次々に姿を消し、丹後・丹波の谷々に約800カ所もあった紙の里も瞬く間に洋紙に圧倒され、伝統は途絶えていった。
が、黒谷の伝統は残った。「早くに組合を組織して職人は紙作りに専念できたので技術が守られたのと、実用紙のほか工芸分野にも広げたことです」。そして「綾部が発祥地である繊維メーカー・グンゼが養蚕用紙や包装紙として黒谷和紙を後押しした」と林さんは言う。ところが今日、「親に紙作りを教えてもらって一人前」の黒谷でも代々生業としてきた家は、ただ1戸残るだけとなった。
堀江チヨ子さん、山城睦子さん親子がその1戸。組合の専務理事でもある睦子さんは、「おばあちゃんが紙を漉くチャポン、チャポンという音が今も耳の奥に残っています。子どもの頃はどの家からも紙漉きの音が聴こえました」。結婚後、京都市内で暮らし、子どもが手離れしたのを機に黒谷に戻って伝統の紙作りを母親から受け継いでいるという。
紙作りは、その重労働と得る収入とは見合わない。どの家も子に紙作りを継がせず、若い人はみな黒谷を離れて都会に仕事を求め、集落に残るのはお年寄りばかり。お年寄りは紙漉きのベテランだが、集落には技を伝えるべき若い世代がいなくなり、里の伝統も「これまでか」となった。

水に晒した楮の皮を1本ずつ剥いでいく「かごへぎ」の作業をする堀江、山城さん母娘。親子で紙作りをするのは集落でも一戸だけになってしまった。
そこで組合が取り組んだのが、後継者となる紙職人の育成だ。全国から若者を募り、お年寄りから技術を学んだ。
「今、黒谷和紙の伝統を繋いでいるのは黒谷和紙に惹かれて各地から集まった人たちです」。そう話す林さん自身、18年前に後継者育成で紙職人になった一人だ。

黒谷和紙協同組合理事長の林伸次さん。綾部生まれで画家志望だった林さんは、「黒谷和紙の伝統と古法を守るため」に後継者育成事業に応募して紙職人になった。「辞めずにいるのは好きだからでしょうね。若い力で黒谷和紙を盛り上げたい」と語る。

山本さんの借り受けた民家にある紙漉き場。黒谷の紙漉き場の原形をほぼ留めている。狭いが作業の工程が効率よく流れるように配置され、山本さんは昔ながらの職住一体の生活をする。