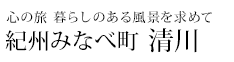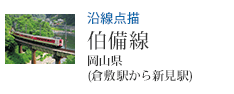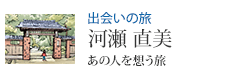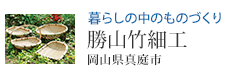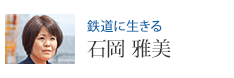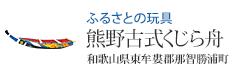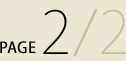
スーさんの案内で地区を回った。地区は思いのほか広く、林道を走るには案内人がいないと迷子になる。清川天宝神社や絶滅危惧種指定の植物キイジョウロウホトトギスが自生する妙見神社。スーさんの軽トラックは梅畑の中の急な坂道を軽快に上り、農家の庭先を抜け、棚田を見ながら走る。
曲がりくねった山路を辿って、やっと訪ねたのが紀州備長炭を焼く原幸夫さん、正昭さん親子の炭焼き小屋。みなべ町全体で炭焼きは約30人、そのうち清川には10人。幸夫さんは、中学を出るとすぐに父親と炭焼きを始め、炭焼き職人歴60年の最長老だ。正昭さんは一度は村を離れて都会で暮らし、清川の素晴らしさにあらためて気付いて炭焼きを始めた。

今では貴重種となったキイジョウロウホトトギスが石垣一面に群生する妙見神社。秋には可憐な黄色い花を咲かせる。
親子が焼く炭は多くの顧客が待ち望むほど質が良い。炭は製炭の違いで2種類。黒炭[くろずみ]は、ナラ類の原木を400〜700度の熱で焼いた柔らかな炭で、火付きが良いのが特長で、一般に木炭と呼ばれる。それに対して、カシ類で焼く紀州備長炭は白炭[しろずみ]と呼ばれ、一週間ほど蒸し焼きにした後、窯出し直前に一気に空気を取り入れて1,200度もの高温で完全に炭化させ、かき出して土と灰で蒸らす。その際、表面に白い粉が付着するので白炭という。特長は金属のような硬度と光沢だ。叩くとキーンと金属音を発し、火力が安定していて、火持ちが良く、特にウナギの蒲焼きや焼き鳥など料理用燃料には最高といわれる。最近では料理のほか浄水や消臭などの用途でも人気がある。ウバメガシを焼いたものだけが紀州備長炭と呼ばれ、その製炭技術は和歌山県の無形民俗文化財だ。

紀州備長炭の名は江戸時代、紀州田辺藩出入りの炭問屋「備中屋長左衛門」に由来する。その製法技術を確立したのは、南部川村(現清川地区)の名もない炭焼き職人だという。

炭焼き中の原さん親子。山仕事で伐採した約10tのウバメガシを10日ほどで焼き上げる。窯出しは柄の長さが5m以上もある朳[えぶり]でかき出す。1回の窯出しで製炭はダンボールケースで20数箱になる。
原さん親子はとりわけ数少ない専業の炭焼き生産者だ。今も自ら山に入り、ウバメガシを伐採し、炭焼き小屋まで運び、炭を焼くという伝統的な製炭を続けている。「山に入ると鬼になる」という幸夫さんは、「炭焼きは炭焼くだけやない。炭焼きよりまず山仕事」。山に入り、山や樹林の相を読み、不要木を間伐して山や木が再生できるように手当てし、炭を焼く。それが山仕事だ。
それは「昔の炭焼きには当たり前の山仕事の基本」だ。ところが戦後、山仕事の基本を教わらないまま炭を焼く人が増えたという。そして息子の正昭さんはこう続けた。「昔は木の成長の循環を考え、山から山へ移動して炭を焼いた。ウバメガシは成長に40年以上かかる。だから、15年から20年で山が戻るように木を見て択伐する。皆伐してしまえば次の原木がなくなり、山の暮らしが成り立たなくなる」。
それだけではない。山は保水能力が低下し、生態系や環境も狂い始める。「皆で本気で里山の管理をしないと大変なことになる」と正昭さんは訴える。そんな正昭さんに共鳴する岩澤健一さんは、神奈川県から移り住んで炭焼きになった。「学生時代に、正昭さんの仕事に共感を覚え、ヒッチハイクでやって来たんです。厳しい仕事ですが、寡黙に自然と向き合う仕事をしていると生きている実感がします。猛反対した両親も、3人の孫に会いに清川に遊びに来ますよ」。

窯は100年以上前からあるもので、その度補修しながら今も使い続けられている。

炭焼きは山仕事をしてこそ成り立つ。それは人と山が一緒に生きていくことにほかならないと語る原さん親子。
正昭さんも岩澤さんも、「みなべ里山活用研究会」のメンバーだ。清川の若者が中心になって、紀州備長炭の歴史と伝統を新しい世代に引き継ぐためにウバメガシの植林や、択伐による山づくりで里山の再生を図っている。「また来たくなるような清川にしたい」とスーさんが呟いた。清川の山と川、そして人々の生活の営みは、忘れ去られがちな日本の良き原風景を思い起こさせてくれた。

大学を卒業後すぐ神奈川県湘南から移住し、炭焼きになった岩澤さん。始めて20年のベテランの炭焼きだ。岩澤さんの焼いた紀州備長炭は、森林組合を通じて主に東京に出荷されるそうだ。