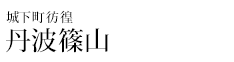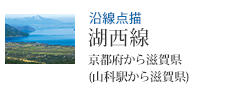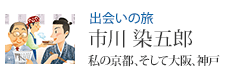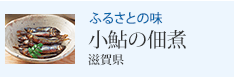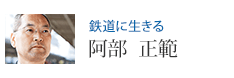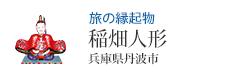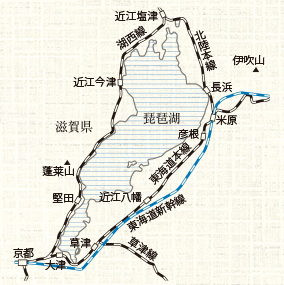
400万年もの壮大な歴史と、日本一の大きさを誇る琵琶湖。 豊かな水をたたえる母なる湖は、多種多様な生物の命を育み、 湖国に暮らす人々の営みを支え続けてきた。 郷土に伝わる味といえば、ホンモロコ、ビワマス、ニゴロブナなど、 湖の幸でつくる個性豊かな湖魚料理。 小鮎に代表される「湖魚の佃煮」は、 県の無形民俗文化財に選ばれている伝統食の一つである。
滋賀県のシンボル琵琶湖は、まわりを伊吹、鈴鹿、比良などの山々に囲まれるようにして、県のほぼ中央にすっぽりとおさまっている。 その形状が和楽器の琵琶に似ていることが名前の由来とされるが、古くは近淡海[ちかつあわうみ]、鳰[にお]の海などの呼び名で歌にも詠まれてきた。
湖の最も狭い部分には琵琶湖大橋がかかり、これより北を北湖、南を南湖と呼ぶ。この湖の大部分を占める北湖は南湖よりもはるかに深く、最深部は100メートル以上もあるという。このため、冷水性から温水性にいたるまでさまざまな生物が生息し、現在では50種類以上の魚類が棲む「淡水魚の宝庫」となっている。

明け方の湖面を、漁を終えた船が進む。夜間に網をしかけ、翌朝3時頃から引き上げることで、かかった小鮎をより新鮮な状態で水揚げする。
琵琶湖周辺には「鮒寿司」など、こうした多彩な淡水魚類を使った独特の湖魚料理が伝わっているが、琵琶湖産のアユで作る「小鮎の佃煮」もその一つ。アユは寿命が1年であることから「年魚」、その独特の香りから「香魚」などと呼ばれ古来より日本人に親しまれてきたが、琵琶湖の「小鮎」とは、アユの稚魚のことではなく、一生を琵琶湖で過ごすアユのことを言う。川を遡上し、苔などをエサとして大きくなる一般のアユに比べ、小鮎はプランクトンを主に食べるため、成魚でも10cメートル以下と小ぶりで苦味が少ないなどの特徴を持つ。琵琶湖では、小鮎の習性に合わせて多くの漁法が編み出され、定置網の一種「エリ漁」をはじめ、水中にカーテンのように網をしかける「小糸漁」、6月・7月の最盛期には、湖面に浮かぶ群れを漁船の先端に付けた網で豪快にすくい取る「沖すくい網漁」などが行われている。季節によって小鮎の行動が変化するため、それに合わせて漁法も変えると言う。
湖東の彦根市に本店がある「あゆの店 きむら」は、琵琶湖畔の食文化を伝承するアユ専門店として知られる。この店の「小あゆ煮」には、何より素材そのものへのこだわりがあるという。佃煮といえば、大量に捕れる時期のものを保存用に加工するのが一般的だが、この店で用いられるのは、主に水温低い3月頃から水揚げされる出始めの小鮎。三代目の木村泰造[たいぞう]さんによると、鮮度が落ちやすく、魚に脂が多くなる夏場のものより、小鮎本来の味わいが引き立つそうだ。また、さまざまな漁法の中でも、小糸漁だけで捕れる小鮎にこだわる。小糸漁は、捕れるアユの大きさが均一で、網から抜け出そうとする時に腹の内容物を吐き出すため、その味はクセがないのだという。早朝に揚がった新鮮な小鮎は、その日のうちに専用の醤油、地酒、砂糖に、ごく少量の水アメを加えて炊かれ、ふっくらと艶やかな佃煮に仕上げられる。
毎年5月、地元の祭りの際には、店先は子ども神輿の行列の休憩所となる。この時、「小鮎の佃煮」を子どもたちにふるまうのが20年来の習わしという。かつての家庭の味は、今では店の秘伝の味となって、次の世代へと受け継がれている。

「小鮎の佃煮」は、地域によっては「浜煮」や「醤油煮」などとも呼ばれる昔ながらの家庭料理。かつては、旬の時期には各家の味付けで炊かれていた。

醤油、酒、砂糖などの調味料が煮立った中に小鮎を投入し、約3時間アクを取り火加減を調整しながら炊き上げる。

6から8キログラムほどの小口炊きが「あゆの店 きむら」のこだわり。均一に味がなじみ、煮崩れなく仕上がるという。