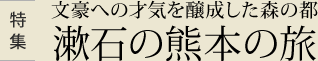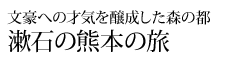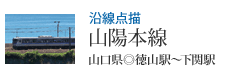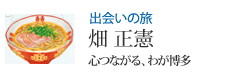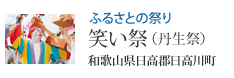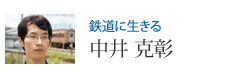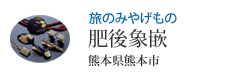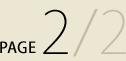

『草枕』が「新小説」に発表されたのは1906(明治39)年。2年間のロンドン留学から帰国した3年後、漱石39歳の時である。雑誌は発売3日で完売したほどの人気で、冒頭の「山路を登りながら、こう考えた」に続く文章は一世を風靡した。
「知に働けば角[かど]が立つ。情に棹[さお]させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい」。そうして、漱石の分身とおぼしき主人公の画工[えかき](画家)を通して描いたのは「非人情への旅」だ。“いやな奴”がはびこる俗世間を脱し、人情のしがらみから解放されて人間も自然の一点景であるような、そんな「美を生命とする非人情」の理想郷を探し求める画家の旅の話である。
際立ったストーリーはなく、芸術家の哲学的な独白とも芸術論とも読める。この『草枕』の舞台が熊本市の北西に隣接する、現在の玉名市天水町小天。有明海を隔てて向こう正面に「山」の字のような雲仙岳を望む、温暖で穏やかな里だ。

那古井の温泉宿のモデルになった前田案山子別邸には、漱石が宿泊した部屋が、ほぼ当時のまま保存されている。

小説『草枕』の「山を越えて落ち着く先の、今宵の宿は那古井[なこい]の温泉場」とは小天温泉。そして画家が投宿したのは当地の大素封家・前田家の別邸。骨董三昧のご隠居は、前田家当主の前田案山子[かがし]、ヒロインの那美[なみ]さんは案山子の次女の卓[つな]さんがモデルだ。文武に優れ、思想や意見を自由に表現する、そんな卓さんに漱石は惹かれたのかもしれない。
熊本市内の家を出発した漱石と山川は鎌研坂[かまとぎざか]を登る。渓流に沿った坂を息も喘ぎながら登りきると、鳥越峠の茶屋の井戸跡が残り、そのそばには茶屋資料館が建っている。さらに金峰山の北の山麓の竹林の道、薄暗い苔むした石畳の道を歩いていると、自然に世俗から離れていくようだ。そして、2つめの茶屋があったという野出峠を越えて眺めるその眺望は絶景の一語に尽きる。鏡面のような有明海、その海からせり出したように雲仙岳が正面にそびえている。漱石が見つけた非人情の理想郷、小説の那古井の湯は峠を下った里にあった。まさに桃源郷のような所である。

阿蘇中岳の噴火口。『二百十日』では、もうもうと立ち上がる噴煙を「百年の不平」に例えて社会を痛罵している。
もう一つの旅は阿蘇登山だ。短編の『二百十日』は、山川と2人で出かけたこの阿蘇から着想して書かれた。作中の「碌[ろく]さん」と「圭[けい]さん」という2人の人物にそれぞれの思いを託 し、漱石は当時の社会を痛烈に批評する。登山は、阿蘇神社に参詣し中岳をめざしたものの、折からの嵐に遭遇し途中で道に迷ってしまう。散々な目にあって下山せざるを得なかったが、噴煙を高々と吐きあげる阿蘇の猛々しさと、この時の非日常の登山体験そのものが作品のモチーフになっている。そして漱石は作品の終わりをこう結んでいる。「二百十日の阿蘇が轟々[ごうごう]と百年の不平を限りなき碧空[へきくう]に吐き出している」と。

この2作品のほか、『三四郎』や『吾輩は猫である』などにも熊本時代の体験が投影されている。『三四郎』は主人公が五高を卒業し、上京する夜汽車の車中からはじまる。漱石といえば一般的に『坊っちゃ ん』の「松山」の印象が強いが、むしろ熊本での生活や友人との交流が後の文豪・漱石の才気を育んだように思われる。