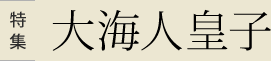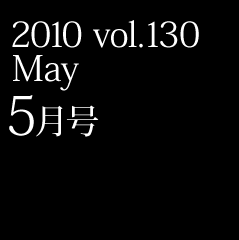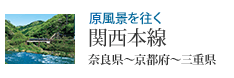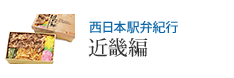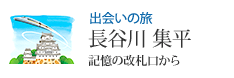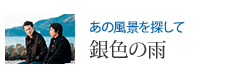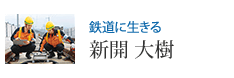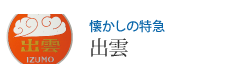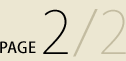

大海人皇子は天智天皇の弟だが、謎の部分が多い。出生年が不明で幼年期がほとんど分かっていない。いつも兄の影に隠れて目立たない存在だったのだろうか。その大海人皇子の名がおどり出るのが「壬申[じんしん]の乱」だ。
蒲生野での遊猟から数年を経て、天智天皇は病に倒れ枕元に大海人皇子を呼び、「後を任せる」と告げた。しかし策略家の兄のことだ、この場で素直に「はい」と答えたなら、謀反の疑いをかけられてその場で捕らえられるに違いない。そう察した大海人皇子は、すぐその場で吉野に出家を願い出ると、髪を剃り、妃である 野讃良[うののさらら](後の持統天皇)と子ども、数十人の供を従え 、逃れるように大津宮を後にした。その姿に朝廷の役人たちは口々につぶやいた。「虎に翼をつけて野に放つようなものだ」。
見送りの役人も、皇子の明晰さと勇猛さはよく知っていた。 それは朝廷にとって大きな脅威になる。追手の危険を感じた大海人皇子は吉野の深い山中に身を隠した。この時の道中の心境を後年に詠んだ長歌が「み吉野の 耳我の嶺に…」。ただ死を待つか、朝廷軍と戦うか、その迷いが次々に頭の中に去来したことだろう。
身を寄せた吉野宮は、吉野川上流の宮滝という小さな集落にあった。村人は大海人皇子をかくまい、食事や酒でもてなした。天智天皇が亡くなったのは吉野に逃れて数カ月の後だ。今や近江朝廷を支配するのは大友皇子。天智天皇の子で大海人皇子にすると甥。この親子ほどの年の差の甥に戦いを挑んだ。結末は朝廷に不満を持つ多くの地方豪族を味方につけた大海人軍の圧勝であった。

上の写真は、吉野川宮滝から上流の国栖(くず)にある浄御原神社。ここには今も大海人皇子にまつわる言い伝えが残る。

吉野川上流の国栖付近
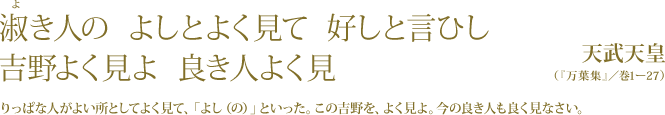

壬申の乱における大海人軍と近江朝廷軍(大友軍)との攻防は、近江、大和、河内など各地で展開された。最後の激戦となった瀬田の唐橋の戦いで大海人軍が勝利し、朝廷軍は敗走。大津宮は焼き払われ、大友皇子は25歳の命を自ら絶った。
大津宮は焼き払われ、勝利した大海人皇子は明日香に戻り、飛鳥浄御原宮[あすかきよみはらのみや]を造営し、天武天皇となる。その後の生涯は国の基盤づくりに努めた。律令体制を強固にし、国史として『古事記』や『日本書紀』の編纂に着手。また、唐の新しい文化を取り入れ、神仏を敬う信仰心を広めた。そうした天武天皇が築いた国の基盤の上に花開いたのが白鳳文化だ。
白鳳建築の代表ともいえる薬師寺は、病に倒れた讚良皇后の完治を祈って天武天皇が発願した寺院である。妻への愛情、あつい信仰心を持つ天武天皇が常に心を痛めたのは兄弟や叔父と甥が争った壬申の乱の苦い経験である。そして、かつて我が身を案じてくれた吉野の自然と吉野の人々に託して、「淑き人の よしとよく見て…」の歌を詠んだ。この歌には、子どもたちよ仲良くしなさい、二度と悲劇を繰り返さないようにという強い願いが込められ、6人の子どもらに誓わせた。だが、歴史は天武天皇の願いを叶えず、誓いは守られなかった。
明日香村の檜隈大内陵[ひのくまのおおうちのみささぎ]では、千数百年の時を経て、天武天皇は妻の持統天皇とともに今も仲睦まじく眠りについている。