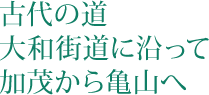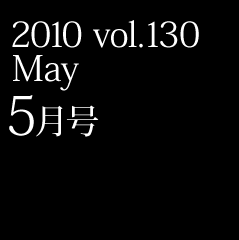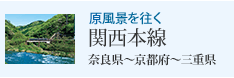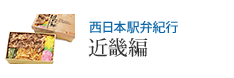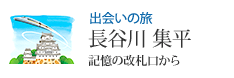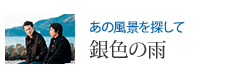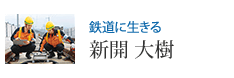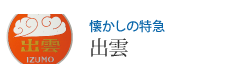関西本線は、大阪のJR難波駅と名古屋駅を結ぶ全長約175kmの線区だ。加茂駅から亀山駅間は非電化区間で、 山を抜け、峠を越え、田園地帯をディーゼルカーに揺られてゆっくりと走る心なごむローカル線の旅にでかけよう。
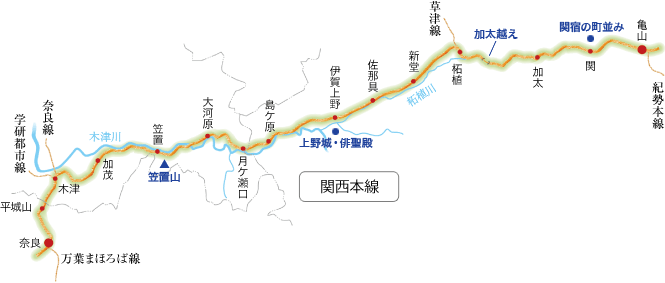
奈良駅から東へ3番目の加茂駅でディーゼルカーに乗り換える。ここからは単線に変わり、車両も1から2両編成となって、 ぐっとローカル線の趣になる。木津川を眼下に、山腹をへつるようにレールが続く。ほどなく走ると椀を伏せたような笠置[かさぎ]山が現れる。
笠置は、最近ではカヌーのメッカとして若者に人気の場所だ。町の中心を流れる木津川に、大人から子どもまでカヌーを楽しむ人が集う。また、笠置山中は巨岩や奇石の景勝地として知られる。「笠置」の名の由来は、笠置寺縁起によると、この地に狩猟に来た大海人皇子(天武天皇)が、山中で進退きわまり、弥勒仏に祈って難をまぬがれた。その場所を忘れないように目印として笠を置いて去ったという伝説によるものだそうだ。
駅を降りると徒歩で史跡を回る散策コースがいくつかある。なかでも山上の巨岩や奇石めぐりは途中下車する値打ちがある。日本で最大最古と伝えられる弥勒大磨崖仏[まがいぶつ]や驚くほどの巨岩に線彫りした虚空蔵石、胎内くぐり…。足下に木津川が山峡をぬって流れている。遠くの鉄橋を渡る列車は精巧な模型を見ているようだ。

カヌーのメッカでもある笠置。木津川の河原には、巨岩や奇石が無数にある。(写真提供:フジタカヌー)

笠置山より木津川を望む。関西本線は川に沿うように走る。

古来から石仏信仰の聖地だった笠置山。山中にある笠置寺はかつて修験行場として栄え、1300年の歴史を持つ。境内には弥勒大磨崖仏(高さ16m、幅15m)をはじめ巨岩、奇石が点在している。
木津川に沿って走る路線は、古代の大和街道とほぼ並走している。山間を抜けると、伊賀盆地が目の前に広がる。伊賀上野は間もなくだ。四方の山々で、外界から姿を隠しているかのような地形が“忍者の里”そのものだ。「上野忍町」という町があり、忍者の子孫だという人がいるのもいかにも忍者の里らしい。「百術」を会得した忍者の地を、人知を超えた「化けものの国」と怖れ、伊賀上野城主の藤堂高虎は「秘蔵の国」と呼んだ。町のシンボルは伊賀上野城。城は再建されたものだが、濠の石垣は築城時のままだという。町を散策すると、芭蕉生誕の地とあって随所に芭蕉ゆかりの史跡がある。

白鳳城とも呼ばれる伊賀上野城。戦国期に筒井氏が築城し、筒井氏改易後に藤堂高虎が大改築した。現在の城は昭和初期に再建された。

上野公園にある俳聖殿。芭蕉の旅姿を形どった八角堂で、殿内には伊賀焼等身大の芭蕉座像が安置されている。

伊賀流忍者博物館には、忍者屋敷や忍者にまつわる資料の展示のほか、忍術ショーも開催される。
伊賀を離れると、木津川は柘植[つげ]川に名称が変わる。伊賀盆地の田園風景の中を走るとやがて草津線と接続する柘植駅に着く。柘植の先は、「加太[かぶと]越え」で知られる随一の難所だ。壬申の乱の折に大海人軍が行軍し、本能寺の変では家康が敗走した「伊賀越え」の道である。この難所を越えるとエンジン音も軽やかに列車は山を下り続け、鈴鹿山脈の東の山麓に出る。江戸から数えて東海道五十三次の47番目の宿、関宿である。

東海道五十三次の宿場町、関宿。交通の要衝として活気に満ちていた。今も伝統的な風情ある町並みが残る。
旧街道にそって200軒ほどの古い佇まいの町家が軒を連ねる。東西約2km続く町並みは江戸時代の宿場の姿、雰囲気がそのままだ。本陣、商家、土蔵、民家など多彩な建物が通りに沿って並び、その一つ一つの町家の意匠や造り、屋根の瓦や細かな紋様細工を眺めるだけでも興味が尽きない。町家の外観をそのままにしたレトロモダンなギャラリーやカフェもある。関には、今なお江戸時代の空気が流れている。
そうして東海道46番目の宿、亀山でこの旅は終わる。変化に富んだ車窓の風景を楽しむ一時間半の旅は、心をなごませてくれる。

関宿にある最も古い町家を利用したギャラリーカフェ。薬草をブレンドしたお茶がいただける。
![原風景を往く[関西本線<奈良県・京都府・三重県>]奈良駅から亀山駅](img/location_img09.jpg)
亀山側から来る上り列車は加太駅を出発すると急勾配を登り、加太峠に差し掛かる。
![原風景を往く[関西本線<奈良県・京都府・三重県>]奈良駅から亀山駅](img/location_main.jpg)