 |
 |
|
春の陽ざしの中、握り拳を振り上げたような姿で
いっせいに萌え出すわらび。
素朴な味わいは、山菜の代表として
古くから親しまれてきた。
俳誌『玉藻[たまも]』を主宰し、女流俳人の先がけとして
活躍した星野立子[たつこ]の句とともに
里山に春を告げるわらびの情景をたどってみた。
|
 |
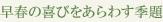 |
俳句において、わらびは春の季語として数多く詠われてきた。摘み採ったわらびは、さまざまな野の味わいに姿を変えることから、煮蕨・蕨汁・蕨飯などの語でも登場する。冒頭の句には、旬のもてなしとしての蕨飯が炊きあがるのを待つ期待感とともに、寛いだ心情が詠われている。わらびは、山野の日当たりのよい草地に生えるシダ植物の一種である。若葉が開かないうちは、先が丸く渦巻き、子どもの拳に似ているため、「蕨手[わらびて]」という呼び名もある。早春の野山をにぎわす山菜の中でも日本人にとっては馴染み深く、平安時代の『延喜式[えんぎしき]』にわらびを塩漬けにすることが記されているなど、食用の歴史は古い。また、和歌にもしばしば詠われ、志貴皇子[しきのみこ]の「石[いわ]走る垂水[たるみ]の上のさわらびの萌え出づる春になりにけるかも」(『万葉集』巻八)の秀歌に表れているように、芽を出したばかりの若いわらびは、待ちわびた季節の到来を象徴するものであった。

作者星野立子は、1903(明治36)年高浜虚子の次女として生まれ、結婚後23歳の頃より虚子の勧めで作句を開始。1930(昭和5)年には、初の女流主宰誌『玉藻』を創刊するなど、『ホトトギス』を代表する作家の一人である。

「自然の姿をやわらかな心持ちで受け取ったままに諷詠[ふうえい]する」と虚子が評したように、その句風は素直でためらいがなく、季語をいきいきと伝えることを身上とした。虚子は、発句の旅には立子を連れていったとされ、掲句も1935(昭和10)年に二人で京都嵐山に立ち寄った際に詠まれたものである。父と娘、水入らずのひとときのなごやかさと季語が一体となり、のどかな春の風景を思い起こさせる写生句となっている。
|
 |
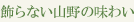 |
待ちに待った春、山野の雪もいつしか消え、いよいよわらびが芽吹き出す。次々と出てくる褐色の綿毛をかぶった、先が拳状に巻き込んだ柔らかい新芽を食用にする。かつて、こうした山菜採りの楽しみは、自然の恵みを味わうこと以上に、野遊びと称して小さな芽吹きを探しながら、春の1日を山野で過ごすことにあった。

|
| |
|
 |
 |
 |
 |
わらびは山菜の中でもアクが強く、まず木灰[きばい]や重曹で十分にアク抜きをする。その後、さらに火を通してから、お浸しや和え物、汁の実など季節の味に調理される。山菜は、採れる時期が限られる。そのため、一度にたくさん採ったものを、塩漬けにして長期保存するというのが昔からの生活の知恵であったという。

句の季語である「蕨飯」は、わらびの素朴な風味をいかしたご飯である。奈良県明日香村、西国三十三所観音霊場の第七番札所に数えられる岡寺[おかでら]の参道に立つ「坂乃茶屋」では、このわらびご飯が名物のひとつ。山菜にゅうめんと山ぶき煮が付いた定食を目あてに、参拝客が訪れている。この地で約50年、変わらぬ味を守り続ける大蔵さん夫妻によると、かつて店の裏山は太くて短い、良質のわらびの宝庫だったという。「あまり手を加えず、持ち味をいかすことが大切」というわらびご飯。鰹と昆布のだし汁、酒、しょう油の飾らない味つけであるが、炊き上がる頃、店内はどこか懐かしいような豊かな香りに包まれる。作者立子もまた、漂う香りの中で、のどかな時を過ごしたのであろう。わらびの葉が開き、シダが形を整える頃には、春も深くなっていく。
|
 |
 |
 |
 |
|
| 岡寺へと続く参道の坂道に立つ坂乃茶屋。 |
| |
 |
|
| 奈良市にほど近い、京都府相楽郡の和束町活性化センターでは、わらび摘みの体験ができる。4月になると特産の茶畑周辺の群生地はわらび摘みを楽しむ参加者でにぎわいをみせる。 |
|
|
 |
 |
|
|
 |