|
湖水から立ちのぼる水蒸気に野山にはいつも霞が漂い、しっとりとした空気が一面に立ちこめている。

琵琶湖の静かな湖水に浮かぶ竹生島[ちくぶしま]を繰り返し眺め、正子は日本の信仰の歴史に思いを寄せた。島は「前方後円墳そのままである。(中略)仏教が入ってきて、そこに観音浄土を想像したのも自然の成行きであったろう。竹生島の美しい姿自体が一つの歴史であり、神仏混淆[しんぶつこんこう]の表徴であった」と、著書『かくれ里』に記している。

竹生島は周囲2kmの小島で、日本古来の神と仏教とが習合した湖上の霊地である。島には仏教伝来以前の女神ツクブスマをまつる都久夫須麻神社[つくぶすまじんじゃ]と、弁才天を安置する宝厳寺[ほうがんじ]がある。古来のツクブスマの神は仏教の伝来の後に、水を意味する弁才天へと変身した。『近江山河抄』に「これが竹生島の歴史であり、私たちの祖先が経てきた信仰のパターンでもある」と正子は書く。二つの神仏は、今も篤い信仰の対象だ。

湖水は深い青色で、島は眺めるほどに尊く清らかで、神秘さを漂わせている。島の北側に突き出しているのは葛籠尾崎[つづらおざき]だ。入り江が深い湖北の景観は自然が色濃く残る。そのなかに姿を隠すように、菅浦[すがうら]の集落はひっそりとたたずんでいる。訪ねてくる人も少なく、むしろ外部の人を拒んでいるような雰囲気さえある。

菅浦には、奈良時代に政争に敗れ、皇位を奪われてこの地に幽閉された第47代淳仁[じゅんにん]天皇(733〜765年)の伝承が残る。菅浦に住む人々は、淳仁天皇の従者の子孫だと語り継がれ、集落の入り口には門が構えられている。そして、背後には人を簡単には近づかせないような急峻な山が迫る。その麓に、淳仁天皇をまつる須賀神社が建ち、本殿の裏には天皇の御陵と伝えられる遺構が残っている。

正子は、こうした菅浦に伝わる話を『かくれ里』にこう書いている。伝承の真偽はともかく、「そのような伝説が、ひそかに伝えられて来た事実はやはり私の心をひく。そして、それが菅浦の歴史であり、信仰でもあることを、私は疑う気にはなれないでいる」。千数百年を経た今も、語り継がれる伝説と人々の信仰心に正子は敬意すら覚えた。

湖北地方の木之本や高月[たかつき]地区の小さな寺々には観音像が多く残る。しかも「名作が多い」ことに正子は驚く。湖北は“観音の里”と呼ばれるほどで、なかでも特筆するのが、高月にある古刹、向源寺(渡岸寺[どうがんじ]観音堂)の十一面観音像だ。正子は「近江で一番美しい仏像」と感銘し、「こんなささやかな寺にかくれているのは、湖北の性格を示すものとして興味がある」と指摘する。

ひっそりとたたずむ里に暮す人々の敬虔な祈りが、観音像を守り継いでいるところに日本人の心を見い出し、正子はある種の安堵感を覚えたに違いない。
|
|
 |
|
 |
|
| 竹生島にある宝厳寺の唐門(国宝)。豊臣秀頼によって移築された門には細緻な彫物が随所に施されている。 |
|
 |
|
| 淳仁天皇をまつる須賀神社。石段手前のからは、素足でお参りするのが習わし。 |
|
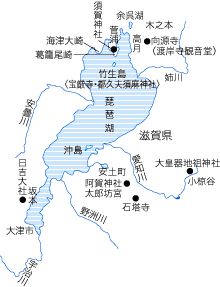 |
|
|
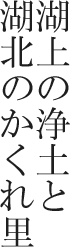 |
|
 |
|

宝厳寺は厳島、江ノ島と並ぶ日本三弁才天の一つ。写真は前立の弁才天像で、御本尊は60年に一度だけ開帳される。 |
|

白洲正子が「近江で一番美しい仏像」と評した向源寺〈渡岸寺観音堂〉の十一面観音像(国宝)。 |
|

十一面観音は、十一の苦を仏果に変えて絶大な功徳を施す現世利益の菩薩。頭部真後ろの「暴悪大笑面(ぼうあくだいしょうめん)」は、悪を暴いて笑い飛ばし、良心を目覚めさせる意味を持つ。 |
|