 |
 |
「紅花栄[こうかさかう]」。
暦の七十二候では、5月26日〜30日頃、
紅花が盛んに咲く季節をこう呼び習わす。
橙黄色の可憐な花姿は、古くから歌に詠まれ、
また、さまざまな用途で暮らしに溶けこんできた。
ホトトギスの女流俳人 田畑美穂女[みほじょ]の句とともに、
紅花と日本人との関わりの歴史を辿ってみた。
※七十二候とは、大まかな季節の移り変わりを示す
二十四節気を、さらに具体的な現象で表したもの。
|
 |
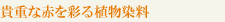 |
紅花はキク科の1年草または2年草で、頭状花という小さな花が集まったアザミに似た花をつける。原産地は、中央アジアやエジプトのナイル川流域と伝えられる。日本へはシルクロードを通り、中国から朝鮮半島を経て渡来したとされている。「くれなゐ」という古名は、中国の呉から伝わった藍(染料)という意味の「呉藍」に由来するという。『万葉集』や『古今和歌集』には、「末摘花[すえつむはな]」の名で登場している。「末摘花」というのは、茎の末端に咲く花を摘み取ることをさし、花弁は布や紙を染める染料や口紅、頬紅などの化粧品の原料として用いられてきた。また、紅花には血行をよくする薬効があるとされ、女性の肌着を染めたり、乾燥させた花は生薬としても利用された。

咲き始めの黄色からしだいに紅色に移り変わるように、紅花にはふたつの色素が含まれている。そのうち、赤の色素は黄色の色素に比べて少量のため、紅花からとれる「紅」はとても貴重なものであった。とりわけ、何度となく染め重ねた濃い紅色は「韓紅花[からくれない]」と呼ばれ、「中紅花[なかくれない]」や「退紅[あらぞめ]」といった薄い色目のものとは区別されていた。平安時代には紅の濃い色は「禁色」として着用が制限され、その後も寛永年間(1624〜44年)には「紅花染使用禁止令」が出されるほど、高価で贅沢な植物染料であった。その価値は、「紅一匁は金一匁」といわれ、同じ目方の金によって取引されたと伝えられている。
|
 |
 |
|
| 可憐な花で彩られた榮井さんの紅花畑。開花時期は6月末から7月にかけてで、黄色が鮮やかなうちが摘み時という。紅花の葉には棘があるため、露のある早朝に摘むのがよいとされ、美穂女も「露の干ぬ間」という表現で紅花摘みの情景を際だたせている。 |
|
 |
|
| 摘んだ後の花びらは、約10日間天日干しにされる。かつては花を水洗いして黄色の色素を取り出した後、餅状に搗いて「紅餅」に加工したものが京へ運ばれたという。 |
|
 |
|
| 熟した梅の実を燻して作る「烏梅(うばい)」。紅花染めにとって色素を定着させ、鮮やかに発色させる媒染剤として欠かせない。奈良市月ヶ瀬の中西喜祥氏が日本でただ一人、その技術と文化を継承している。
|
|
|
|
 |
![紅花[べに]摘みに露の干ぬ間といふ時間 美穂女](image/poet_text.gif) |
 |
 |
 |
田畑美穂女、本名秋子は、1909(明治42)年に大阪・船場の道修[どしょう]町で生まれた。道修町は、薬の町として知られているが、美穂女の生家も薬種商を営んでいた。三男四女の長女であった美穂女は、店に奉公していた13歳年上の富夫と養子縁組して結婚。1967(昭和42)年に夫が亡くなった後は、自ら家業を受け継いで製薬会社の社長職を務めた。豊かな家庭に育った美穂女は、幼い頃から祖母や母の影響で文楽、歌舞伎、芝居に親しみ、『源氏物語』などの古典を好んだという。また、歌人であった父の影響を受け、若い頃は西行を学ぶなど、短歌に傾倒していたと伝えられる。その後、俳誌「ホトトギス」を手にしたことから俳句を志すようになり、1936(昭和11)年、美穂女27歳の時より高浜虚子に師事。「ホトトギス」と虚子の次女である星野立子が主宰する「玉藻」に所属して句作に励むこととなった。さらに、1949(昭和24)年には「ホトトギス」同人となり、虚子亡き後も年尾、稲畑汀子のもとで客観写生による句作の姿勢を貫き続けた。掲句は、行動派であった美穂女が、紅花みたさに山形まで出かけた際に詠まれたもので、第一句集『美穂女抄』及び『吉兆』(ともに1982年刊)に収められている。

|
 |
 |
 |
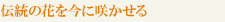 |
現在、紅花といえば山形産という印象を持つが、耕作がさかんになったのは江戸時代に入ってからのこと。それ以前は西国の各地に産地があった。平安時代、紅花の生産は各国に割り当てて賦課され、『延喜式』(927年)には伊賀、伊勢、尾張、上総、信濃、加賀など24の産地が記されている。中でも、伊賀国は「七斤八両」という目方まで規定され、一大生産地であったことがうかがえる。三重県伊賀地方は、古くは「隠国[こもりく]」と呼ばれた小さな盆地。東に高地を控え清流にも恵まれた地形は、深く低く朝霧がかかり、直射日光を好まない紅花の作付けには適地であった。元禄の頃までは産地として上位にあったとされるが、やがて紅花は稲作に取って替わられた。

伝統の地に紅花を復活させたのは、伊賀市の榮井[さかい]功さんである。京都の染色家吉岡幸雄さんから依頼されたのがきっかけで2005(平成17)年の春から始まった栽培は、今年5回目を迎える。榮井さんによると、栽培を左右するのは天候で、成育と収穫の時期に晴天に恵まれることが条件であるという。また、紅花にとってよりよい環境を作るため、しいたけの菌床をもとに米ぬかやフスマなどをすき混む土壌づくりは、1年を通じての作業になるそうだ。丹精こめて育てられた紅花は、奈良・東大寺「お水取り」の花拵えの材料として奉納される和紙を、色鮮やかに染めている。
|
 |
 |
|
| 李時珍によって書かれ、中国から日本へ伝わったとされる『校正本草綱目』。薬学史料の中にも、紅花の薬理作用が記されている。(大阪市立図書館蔵) |
|
| |
|
|
| |
 |
 |
|
|
 |