|
 |
 |
〜場所じゃ場所じゃ吹屋は場所じゃ〜

場所とは「繁華な町」という意味である。江戸時代後期から昭和の中頃までの吹屋は、荷を積んだ牛馬がひっきりなく往来し、倉敷と並ぶほど活気に溢れていたという。銅の生産とあいまってベンガラ製造が吹屋にいっそうの富をもたらした。

町並保存会会長の小川博さんは、吹屋の町は銅山師よりも「むしろベンガラ製造で莫大な富を得た豪商たちがつくりあげた町なのです」と話す。ベンガラは「弁柄」とも「紅殻」とも書く赤色顔料で、吹屋は「ベンガラの町」とも呼ばれる。

通りに並ぶ妻入り、平入りの豪奢な構えの商家もほとんどがベンガラ製造で財を築いた長者屋敷である。インドのベンガル地方から輸入されていたことから「ベンガラ」と呼ばれるようになったこの赤色顔料は、絵具、染織、輪島塗りなどの漆器や伊万里焼や九谷焼など陶器の着色顔料として、また優れた防錆・防腐効果は建築や船底塗料等々に欠かせない。古くは中国などからも輸入され、また鉄分を含んだ粘土を焼いたり鉄錆から採取してつくられたが、吹屋で製造されるベンガラは品質が格段に優れ、「赤の中の赤」と珍重されて日本全国をはじめ、海外にまで広まったという。

ベンガラの主成分は酸化第二鉄で、吹屋の銅山で産出される硫化鉄鉱を原料として生まれた、いわば銅の副産物である。吹屋ベンガラが誕生したのは江戸時代の1707(宝永4)年だが、こんな逸話が残っている。「火鉢の中の焼石を庭先に捨てたところ、降っていた雨に濡れて水が赤くなった」。これにヒントを得て、鉱石を焼いて水洗いすれば赤い色素が得られることを偶然に知ったという。そして吹屋を治めていた時の代官、早川八郎左衛門正紀はベンガラの商品価値を見抜き、吹屋で独占的に製造することを奨励した。そのために吹屋の人はいまでも「早川代官はえらい人です」と町の恩人としてたたえる。

ベンガラ生産が本格的になるのは1751(宝暦元)年。吹屋長者を代表する家の一つで、町を下ったところに豪壮な屋敷を構える西江家、同じく町とは離れたところに城塞のような屋敷を構える広兼家、橋本家などがベンガラの原材料になるローハ(緑礬)を製造。このローハは吹屋のベンガラ業者の工場に運ばれ、釜で焼成され、水槽にいれて不純物を取り除き、天日乾燥の後に赤い粉末状のベンガラとなり、これを袋詰めにして出荷された。江戸時代には大坂の商人を通じて、明治以後は吹屋商人が直接、全国の顧客と取引するようになった。

中町のほぼ中央付近に屋敷を構える本片山家は、吹屋を代表するベンガラ豪商で屋号を「胡屋[えびすや]」といい、間口は10間だが奥行きは40間にも及ぶ大邸宅である。斜め向かいの「長尾屋」、本長尾家は江戸初期に吹屋に移り住み、タタラの鉄を扱う問屋だったが幕末にベンガラ製造を始めた。母屋は18世紀末の建築で吹屋でもっとも古い建物の一つといわれている。早川代官はベンガラを生産するにあたって株仲間を組織させ、ローハの総量規制や値下げ競争の禁止を規定した議定書をつくり、吹屋ベンガラの商品の安定と発展に尽力したという。こうして、江戸、明治、大正、そして昭和にかけて吹屋は繁栄をほしいままにする。「米一升が10銭の時に、ローハ百匁[もんめ](375g)は60銭もした」。しかし最後のベンガラ業者であった田村家が製造を止めて、1974(昭和49)年に吹屋ベンガラの歴史は断たれる。化学製法にとって替わられたのだが、現在でも「色は吹屋ベンガラに及ばない」という。

ベンガラ豪商がつくった吹屋の町並み。この歴史的な家々の佇まい、町の景観は豪商たちの夢の跡であるとともに、彼らが現代に残してくれた貴重な文化遺産でもある。 |
|
 |
|
 |
|
【広兼邸】
山上近くにある建物の豪奢さ、高く組まれた石垣の豪壮さを仰ぎ見ると、その圧倒的な迫力に驚かされる。敷地は581坪あり、屋敷は部屋数が56室ある。映画『八つ墓村』のロケに使われた。 |
|
 |
|
【広兼邸の内部】
玄関を入ったところの土間から奥に4部屋が連なっている。手前左下に見えるのはオクド(かまど)さん。屋敷は県に寄贈され、現在は一般に公開されている。 |
|
 |
|
| ローハ豪商の西江家の屋敷は、どこか西洋的な雰囲気もする大邸宅である。江戸時代には御用銅山を経営し、代官御用所もつとめた吹屋の豪商で名家。 |
|
|
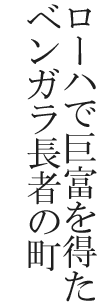 |
|

吹屋町並保存会の会長、小川博さんは定年退職して吹屋に戻り、伝統的な町並みの保存に力を注ぐ。 |
|
 |
|

粉末状のベンガラ。ベンガラは赤色の着色材として、また優れた防腐・防錆効果によってさまざまな分野・用途で用いられた。 |
|

伊万里焼・九谷焼・清水焼など陶磁器の絵付の赤色顔料として吹屋のベンガラは日本一だった。 |
|

「ベンガラ館」は、吹屋で最後までベンガラを製造していた田村家(屋号/福岡屋)の工場を整備したもの。ベンガラになるまでの工程を常設展示している。 |
|

1921(大正10)年頃の本片山家のベンガラ工場。 |
|
|