|
岡山駅から総社を経て、伯備線の備中高梁駅まで特急で約40分。古くから瀬戸内と日本海とを結ぶ交通の要衝であった高梁から中国山地の山懐へ入る。吹屋へは、備中川面町を通ってさらに小一時間。勾配の急な曲がりくねった山道を行くと、吉備高原に至る。高原といっても地形は険しく、道幅は狭い。眼下には深く鋭く削ぎ落ちた渓谷が随所にみられる。

林間の道を進んでいくと、赤い家並みが忽然と現れた。町を貫く通りに沿って建ち並ぶ家々は、石州瓦の朱色の屋根と赤い壁のせいで、全体が夕陽に染まったように見える。通りを歩くうちに、時を遡ったような不思議な感覚にとらわれた。現世の匂いがまったくしない。通りには電信柱も電線も、派手な看板も見当たらない。

家々はほとんどが江戸時代から明治・大正期にかけて建てられたものだ。吹屋の町は標高500mの西地区(千枚・中町・下町)と標高450mの東地区(白石・下谷)とに分かれ、全体は距離にして約1.5km。家々はそこかしこに町の栄華を記憶にとどめ、昔の姿そのままである。軒高の低いベンガラ格子の商家、白壁の土蔵、屋根の卯立[うだつ]、家紋入りの鬼瓦、牛馬を繋いだ鉄輪…。なかでも吹屋の中心を成すのが中町で、商家の構えや造りはみな豪奢で風格がある。

これほどの町が山深い高地に形成されたのは驚きだが、それには「吹屋」という地名に関わりがある。「吹く」とは、銅を精錬するという意味で精錬所をもっている家を吹屋という。吹屋銅山の発祥は平安時代、町に伝わる古文書には「大同年間(806〜808年)鉱山師あり」という記述がある。南北朝末期(1400年頃)という説もある。いずれにしても中国山地は古代から砂鉄や銀、銅を多く産出してきた。吹屋もその一つであったのだろう。

吹屋銅山が活況を呈するのは江戸時代になってからである。現在の町の基礎が形成されたのもこの頃だ。大坂の豪商、泉屋吉右衛門(後の住友の祖)が幕府から銅の生産を請け負い、産出量を大いに増やし西国一の銅山の名声を得る。各地から人が集まり、働き手は1,000人を超え、山中に賑やかな鉱山町ができた。が、泉屋はわずか20年ほどで新たに発見された四国の別子銅山へと移る。その後は地元の銅山師が請け負うが、1873(明治6)年に三菱の創始者・岩崎弥太郎が吹屋銅山の経営に着手する。

三菱は莫大な資本と近代技術を鉱山に注いだ。自家水力発電による排水ポンプを導入し、洋式溶鉱炉による精錬、さらに専用のトロッコ軌道を敷設するなどして、吹屋銅山は明治から大正にかけて従業員1,300人以上を数える日本三大銅山の一つとして最盛期を迎えた。ところが第一次大戦後の不況とその後の世界恐慌で、三菱は1932(昭和7)年に銅山を閉鎖。第二次世界大戦後に再び生産されたが1972(昭和47)年に閉山され、吹屋銅山の長い歴史は幕を閉じた。鉱山で働く大勢の人が往来した通りは今ではひっそりしているが、かつての賑わいをうかがい知る唄が残っている。 |
|
| 〜吹屋よいとこ金掘るところ、掘れば掘るほど金が出る〜 |
|
 |
|
 |
|
【笹畝坑道[ささうねこうどう]】
江戸時代から大正時代まで黄銅鉱や硫化鉄鋼を採掘した。「ふるさと村整備事業」で復元・整備された坑道は300mほどで、随所に斜坑があり地中奥深くつづいている。 |
|
 |
|
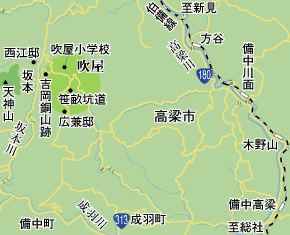 |
|
|
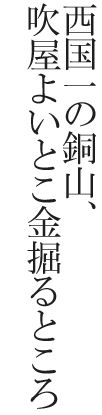 |
|

【吉岡銅山跡】
石やレンガを積みあげてつくられたかつての銅山の構造物や排水用の溝がある。 |
|

1918年(大正7)頃の吉岡銅山。まるで要塞を思わせる。写真右上の山上付近に選鉱場や精錬所があり、右下には鉱山本部の建物がある。 |
|
 |
|

吹屋の銅山で採掘された銅の原石。ほんの微量だが原石には金や銀も含まれる。 |
|

銅山の神様をまつる山神社。17〜8世紀の創建と伝えられ、明治時代には岩崎弥太郎が玉垣を寄進している。 |
|

吹屋小学校は、1900(明治33)年に三菱の鉱山事務所跡に建てられた。現役の木造校舎としては、日本でもっとも古い。県の重要文化財でもある。現在、10人の子供たちが通い、4月からは6人となる。 |
|