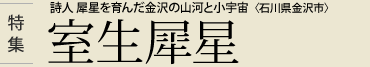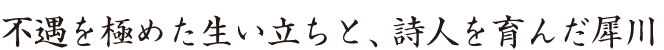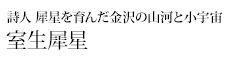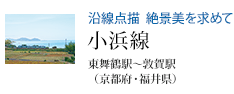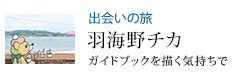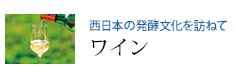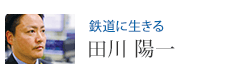朗々と流れる犀川の畔りを歩けば、遠くに屏風のように連なる白山連峰に続く山々や医王山[いおうぜん]の雄姿が眺められ、足元の水辺では水鳥が羽を休めている。
「この犀川の上流は、大日山という白山の峰つづきで、水は四季ともに澄み透って、瀬にはことに美しい音があるといわれていた。私は手桶を澄んだ瀬につき込んで、いつも、朝の一番水を汲むのであった」
小説『性に眼覚める頃』の一節には、少年犀星の日常の風景が描かれている。犀星が故郷を想うとき、まず浮かんでくるのが犀川だった。犀星が見つめ続けた風景は、今も昔も変わらない。
室生犀星の名は、犀川に由来している。生まれ、育った家は犀川の西岸にあり、「西」に「星」をあてがい筆名とした。本名は赤井照道[てるみち](後に、室生照道)。犀星の生い立ちは、生まれた時から複雑だ。犀星は1889(明治22)年に、金沢市裏千日町に生まれた。父は旧加賀藩士であった小畠弥左衛門吉種[よしたね]。母は定かではないが、小畠家の使用人とされている。この時、吉種は64歳。世間体を気にしてか吉種は、近くの犀川の畔りにある「雨宝院[うほういん]」の住職 室生真乗[しんじょう]の内縁の妻、赤井ハツに生まれてすぐに養子に出してしまう。室生家には犀星の他に血の繋がりのない兄妹があり、長女のテエ、長男の真道[しんどう]、妹きんの6人家族だった。小畠家は雨宝院から歩いてすぐの距離だが、養母ハツにより行くことをかたく禁じられ、犀星は生涯、生母の消息すら知ることはなかったとされる。

犀星が生まれてすぐに引き取られた雨宝院。白山を開山したと伝わる泰澄大師を創始とする密教寺院で、犀星はここで育った。

雨宝院の近くにある神明宮(しんめいぐう)。幼少の犀星は、境内でよく遊んでいたという。御神木の“神明の大ケヤキ”は樹齢1000年を超える。

-
1889(明治22)年…
生後ほどなく赤井ハツの養子として雨宝院に引き取られる
-
1896(明治29)年…
室生真乗の養嗣子となり室生照道を名乗る
-
1902(明治35)年…
高等小学校を中退し金沢地方裁判所に就職、上司より俳句を習う
-
1908(明治41)年…
金沢区裁判所金石出張所に転任。翌年に退職し地方新聞社に勤務
-
1910(明治43)年…
上京。下宿を転々とする
-
1912(明治45)年…
7月に帰郷。生活の窮乏で帰郷と上京を繰り返す
-
1918(大正7)年…
1月『愛の詩集』を自費出版。9月『抒情小曲集』刊行
-
1923(大正12)年…
関東大震災で家族とともに金沢に帰る
-
1928(昭和3)年…
義母ハツ死去。大正15〜昭和4年まで金沢で庭作り
-
1935(昭和10)年…
芥川賞選考委員となり、第16回まで続ける
-
1941(昭和16)年…
講演のため金沢に帰る。これが生涯最後の帰郷となる
-
1956(昭和31)年…
『杏っ子』を東京新聞に連載開始
-
1962(昭和37)年…
最後の詩『老いたるえびのうた』を書き上げた後、逝去。享年72歳

「犀星のみち」から見る雨宝院の裏手。当時は雨宝院の庭と犀川の河原は続いており、犀星は毎朝、水汲みをした。

1903(明治36)年頃の養家の家族写真。写真は手前右から養母赤井ハツ、次女きん、長女テエ、中央が長男真道で、左上の円内が14歳頃の犀星。室生家は、養父真乗を加えた6人家族だった。(写真提供:室生犀星記念館)

雨宝院の庭には、作品にも出てくる犀星の好きだった杏(あんず)の木が今も健在だ。

金沢市の北西にある金石(かないわ)地区、犀川の河口。犀星19歳の時、金沢区裁判所金石出張所雇員として過ごし、青春期の孤独な感傷を謳った。
1900(明治33)年、10歳で金沢市立長町高等小学校(四年制)に入学するも、学校になじめない犀星は中途退学する。その後、兄の真道が勤めていた金沢地方裁判所に給仕として勤務し、お茶運びなどの雑用係となった。苦悶の日々の犀星を救ったのが、俳句だった。芭蕉ゆかりの金沢は元禄の頃から俳諧の盛んな町で、職場の先輩には優れた俳人であった河越風骨[かわごえふうこつ]や赤倉錦風[あかくらきんぷう]がいた。この裁判所勤務が、犀星にとって大きな転機となる。
「自分が俳句に志したのは十五歳の時である。当時金沢の自分のいた町裏に芭蕉庵十逸[ばしょうあんじゅういつ]という老翁が住み、自分は兄と五六度通うて発句の添削を乞うたのが始である」と、後に語っているが、最初は続かなかった。しかし、裁判所では正岡子規を代表する俳句の新派である新俳句を嗜む先輩らに指導されながら、句会にも参加するようになった。俳句に夢中になった犀星は、真綿が水を吸うように才能を現し、わずか2年でホトトギス派の俳人が選定する『北國新聞』に句が初掲載された。そして、新派俳諧結社「北声会」という俳句の月例会にも出席する。やがて、犀星は『少年世界』や『中学文壇』などの雑誌に投稿し、詩や短歌、小品文などの創作を手がけていく。
20歳になった犀星は詩人への憧れを胸に秘め、裁判所を退職。その翌年に、定職のあてもなく金沢駅から夜行列車で上京する。しかし、現実は厳しく、犀星はたちまち生活苦に陥った。駒込、根津、谷中、千駄木など居を転々とした後、困窮の果てに帰郷する。金沢に帰った犀星は、当時新築された石川県立図書館にこもり、詩の創作に没頭した。都落ちしたその心情を吐き出すように、『朱欒[ザンボア]』『スバル』『詩歌』『創作』などに投稿し、56篇の詩が掲載される。

1910(明治43)年、犀星20歳で上京。上京した犀星を迎えに来た幼友達。3人の友達は東京美術学校の生徒だった。写真左から2番目が犀星。
(写真提供:室生犀星記念館)

北原白秋によって1911(明治44)年から発行された『朱欒』。白秋は犀星の詩を評価し、発表の場を与えた。大正2年1月〜5月に、犀星の詩15篇が掲載された。帰郷後の都落ちした心境を表現し、後に『抒情小曲集』に収められる詩を「北國新聞」「朱樂」「スバル」などに発表する。
(写真提供:室生犀星記念館)