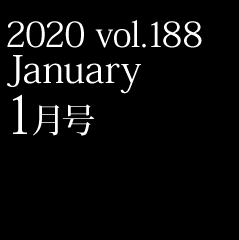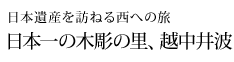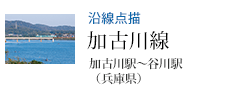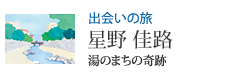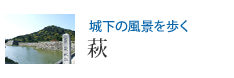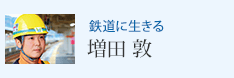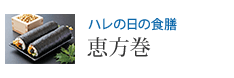城崎変電所内、交流遮断機の点検作業。圧力計の数値が規定値かどうか、過去のデータと照らし合わせ確認するとともに、異音や油漏れ、熱を持っていないかなど細部にも目を配る。
列車の安全・安定輸送はもとより、信号や駅の照明機器に至るまで、鉄道輸送に欠かすことができない電気。入社以来、電気設備の保全や設計、指令業務など、電気一筋に経験を積む増田は、電気を安定供給するという使命を胸に、さらなる品質の向上に励む。

電車線や信号に送る電気をコントロールする配電盤設備。検査で異常があれば、データ履歴から原因を調べる。
増田の入社は2004(平成16)年4月。学生時代、電気を専門的に学び、電気がどのように列車を動かすのかに興味を持ったことが志望の動機という。最初に配属された部署は福知山電気区。以来、兵庫県北部・京都府北部エリアを中心とした沿線の電気設備管理を担う。
列車に電気を送るための「電車線設備」、照明などの「電灯電力設備」、電力会社から供給される電気を鉄道に最適な形に変換して各施設に送る「変電設備」など、電気設備の管理は多岐にわたる。増田は、中でも電車線設備の検査や修繕工事における経験が長い。入社直後に携わったのは、山陰本線の城崎温泉駅から船岡駅、さらに東舞鶴駅までの舞鶴線や福知山線の一部などの架線の検査だったという。増田は、先輩の後を追いながら作業を観察し、技術の習得に努めた。同時に、架線作業車※を運転して架線の検査を行うための停電手続き、線路閉鎖工事など作業の安全確保のための手順やルールについても学んだ。「パンタグラフが直接接触するトロリ線は、摩耗するため限度になれば交換が必要です。その直径を、数ミリ単位にこだわって測定する先輩の姿から、断線など重大な故障を起こさないための日々の設備管理の大切さを学びました」。
※架線の保守点検に使われる線路と公道の両方を走行できる特殊車両。

施工の打ち合わせでは、図面と照らし合わせて現場での作業と安全を確認。
2008(平成20)年10月、福知山支社電気課に異動になった増田は、新たに工事設計を担当する。検査で設備に不具合が見つかれば、その取り替え工事のための計画を立て、図面を描く。施工を担うグループ会社の担当者との打ち合わせ、発注や契約業務なども初めての経験だったという。そんな中、これまで自分のペースで仕事を進めてきた増田は、自身の設計の遅れによって、土木や建築なども関わる支障移転工事の工程を大幅に遅らせる事態を招いてしまった。「設計の1日の遅れが現場では1カ月の遅れになる」。当時の上司の言葉が胸に刺さった。「鉄道の仕事は、多くの人たちが繋がって成り立っていることを肝に銘じた苦い経験です」と語る。
その後も増田は、変電所や架線など電気設備の異常を監視し復旧手配などを行う電気指令、輸送障害や労働災害が発生した場合の対応や検証にあたる保安業務など、電気の安全管理に幅広く携わる。中でも、忘れることができないのは、保安業務を担当していた頃、和田山変電所の老朽化に伴う設備の取り替え作業時に発生した感電負傷事故だ。特に感電事故防止には注意が払われてきただけに、報告を受けた時は頭が真っ白になったという。増田は、保安担当として、事故の原因究明や分析に当たった。また、負傷した協力会社の方を見舞い、聞き取り調査も行った。「事故は、ルールが一部省略されたことによって起こったものでした。幸い、命に別条はなかったものの、協力会社の方が重傷を負うという労働災害が発生した重大性を重く受け止め、現場で安全対策のルールや手順が守られるためには何が必要なのかを考え、対策を講じました」。

設備管理において重要な資料となる検査データの入力を指示する。
現在、係長として豊岡電気区電力グループを率いる増田は、若手を指導する際にも安全対策のルールや作業手順の「目的」を伝えることに心を配る。事故を検証する中で、ルールそのものではなく、なぜこのルールがあるのかを理解する必要性を強く感じたからだ。「ルールに沿った手順を踏むことは、仲間や自分の命を守ることでもあるのです」。その後新たに定められた感電事故防止のためのルールを、和田山での感電負傷事故に関わった者の一人として、社員、グループ会社に徹底することで今、現場の安全を守っている。
さらに、増田は電気設備の品質管理の向上にも熱心に取り組む。「雪の重みでしなる竹は事前に除去して断線を防ぎ、照明の球切れをなくし駅を明るく保ち、お客様に安全に安心して鉄道を利用していただく。大切なことは、先手先手の対応です」。また、一つひとつの設備に愛着を持つことで気づきや工夫が生まれ、それが管理の品質を高めることに繋がると話す。「しっかり管理されたJR西日本品質の電気設備を提供していきたい」。増田の想いは技術と共に、次の世代に受け継がれていく。