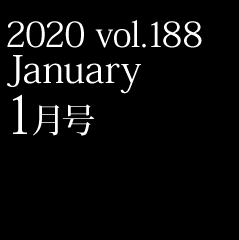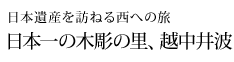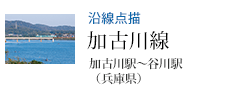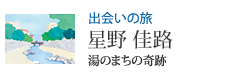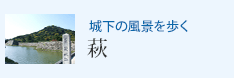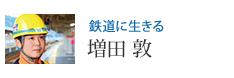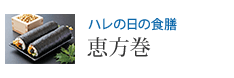毛利氏三十六万石の城下町として栄えた萩。
町を歩けば、お椀を伏せたような小高い山が顔をのぞかせる。その山裾に築かれた城郭は、石垣を残すだけとなった今も優美な曲線を堀に映し、森厳かつ神秘的な雰囲気さえ漂わせている。白壁と黒板塀が織りなす風景の中に、幕末の英傑ゆかりの史跡が散在し、町は往時の姿のままに歴史を物語る。

山陰本線「玉江駅」から徒歩約20分。「萩バスセンター」からバスで約8分、「萩城跡・指月公園入口/北門屋敷入口」バス停下車、徒歩すぐ。


日本海に張り出した標高143mの指月[しづき]山山頂の山城と麓の平城を合わせた平山城。南麓に本丸、二の丸、三の丸が梯郭[ていかく]式に配置され、本丸南西隅の天守台(写真上)には5層5階の望楼型天守が築かれた。天守閣跡(写真下)には、在りし日の天守を偲ぶ礎石が残る。別名指月城。


豪商江戸屋に由来する江戸屋横町には、黒板塀が連なる風情ある町筋が残り、幕末の志士ゆかりの旧跡も多い。
萩城城下町は、日本海に注ぐ松本川、橋本川に挟まれた三角州の上に立地している。突端の島のように海に張り出した指月山とその山麓に城を築いたのは、萩藩祖 毛利輝元[てるもと]。関ヶ原の戦いの敗戦により、本拠広島城を失った輝元は、1604(慶長9)年、まず山上の詰丸[つめまる]から築城を開始した。
萩城の特色は、自然の地形を巧みに活かした縄張にある。詰丸は、山頂を切り開いた平地に石垣を築き、二重櫓や櫓門が構えられていた。井戸代わりの用水槽が設けられ、中世の山城の機能を備えていたという。南麓の平坦地には、本丸、二の丸、三の丸がそれぞれ内堀、中堀、外堀によって区画された。本丸は、コの字に巡らされた内堀で守られ、藩政の中枢を担う広大な本丸御殿があったと伝わる。南西隅に築かれた天守台には、5層の白亜の天守閣が聳えていた。
現存する遺構の一つ内堀にかかる極楽橋を渡れば、現在は指月公園として整備された城跡が広がる。1874(明治7)年、天守などの建物は解体されたが、かつての本丸には天守閣跡や豪快な武者走りの石組みが残り、城外から移築された13代藩主毛利敬親[たかちか]ゆかりの茶室「花江茶亭[はなのえちゃてい]」などの旧跡が緑の中に収まっている。

堀内、平安古には、敵の侵入を防ぐため左右を高い土塀で囲み、鍵手形〈直角〉に曲げた鍵曲(かいまがり)と呼ばれる見通しの悪い道筋が残る。

明治維新後、禄高を失った士族救済のため、武家屋敷の庭を利用して栽培が広まったという萩の夏みかん。開花時の5月頃には、城下は甘い香りに包まれる。

藩の御用窯として発展した萩焼。伝統的な白萩に加え、土の配合や釉薬の色に変化を持たせた青萩など、新しい色の魅力が生まれている。(千春楽 城山製)
築城当時、三角州には沼地や葦原が広がり、指月山麓も海水が入り込んでいたという。湿地帯を埋め立て、城下町は整備されていく。参勤交代の際に藩主が往来した「御成[おなり]道」が町を貫き、碁盤目状の地割の中に武家屋敷や豪商の町家が整然と配置された。
城下は外堀によって区切られ、かつての城内三の丸にあたる堀内地区は、藩の重臣たちが屋敷を構えた。外堀に面して立つ「北の総門」(復元)近くには、永代家老 益田家の物見矢倉[ものみやぐら]が堅固な佇まいを残し、町筋に沿って続く長い土塀や長屋門が当時の格式を伝える。外堀の周囲に位置する平安古[ひやこ]や城下町地区は、中・下級武士や商人の屋敷が軒を連ねていた所だ。御成道に沿って藩の豪商だった江戸屋、伊勢屋、菊屋の商家が並び、脇道にはそれぞれの名が残る。とりわけ、菊屋横町は、一直線に伸びる小路に白壁の土蔵やなまこ壁が連なり情趣が漂う。この辺りは高杉晋作、木戸孝允らの旧宅も点在し、萩が明治維新胎動の地であることを思い起こさせる。
歴史的景観は、三角州の南端まで続く。川島地区には、1744(延享元)年に外堀に通じる水路として開削された藍場川沿いに旧家が残り、川の水を生活用水に利用した暮らしの情緒を今に伝える。萩は、町全体が史跡のようだ。「萩城下町」は、世界遺産「明治日本の産業革命遺産」※の一つに選ばれている。
※幕末から明治末までの日本の産業化の過程を示す8県11市にわたる23の資産で構成。萩市には、萩城下町(城跡・旧上級武家地・旧町人地)の他、松下村塾や萩反射炉など5つの資産がある。2015(平成27)年登録。