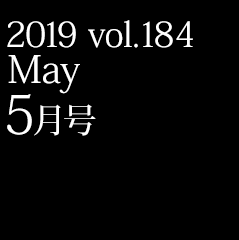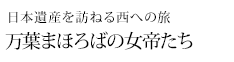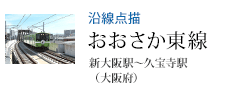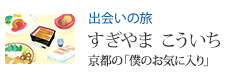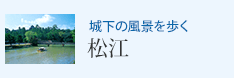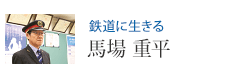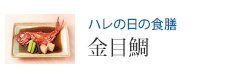城山の緑に守られてそびえ立つ漆黒の天守。
その本丸、二の丸を囲む堀川を、遊覧船が悠々と進む。
水の都と謳われる松江には、築城と同時に造られた美しい堀割や町並みが400年前の姿のままに残る。
藩政時代の面影を辿りながら、城下町を歩けば往時の息づかいを感じとることができる。

松江城には、JR松江駅よりレイクラインバス(7番のりば)より約10分の松江城(大手前)下車、徒歩約1分。


松江市街の中心部、標高28m余の亀田山に建つ国宝 松江城。外観は4重、内部5階、地下1階の構造を持ち、入り口に附櫓[つけやぐら]を設けた複合式の望楼型天守に分類される。360度の展望が広がる最上階に立てば、眼下に陽光に輝く宍道湖を望む。2015(平成27)年国宝指定。


城の北側の内堀沿いに、黒板塀と白壁の武家屋敷が並ぶ「塩見縄手」。縄手とは一筋に延びる道のことで、家老塩見小兵衛の邸宅があったことに由来する。

松江藩御殿女中が作り始めたと伝わる和紙てまり。出雲民芸和紙を材料に、県花の牡丹や市花の椿など四季の花があしらわれる。
松江城大手前広場には、「松江開府の祖」堀尾吉晴公の銅像が立つ。武勇の誉れ高い吉晴公は、1600(慶長5)年、関ヶ原の戦いの功績によって出雲・隠岐二十四万石を拝領し、はじめ月山富田城(安来市広瀬町)に入城する。しかし、領国支配に不便な山城であったため、息子忠氏とともに城地を選定し、水陸交通に優れたこの地を新たな居城とした。1611(慶長16)年の完成と同時に、中心部を武家町が取り巻き、外堀を隔てて町人町を配置するなど、城下町の基礎も築かれた。当時の町割の様相は、城の北側に沿う塩見縄手に色濃く残る。
大手門跡から本丸内へと進み天守をめざせば、途中、築城時に石垣に刻まれた堀尾家の分銅紋に出合う。往時を偲びながら二の丸上の段にあがると視界が開け、三の丸跡に建つ県庁が見える。ここには、近年復元された南櫓、中櫓、太鼓櫓が建ち並ぶ。三ノ門跡、二ノ門跡を経て一ノ門をくぐると、目の前に現れるのは黒々とした下見板張りの重厚な天守だ。松江城の特徴は、梯郭式に守りを固めた実戦的な構造にあるが、天守内も石打棚、石落とし、鉄砲狭間(銃眼)などが随所に見られ、井戸や食料庫が残るなど、籠城を意識して設計されたことが分かる。天守中央の入母屋破風[いりもやはふ]や寺院形式の華頭窓などが質実剛健な外観に華やぎを添え、その姿から別名千鳥城というそうだ。
堀尾家、京極家の後、松平家が10代にわたり城主を務めたが、明治の廃城令で櫓などは解体される。地元の豪農や旧藩士の尽力で天守だけは保存され、今も威風堂々と町を見守る。

名物「スズキの奉書焼き」をはじめ、「コイの糸造り」、「モロゲエビの唐揚げ」、「シジミ汁」など、郷土の味に仕立てられた七珍料理。7つの珍味は漁獲される時期が異なるため、1年を通してそれぞれの旬を楽しめる。

宍道湖東畔から嫁ヶ島の彼方に沈む夕日を望む。神々しいまでの夕景は、小泉八雲ら多くの文人墨客に愛された。
望楼式の天守最上階からは、眼下に広がる宍道湖の眺望に恵まれる。周囲47kmの広大な湖は、水都を代表する景観美とともに、魚介類の宝庫として古くから城下町の暮らしを彩ってきた。斐伊川をはじめとする淡水と日本海から中海を通って逆流する海水とが混じり合う汽水湖には、約100種類の多彩な魚類が生息する。早朝、穏やかな湖面に漕ぎ出し、昔ながらの漁具であるジョレンを操って行うシジミ漁の風景は、宍道湖の恵みの豊かさを物語る。
宍道湖七珍[しっちん]は、中でも特に珍重されている郷土の味覚をいう。スズキ、モロゲエビ、ウナギ、アマサギ(ワカサギ)、シラウオ、コイ、シジミ。地元では、それぞれの頭文字を並べ「スモウアシコシ」と覚えるそうだ。藩政時代、宍道湖の東側には藩直轄の漁場があり、四季折々、旬の魚介が献上されていた。かつて松江藩の特産品であったスズキは、松平不昧公好みの「奉書焼き」が伝承の味として受け継がれ、七珍料理を贅沢に飾る。