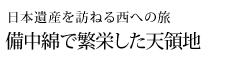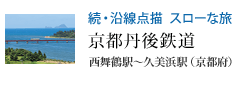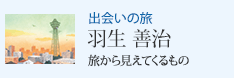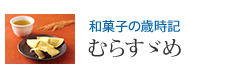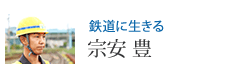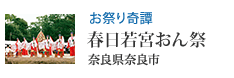1970年生まれ。埼玉県所沢市出身。二上達也九段門下。85年、プロ四段。史上3人目の中学生棋士。89年に初タイトルとなる竜王を獲得。94年、A級初参加で名人挑戦者となり、第52期名人戦で米長邦雄名人を破って初の名人に。竜王も奪還し、24歳で史上初の六冠王となった。将棋界の記録を次々と塗り替え、96年には谷川浩司王将を破って前人未到の七冠独占を達成し、社会現象になった。12年、通算のタイトル獲得数を81期とし、大山康晴十五世名人がもっていた80期の最多記録を更新。14年には4人目となる公式戦通算1300勝を史上最年少、最速、最高勝率で達成。同年には3度目の名人復位も果たしている。2017年12月、渡辺明竜王からタイトルを奪い、史上初の「永世七冠」を達成した。2018年2月には国民栄誉賞を受賞。
将棋を覚えたのは小学1年生の時です。同級生から駒の動かし方を教わったのをきっかけに、12歳でプロ棋士養成機関である「奨励会」に入り、プロになったのが15歳、中学3年生の12月です。自分でもよく分からないまま棋士になっていました。
そしてこの時以来、私の生活のサイクルに「移動」という時間が組み込まれたのです。中高生といえどもプロ棋士ですから、対局やイベントで、遠い近いに関わらず、毎週のようにどこか見知らぬ土地を訪ねることになりました。親の付き添いなどもちろんなく、移動はいつも一人です。
対局は強くなると多くなります。その上学校の授業のある平日でも対局が組まれます。例えば、関西で深夜まで対局に臨み、翌日始発の新幹線で学校に通ったことも珍しくなく、東京へ着いた時には全身へとへとで、教室では席に座っているだけでやっとというのも度々でした。
家出少年に間違われて駅で警察官に職務質問されたこともあります。その頃に、新幹線のなかで夢中に読んでいたのが沢木耕太郎さんの『深夜特急』。インドからイギリスまでザック一つで壮大な旅をしたノンフィクションです。
そして読むうちに、私のなかで「移動」は「旅」へと転化したのです。それは「旅から見えてくるもの」とでもいうのでしょうか、その場所に行き、その場所の空気に触れ、匂いを嗅いでこそ見えてくるもの。
「百聞は一見にしかず」。高校生だった私はこの旅の面白さ、醍醐味を『深夜特急』から学んだといえるかもしれません。いまも、1年のおよそ3分の1を対局やイベントのために遠征し、家を離れる生活を20年以上も続けていますが、そんな生活を苦に感じたことは一度もありません。
むしろ遠征は、プロ棋士になって良かったと思うことの一つです。全国のいろんな場所、観光地にとどまらず、普段あまり行かないようなところにも旅することができる。これまでに、日本全国47都道府県すべて訪ね、数えきれないほどの都市や町それぞれに楽しい旅の記憶を留めています。
西日本でいえば、やはり一番馴染み深いのは大阪です。中高生の頃から毎月毎月、もうどれほど通ったでしょうか。現在でも毎年2、3回は対局で訪れます。というのも、将棋会館は東京と大阪の2カ所にあって「関西将棋会館」は棋士にとって大切な場所です。
大阪駅から環状線の内回りに乗って一つ目の福島駅の近くにあります。30数年前の将棋会館周辺は喫茶店が一軒あるだけの寂しいところでしたが、最近はオシャレな町に大変身して、その隔世に驚かされています。もっとも中高生の頃は一人ではずいぶん不安でした。
しかし対局で通ううちに、一人で町を散策するようになったのです。対局の前後に時間があったり、宿泊する時には、必ず目的もなくぶらぶらと町を歩いたものです。映画『王将』の舞台でもある将棋の聖地、通天閣下のジャンジャン横丁の狭い路地にある将棋センターで将棋を指す人びとの姿に、坂田三吉さんがダブって見えた覚えがあります。
鶴橋の焼き肉の美味しさ、居酒屋や立ち飲み屋が密集した、まるでカオスのような京橋。よく歩いたのは天神橋筋商店街です。1丁目から7丁目まであって、商店街の長さは日本一だそうです。とにかくいつ訪ねても活気に溢れて逞しい。
人と商店街が渾然一体となった賑やかさは、他に例を見ないくらいです。店の人は、私を知ってか知らないかはともかく、誰もが親し気に声をかけ、気さくです。天神橋筋商店街に限らず、大阪ではどの町も同じように開放的でフレンドリーで、町を散策し、見聞するほどに大阪の個性が見えてくるのでした。私の妻は大阪の出身なので、一層親近感が湧くのでしょうか。
ともかく、これこそが『深夜特急』で教えられた「旅から見えてくるもの」なのです。大阪に限らず、そうして私は対局前には、対局先の町をできるだけ散策するように心がけています。対局の場では究極的な集中力が求められます。だからこそ、頭の中を空白にしておくことが大切なのです。
また対局後も、気分転換、リフレッシュのために未知の町を無心に探索します。目的も定めず、ガイドブックにも頼らず、身体の赴くままにただぶらぶら歩くのです。どんな発見、どんな出会いがあるかも分からない、まさにそこが「旅から見えてくるもの」の面白さなのではないでしょうか。そして、将棋の一回一回の対局も未知の旅に似ています。
対局は一回ごとに、未知の旅に出て、知らない何かを捜しに出発する。そんなイメージを抱いて対局に臨んでいます。「棋士は先が何十手も読める」と思われていますが、私はそんなに先は見えていないし、読めません。しかし先が見えないから面白いのです。旅もまた同じではないでしょうか。