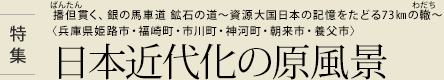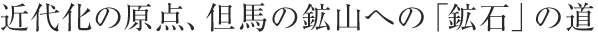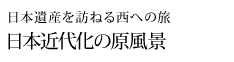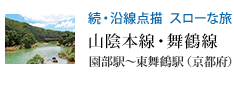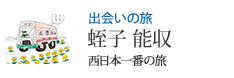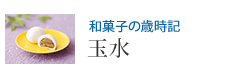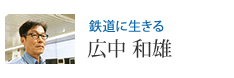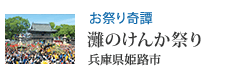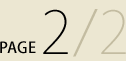

生野銀山は江戸時代には幕府の天領として代官所が置かれた。採掘された銀は日本の代表的な輸出品になった。生野銀山で造られる灰吹銀(鉛に溶け込ませて抽出された銀)の銀含有は99%と高品位だった。

灰吹銀

史跡 生野銀山入り口の門柱には、官営の象徴として菊の御紋が入っている。当時の工場正門から移設されたものだ。

1885(明治18)年に生野鉱山と神子畑鉱山とを結ぶ馬車道に架けられた、神子畑鋳鉄橋(みこばたちゅうてつきょう)。日本に現存する鉄橋としては3番目に古いとされ、美しい洋式橋の姿を今に残す。
生野峠を越えた銀の馬車道は、生野の町中を通って旧生野鉱山本部で終点を迎える。しかし、鉱石を搬出する本来からすると、銀の馬車道のスタート地点だといえる。生野は標高約300mの盆地で現在の人口は約4,000人。が、1万人以上の人々が暮らし日本の経済発展をリードした輝かしい時代がある。
鉱山の開坑は807(大同2)年と伝わるが、本格的に採掘が始まったのは戦国時代。江戸時代には鉱山が幕府の財政を支えた。徳川三代将軍、家光の頃には月産150貫(562kg)を産出。そして時代は明治に移り、明治新政府は官営鉱山の第1号として、フランス人技師のジャン=フランソワ・コワニェを技師長に招き、西洋の先進技術で鉱山の近代化を進めた。
鉱山の専門技師や、大型機械や火薬による採掘、トロッコを用いた大規模坑道に関わる外国人技術者たち、他にも多種の専門家が集められた。そして鉱山技師を育てる鉱山学校も創られた。明治政府はなけなしの財布で、高額の外国人を雇い、日本人は最先端の技術とノウハウを学んでいった。ノミで手掘りする日本では、地下200m以上の採掘ができなかったという。
そして学んだ技術やノウハウはその後日本全国に広められた。育った人材は日本の近代化の担い手になった。その一つの原点が生野鉱山だ。


山の斜面にコンクリートで築かれた神子畑選鉱場跡。15世紀から銀や銅が採掘されていたが、1917(大正6)年に閉山後は明延鉱山で採掘した鉱石の選鉱場となった。高さ75m、横110mの選鉱場は東洋一の規模を誇った。下の写真は最盛期の稼働風景。

約6km離れた明延鉱山と神子畑選鉱場を結んだトロッコ電車「一円電車」。鉱石運搬に加え、1945(昭和20)年からは客車も定期運行され、地域の交通手段としても利用された。
生野からさらに北の鉱山群へと至る道が「鉱石の道」だ。距離は約24km。但馬へと向かう里山と田園の風景は、どこものどかで美しい。清流に沿った道を山中へと進むと、山の斜面に要塞のような巨大な施設が突然現れた。圧倒的な迫力の構造物は東洋一と謳われた神子畑選鉱場跡[みこばたせんこうじょうあと]だ。もとは鉱山だったが、明治時代の閉山後は、山一つ向こうの明延鉱山の鉱石を選別する選鉱場として近年まで稼働した。
明延鉱山は坑道の総延長が550kmもある大鉱山だ。東洋一の錫[すず]鉱山として知られたが、金や銀、銅にタングステンなど多種の非鉄金属の鉱脈がある。1987(昭和62)年に閉山したが鉱山町は現在もあり、人口約70人。「NPO法人一円電車あけのべ」の理事長、明延生まれの藤尾賢介さんは、役所を退官して探検坑道のボランティアガイドも務めている。
見学はヘルメット着用、足下は長靴。坑道に入った瞬間、冷凍庫のような冷気が身体を包んだ。「この坑道は操業当時のままです。重機械も当時のまま。あえて操業時の状態を見ていただいています。リアルでしょ。まさに近代化の遺産です」と藤尾さん。「一円電車」とは、明延鉱山と神子畑選鉱場間を走ったトロッコ電車だ。

東洋一の錫鉱山と謳われた明延鉱山。坑道の総延長は約550km、深さは地下約1,000m。現在でも日本一の埋蔵量といわれる錫鉱脈があるという。
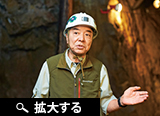
「NPO法人一円電車あけのべ」の藤尾さん。「日本の近代化を牽引した鉱山の歴史は今も私たちの誇りです」と語る。

錫鉱石
直線距離で約6km。電車が通じる前は峠道を這うように牛馬で鉱石を運んでいたようだが、1929(昭和4)年に5本の隧道[ずいどう]を通して「明神[めいしん]電車」として開通。最初は鉱石を運び、後には職員や住人の足として親しまれた。乗車賃が一円なので一円電車。日本遺産の鉱石の道は、ここ明延鉱山からさらに北の山中にある中瀬鉱山にまで至っている。
中瀬鉱山は佐渡金山にも劣らない金山で美麗な自然金を産出した。この長い旅の終わりに改めて銀の馬車道から鉱石の道の道程を見渡せば、鉱山の近代化のみならず、採掘から選鉱、物流まで一貫した長大なシステム全体が浮かび上がってきた。革新的なこの動脈こそが近代化そのもので、現在の技術立国日本に脈々と受け継がれているものではないだろうか。
そんなことを考えながら鉱石の道を辿ってきた。その道すがら、目に映る緑豊かな山々がみな宝の山に見えてきた。実際、山にはお宝がまだまだ眠っているという。