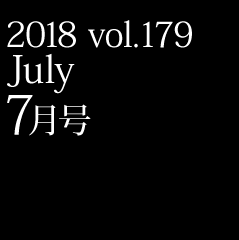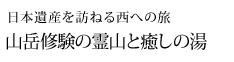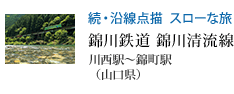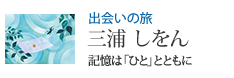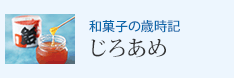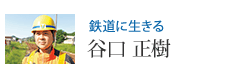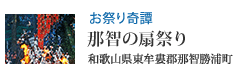加賀地方の古い方言で、やわらかいを意味する「じろい」、「じるい」がその名の由来という「じろあめ」。米と大麦だけで甘さを醸し出した昔ながらの水飴は、菓子としてはもちろん、飴炊きや佃煮などの料理や離乳食、夏バテ防止の滋養食品としても重宝されている。江戸時代より食べ継がれる「あめ」の歴史を辿ってみた。


「あめ」という言葉の語源は、「あま味」「あま水」など、「甘い」という言葉がもととされる。今日、甘い食品の代表といえば砂糖だが、これは奈良時代に薬として伝わり、長く貴重品として扱われていた。甘味料として広く庶民にまで普及したのは明治の頃と考えられる。一方で、古くから人々の身近にあった甘味料が、現在ではお菓子として親しまれている飴であった。
本来、飴とは、穀物や芋類など植物のでんぷんを酵素で糖化させたもので、今でいう水飴にあたる。その製法は、農耕文化とともに中国から伝来。8世紀初めに編まれた『日本書紀』に、すでに「飴」は登場し、また平安時代の延喜年間(901〜923年)に成立した漢和薬名辞書『本草和名[ほんぞうわみょう]』には、和名を「阿米」とした記述が残る。このように、飴と日本人との関わりの歴史は古く、甘い味覚が貴重であった頃は、甘味料にとどまらず、薬や神仏への供え物として扱われていたようだ。
飴づくりには、当初は米など穀物のでんぷんを糖化するのに、米を発芽させた「米もやし」が使われた。その後、より強い酵素を持つ大麦(麦もやし)を用いるようになったと伝えられる。米のでんぷん質は、大麦の実に含まれる糖化酵素(アミラーゼ)の働きによって麦芽糖に変わり、甘みのある液体がとれる。これを煮詰めてとろりとした粘り気のある液状に練り上げるのだ。植物の化学反応から生まれた自然の甘味は、麦芽独特の明るい褐色と米のやさしい風味を併せ持っている。

穀物を原料に作られる飴は、糖質のほかミネラルやたんぱく質を含み、糖の吸収が穏やかなため身体にもやさしいという。

その日の気温や麦の状態によって、糖化の進行具合は微妙に変化する。丸4日かかるという製造工程全てを熟練の技が支える。

水分を抜いて固形状にした「おこしあめ」。じっくり練り込んだ飴の持ち味は、甘露煮や佃煮などの料理にも発揮される。
金沢市の城北、浅野川近くの路地に佇む「飴の俵屋」。1830(天保元)年の創業以来、穀物から甘味を得た先人の知恵を連綿と受け継ぐ飴の老舗だ。藩政末期頃の建築とされる店の建物は、1985(昭和60)年に市の指定保存建造物となり、往時の商家の姿をしのばせている。
俵屋は、もとは米穀商であったが、凶作や飢饉で食べ物が不足していた当時、乳飲み子を抱えながら母乳が出ずに困っている母親たちを見かねた初代次右衛門が、母乳に代わる栄養価の高い食べ物として作り上げたのが「じろあめ」の始まりという。時代とともに道具や燃料は変わったが、俵屋では現在も創業時と同じ原料と製法を守る。厳選された国産米と大麦、大自然を源とする良質の水を原料に、米を蒸して麦芽と混ぜ合わせ、温湯とともに糖化を促す。米と麦芽の配合割合をはじめ、米の蒸し時間や糖化の際の保温管理、また糖化の進み具合の見極めにも秘伝があるのだという。季節ごとに仕上がりの堅さを調整する練りの作業にも、一家相伝の技が息づく。
「じろあめ」、さらに煮詰めて水分を抜いた固形状の「おこしあめ」は、地元では料理の味付けにも使われる。砂糖が手に入りにくかった頃からの庶民の知恵。中でも魚との相性がよく、臭みをとったり、コクや照りが増すという。「じろあめ」を好みの甘さに湯で溶いて冷やし、生姜を効かせた「冷やしあめ」は、夏バテ解消の飲み物だ。ほのかな甘さがどこか懐かしい素朴な飴は、金沢の食文化の中で存在感を示している。