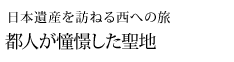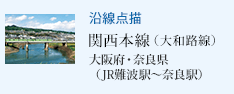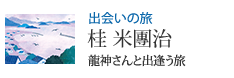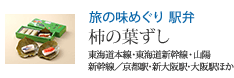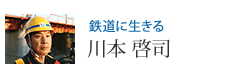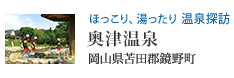関西本線のJR難波駅から奈良駅まで41km。
“大和路線”に乗って、
信貴・生駒の山を車窓に眺めつつ
青垣の山々が連なるまほろばの奈良を目指した。

大型商業施設「OCAT」の地下にあるJR難波駅の改札前。JR難波駅は1994(平成6)年の関西国際空港開港と同日に湊町駅から改称された。

天王寺駅前に広がる天王寺公園エントランスエリア。通称“てんしば”には、おしゃれなフラワーショップやカフェなどの店が並ぶ。

1964(昭和39)年に開設された大阪市中央卸売市場東部市場は大阪市南部の拠点として取引されている。市場で仕入れた鮮度のよい海鮮を提供する食堂も併設されている。

“大和路線”は関西本線のJR難波駅から京都府下の加茂駅までの区間を走る愛称で、アーバンネットワークの一つ。起点であるJR難波駅はJR西日本で初の地下駅で、駅名に「JR」を冠した初めての駅でもある。なお「大和路快速」はJR難波駅発ではなく、大阪駅から大阪環状線を走り、大和路線に乗り入れて奈良方面に向かう。
列車はしばらく地下を走り、すぐに高架線を進む。ほどなく大阪環状線を走り、車窓には大阪のシンボル通天閣が見える。そして大阪の南のターミナル、天王寺駅。大阪環状線のほか奈良、和歌山方面の列車が発着する巨大な駅。駅周辺は再開発が進み、天王寺公園もおしゃれにリニューアルされ、芝生広場は大勢の家族連れで賑わっている。
高架線を走り続ける。すぐに東部市場前[とうぶしじょうまえ]駅だ。大阪市に3つある中央卸売市場の一つ「大阪市中央卸売市場東部市場」の最寄り駅で、最近は市場内の食堂の新鮮な魚介メニューが評判の人気スポット。ただし朝が早い卸売市場だから昼には閉まる店もあるので、その点は要注意。

平野には創業300年を超える老舗和菓子屋や小さな博物館が点在している。写真下右は近くにある全興寺の地獄堂。写真下左は全興寺境内にある「駄菓子屋さん博物館」。



大和川に沿って走る列車。標高273.6m、明神山から大和路線を望む。

王寺駅に広がる大留置線。王寺駅は和歌山線の起点ともなるターミナル駅だ。
次は平野駅だ。この町の歴史は平安時代まで遡る。征夷大将軍・坂上田村麻呂の次男、広野麻呂の所領地で「広野」が転じて平野になったという。戦国時代は摂津、河内、和泉の中継地点で町は二重の濠と土居で守られ、堺と並ぶ町民が自治・自衛する自由都市として知られた。そんな平野の町の現在のキャッチフレーズは「平野町ぐるみ博物館」。江戸由来の商家や町家が多く、町内には「駄菓子屋さん博物館」や「かたな博物館」などの小博物館がいろいろあって、町全体がまさに歴史博物館。楽しい町の散策をほどほどにして先を急いだ。
久宝寺駅は大和路快速も停車する主要駅で、大阪の東部を南北に結ぶおおさか東線と連絡している。そして列車はやがて大阪、奈良の境の山峡を大和川に沿って走る。
それまでの住宅街の風景は一転。大和川は生駒・信貴の山並みと葛城・金剛の山並みを分つように流れ、ちょっとした深山幽谷の気配だ。山峡を抜けて視界が明るく開け、大和川の鉄橋を渡って大きくカーブすると、列車は王寺駅に到着だ。

斑鳩の里の夕暮れ。法隆寺は世界最古の木造建築物で、ユネスコの世界文化遺産に日本で初めて登録された。

郡山城跡の天守台からの眺望。大和郡山の城下とともに、遠くには平城京大極殿や薬師寺、若草山まで望める。

城下町郡山の町並み。紺屋町は藍染めの職人が集った職人町で、東西209mの通りには150軒近い家があったとされている。
王寺駅は、奈良県内で初めて鉄道が開通した1890(明治23)年に開業した。現在は大和路線のほか和歌山線も乗り入れている。奈良県内有数のターミナル駅であり、私鉄とも連絡する駅は県内屈指の乗降客数を数え、車両基地もある“鉄道の町”だ。
王寺駅を離れた列車は大和川に沿って走る。風景はどこまでも穏やかだ。周囲はことごとく青垣の山々で、奈良盆地は広々としている。車窓に、条里制の名残である田畑が続く。聖徳太子ゆかりの斑鳩[いかるが]の里の風景だ。車窓からわずかに法隆寺の塔が見える。法隆寺駅はまもなくだ。
法隆寺駅で途中下車し、法隆寺や中宮寺、法輪寺、法起寺を巡るのが人気の散策路で、駅にはリュックを背負った外国からの観光客も少なくない。とりわけ、斑鳩の里の夕景は美しい。シルエットとなった五重塔の風景は、はるかいにしえのままの風景のように思える。

自動販売機で金魚が売られている。大和郡山ならではの風景だ。値段は金魚1袋200円。

郡山金魚資料館代表の嶋田さんは、「金魚のサイズは大きすぎても、小さすぎてもいけません。そのため、管理にはとても気を配っています」と話す。館内には約40種の金魚が展示されている。

大和小泉駅を過ぎて郡山駅へ。郡山は豊臣秀吉の弟、秀長が治めた後、江戸中期には柳澤家が治めた城下町。城下町らしい古い家並みが残り、「紺屋町」や「材木町」など藩政時代の町名が今も多く残る。そしてやはり大和郡山といえば金魚で、養殖する池やプールが無数に点在する。そもそもは藩主の柳澤吉里が金魚の養殖を伝え奨励したという。

塔のような旧2代目奈良駅駅舎は、1934(昭和9)年に建てられた。現在は総合観光案内所として利用されている。隣接するのがニューアルされた現在の奈良駅。
町内には金魚が泳ぐ風変わりな電話ボックスがあったり、金魚の自動販売機もある。金魚は町おこしに欠かせない大和郡山のキャラクターだ。郡山では年間約6,000万匹の金魚が生産される。「郡山金魚資料館」の嶋田輝也さんはこう話す。「最盛期には150軒。現在は約30軒。郡山は金魚すくい用が主でしたが、今は観賞用にも力を入れています」。
郡山駅を出て高架線を走る列車の車窓に、若草山が見えてくると終着の奈良駅だ。高架駅に改装された現在の駅舎は3代目。駅前の風景は日に日に姿を変えているが、車窓に映る青垣の山々は古代より変わらずに美しい姿のままなのだろう。

奈良公園にある周囲360mの猿沢池。池面には興福寺五重塔が映る。
奈良駅から三条通りの上り坂を進むと猿沢池がある。見上げると興福寺の五重塔。この猿沢池の南の界隈が通称「ならまち」だが実際の町名にはない。元興寺の旧境内の跡地を中心に江戸末期から大正にかけての町家が並ぶ一帯が「奈良町都市景観形成地区」として一般的に「ならまち」と呼ばれている。

“ならまち”の民家の軒先に下がる庚申信仰の「身代わり申」。申の背中に願い事を書いて吊るす「願い申」ともいう。
平城京の下京として整備され、町の歴史は元興寺や興福寺の門前町として始まる。古い町家が密集し迷路のように路地が交錯する。そんな町の佇まいを活かしてまちづくりが進み、現在ではカフェや雑貨店が並び、寺社仏閣とは別の奈良の人気の観光スポットだ。「奈良町資料館」の館長の南哲朗さんはこう話す。

奈良町で貴重な資料や民具、絵看板を無料で公開展示している「奈良町資料館」。館長の南さんは、「私が幼い頃はならまちで外国人を見ることも珍しかった。ところが、平城遷都1300年祭以降、かなり増えました」と話す。
「戦渦を免れた元興寺の極楽堂は世界遺産です。第一級の仏像も周囲の寺院に点在していて、この資料館の裏には五重塔の礎石があります。歴史的に貴重なところなんです。現在のおしゃれなならまちを散歩しながら、同時に世界的な遺産の学習をしてほしいですね」。奥深い歴史、生活風景、そして現代感覚とが共存する、それがならまちの魅力だ。