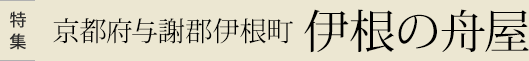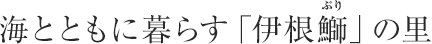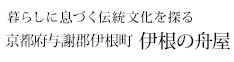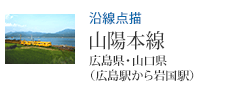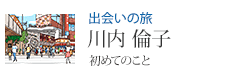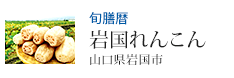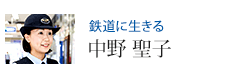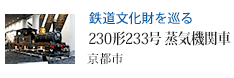伊根湾の東側、伊根浦の一番奥にあたる立石地区の舟屋群。山と海を繋ぐように隙間なく建ち並ぶ景観はこの地でしか見ることができない。
伊根湾を一望する展望台がある。そこから見下ろす湾は蹄鉄[ていてつ]のような形をしていて、湾の入り口を青島が塞いでいる。湾内はとても平穏で、光によってコバルトブルーにもエメラルドグリーンにも色を変える海の上を、観光船が白い航跡を引いて、幾何学模様に見える養殖生け簀[いけす]の傍らを静かに進んでいく。
思わずカメラを向けたくなる風景だ。湾を囲む山々は鋭く海に落ち込み、海岸線を縁取るように帯状に舟屋が隙間なく連なっている。町並み全体が、漁村として全国で初めて選定された「重要伝統的建造物群保存地区」で、この独特の佇まいは江戸時代以来の、伊根ならではの光景だ。
伊根は、平安時代に「伊禰庄[いねのしょう]」として記されるほど歴史は古い。鎌倉時代には小さな集落が形成されていたようだが、その名が広く知れ渡るのは江戸時代だ。富山県の氷見や五島列島の三井楽と並んで伊根は日本三大鰤漁場として知られ「伊根鰤」や「丹後鰤」は諸国に名を馳せた。独特の舟屋群の景観もその頃に成立したとされる。

数少ない江戸時代の舟屋。太い立派な梁が印象的で、1階は海側に緩く傾斜し、舟を出し入れしやすいように海水を中まで引き込んでいる。
そんな舟屋を海から眺めてみた。「よう来なったなあ」。桟橋で出迎えてくれた海上タクシーの船長さんは穏やかな海に船を進めながら説明してくれた。「伊根湾は南向きの湾で、青島は天然の防波堤になっとるさかいに、外海が荒れても湾内はさざ波程度やあ」。そう言って船長は船をゆっくりと舟屋に近づけた。
海にせり出して建てられた舟屋は高床式の海上住居のようだ。1階は海側に傾斜していて海水を取り込み、そこに小舟が収納されている。つまり、海と一体化した舟のガレージ。2階部分は「昔は漁具などの物置場やったけど、今は居室にしとるとこが多いなあ」と船長は話す。こうした舟屋が可能なのは、波の影響を受けにくく潮の干満差が約50cmと、年間を通じて水位が安定している伊根湾だからこそという。

舟屋はどれも海に対して神社建築のような「妻入り」だ。左端が江戸時代の舟屋で、正面の梁は低く、柱は「ハ」の字状の構造をしている。中央は昭和、右は大正時代の舟屋。

鰤漁は伊根を代表し、集落に何度も豊かさをもたらした。今でも冬の伊根鰤は全国的に知られるブランドだ。
周囲約5kmの湾をぐるりと舟屋が取り囲んでいる。舟屋が約230軒、母屋約330軒、約130棟の土蔵が町並みをつくっている。昭和初期まで車道はなく、江戸時代の地割のまま母屋と舟屋を一つの敷地として短冊状に湾を囲んでいた。行き来は舟だけで、舟屋が各家の玄関口だった。今でも対岸へはバスより「舟の方が便利で早い」そうだ。
まさに海と一体化した伊根の暮らしを支えてきたのが、伊根の豊饒の海だ。とりわけ鰤漁は莫大な富をもたらした。昭和に入ってからも大敷網(定置網)漁で「一網2万本以上」を水揚げし、何度も鰤景気で沸いた。「鰤1本、米1俵」といわれた。その頃の伊根の民謡『伊根の投げ節』はこう唄っている。「伊根はよいとこ後ろは山で、前で鰤とる鯨とる。千両万両の金もとる」。

舟屋の隣りには土蔵が残る。壁に「鏝絵(こてえ)」が施された蔵が多く、写真の図柄は大黒。鰤漁で沸いた町の豊かさを物語っている。
そして、1950(昭和25)年前後の数年の鰤景気では舟屋を変えた。茅葺き屋根に板を敷いただけの簡素な舟屋は一斉に瓦屋根の立派な舟屋に建て替えられた。土蔵が多く残っているのも鰤の恩恵なのだろう。
伊根の家並みでひと際大きな構えを見せているのが「向井酒造」の酒蔵だ。創業は1754(宝暦4)年。江戸時代からずっと伊根の繁栄を見続けてきた証人で、その酒は漁師たちが毎夜嗜んだ郷土の酒。波打ち際に酒蔵があるというのは全国でも珍しく、いかにも伊根らしい。
この時期、伊根の宿の夕餉[ゆうげ]の食卓にのぼるのはグジ(アマダイ)やケンサキイカなど。造り、塩焼き、煮付けと盛りだくさんに並ぶ。そして晩酌には向井酒造の旨口。伊根ならではの贅沢だ。


江戸時代から続く「向井酒造」。伊根浦の漁師さんらが愛飲してきた郷土の銘酒だ。写真は14代当主で杜氏でもある向井崇仁さん(32歳)。「これからも呑んで飽きない酒づくりを続けます」と話す。姉の久仁子さんは女性杜氏として知られる。