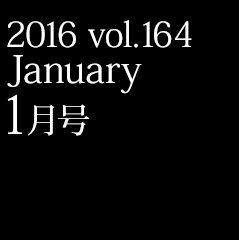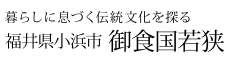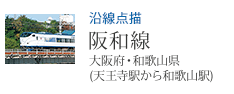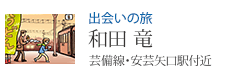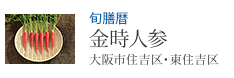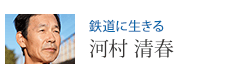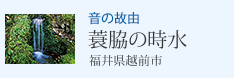![]()

福井県のほぼ中央、日野川が流れる武生盆地に位置する越前市は、古代には越前国府が置かれ行政・文化の中心地であり、平安時代には紫式部も1年余り暮らした。北陸本線武生駅から東にある味真野[あじまの]地区は継体天皇(第26代)ゆかりの地である。
その味真野から山間部に入った蓑脇町にある大平山[たいへいざん]の中腹、標高約300mの谷間に、昔から流れが急変する不思議な湧水として知られる「蓑脇の時水」がある。その昔、蓑脇の山仕事をする人たちにとって「滝の音を3回聞くとお昼」と語り継がれ、いつの頃からか「時水」と呼ばれるようになった。
その正体は、ある時間ごとにあっという間に水が湧き出し、次第に減っていく間歇冷泉[かんけつれいせん]だ。その回数は1日に約8回から25回ほどで、1回の湧水量は約4,000ℓ、湧き出す周期や水量は季節や降雨によって左右されるという。地下内部に空洞があり、そこに地下水が流れ込んで一定量に達するとサイフォン原理によって一気に噴き上がると考えられている。
この現象は全国でも数例しか確認されておらず、極めて稀な自然現象だ。今では地元の有志によって「時水」までの遊歩道が整備され、案内板を設置したり草刈りなどをしたりして、その環境が守られている。
※一部の端末ではご利用になれない場合があります。ご了承ください。