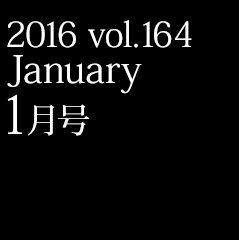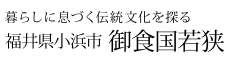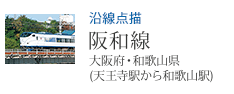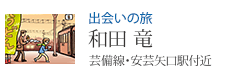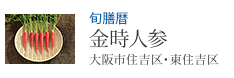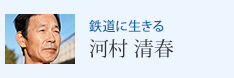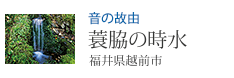「変状の確認は、医者の触診と同じ」という河村。鉄桁の接合部材が緩んでいないかどうかは、ハンマーによる打音の違いを聞き分けるとともに、手袋をはずし、素手で確認する。

京都土木技術センターで取り組む「技術継承ワーキング」では、さまざまな検査機器の扱い方について定期的に学ぶ。
京都を中心に、滋賀・大阪の一部を含めた広範囲にわたる土木建造物の保守管理を受け持つ京都土木技術センター。国鉄時代に入社して以来、30年以上土木業務に携わってきたという河村は今、シニアリーダーとしてセンターの若手社員の指導にあたる。シニアリーダーとは、定年退職後の再雇用制度により、これまでの経験や技術力を生かして活躍する社員のことだ。
河村は、昨年7月に定年を迎えたが、引き続き管内の橋りょうやトンネルなどの検査業務を行いながら、長年培ってきた技術の継承に尽力している。河村は「技術・技能は、一旦途絶えてしまうと、もとのレベルに回復するのは容易ではありません。国鉄時代から脈々と受け継がれてきた技術を、少しでも若い世代に伝えていきたい」と語る。
河村が技術継承への思いを強くしたのは、かつてある現場の実情に接し、危機感を覚えたからという。橋りょうの河川調査の現場に、増水すれば危険な河床の状況を測定できる若手社員が育っていなかったのだ。「橋りょうは、河川の上に架かる構造物。列車の安全な運行のために、検査の基本を徹底する必要を感じたのです」。そこで、河村は技術主任として、現場をともにする若手たちに検査の着眼点をはじめ、なぜ変状が発生したのか、その原因について解説するなど、指導者としての役割に徹してきた。

頭上を列車が通過する橋りょう下の現場。ゴミを取り除き草を刈って風通しを良くし、錆を防ぐことが、構造物の保守管理の基本。
現在、河村は「技術力向上の取り組み」というプログラムで教育を担当する。京都はもとより、大阪と神戸、3つの土木技術センターから各1名、計3名の若手社員が参加するこのプログラムでは、現場実践方式により、土木構造物の検査の「基本」を1年間徹底して教え込む。月4回のプログラムのうち、3回は通常の検査業務に同行し、現場で実際の変状を見ながら、発生の原因をはじめ、一番重要な列車通過時の着眼点などを指導していく。「検査では、例えば小さなき裂であっても、構造物のどの部位で発生しているかを把握することが大切です。その一部だけでなく、周辺全体から変状を見極めることが、適切なメンテナンスに繋がります」。
検査の現場は、木や草が生い茂る場所も少なくない。こうした現場に赴くと、河村は率先して草木を刈る。風通しを良くし、錆を防ぐことの重要性を身をもって示すのだ。雨の日の検査では、水が溜まっている箇所はないかを調べ、ゴミを取り除いて水を抜く。「清掃は検査の基本。私が現場で教えているのは、忘れがちになる基本の大切さです」と話す。

研修生の検査記録簿、感想文に目を通すのは、日常業務が終わってから。質問には絵を示して回答したり、検査のポイントを記した資料も添付しておく。
河村はまた、プログラムに参加する3名の研修生に、現場ごとに各自が作成した検査記録簿と感想文を提出するよう義務づけている。実地で教えたことを各研修生がどう学びとったかをチェックするのだ。「書くと覚える。研修生からの質問を受ける機会にもなっています」。毎回、添削してコメントを添えたり、質問に回答するのは大変な作業だが、自身も新人の頃、検査や修繕の報告書を繰り返し作成することで、基礎が身に付いたのだという。研修生の1人は、「学んだことの振り返りと整理ができる」と話し、記録簿や感想文の意義と河村の思いを受け止める。
「日々、安全に列車を通過させていくのが私たちの使命」という河村。一つの現場が終わると、安堵感はあっても達成感はない。“安全は当たり前”だからだ。そんな地道な業務の中で、心に残っているのは、21年前の阪神・淡路大震災の直後、芦屋駅構内から住吉駅構内までの被害調査を担当した時のことだ。あまりにも大規模な被災現場の状況に呆然としたが、JR西日本社員とJRグループの技術力を結集することによって、早期の復旧を成し遂げることができた。この貴重な経験も含めて、若手社員に基本の大切さを日々、検査の現場で着実に根づかせている。