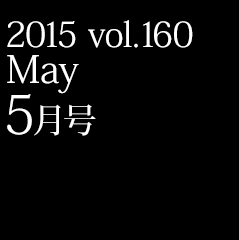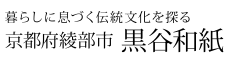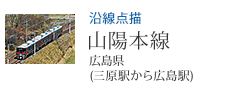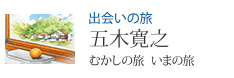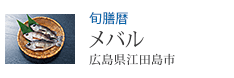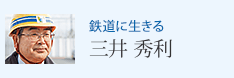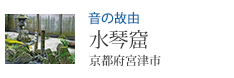2018(平成30)年の完成を目指して工事が進む「西吹田アンダーパス新設工事現場」。地下13メートルで安全、確実に工事が進むよう現場を視察。

三井を中心に助役や係長とのミーティング。こうした日々のコミュニケーションによって、問題点の早期把握・解決を図るとともに、より良い職場環境を作り上げている。
北陸新幹線の開通で賑わう北陸における「金沢駅付近の高架化工事」をはじめ、JR神戸線の「さくら夙川駅新設工事」、「阪神・淡路大震災の復旧工事」、そして現在「西吹田アンダーパス新設工事」を進めるなど、入社以来40年にわたって鉄道工事一筋に歩んできたという三井。
現在は現場長として、工事プロジェクトの円滑な推進を行っていくために、工事所の総合的なマネジメントや安全管理を徹底するほか、若手社員を指導している。
三井が手がける主なマネジメントは、工事の安全管理、工程管理、予算管理、そして品質管理である。これらに加えて、自治体との協議調整、地元協議調整、職場環境づくり、若手社員の育成も行っている。
「工事プロジェクトを進めていくうえで、マネジメントは必要です。そして、マネジメントを行ううえで一番重要視しているのは、問題点の早期把握と解決です。問題点を早く掴むことができるほど、早い段階で対処でき、工事が進んでから大きな問題にしなくて済みます」。では、そのためにどうするか?三井は普段から工事所の助役や係長とのミーティングを密に行い、また、若手社員たちにも自ら声を掛けている。こういった日々のコミュニケーションで風通しの良い職場環境を作り上げることで、部下から「報・連・相」が滞りなく行われるようにしているのだ。

阪神・淡路大震災で、復旧工事期間中と完成の時にマンションに取り付けられた横断幕。今でも工事に従事する三井の原点になっている。
工事を行うためには自治体や地元と協議を行う必要がある。この協議を円満に進めるためには、誠意を持って対話することが求められる。三井はその重要性をかつて自身が手がけたある工事で思い知らされたという。それは「さくら夙川駅」の新設工事である。
当初、駅の新設は地元の方に歓迎されると思っていたが、意外にも反対する人が多く、工事着手までに説明会が毎週のように重ねられ、地元との協議は工事が完了するまで約4年間も続いた。
「とにかく地元の方の話に耳を傾けて、一つひとつの問題にきちんと対応することで、最初は反対されていた人も理解を示してくださるようになり、より良い駅を造るにはどうすればよいか、一緒に考えていただけるようになりました。相手の立場に立って物事を考える、丁寧に対応する、そうすれば状況は変わる。コミュニケーションが大切だということをあらためて教えられました。今でも協議に参加した人と、親睦会のように年に数回の交流をさせていただいています」。
もちろんコミュニケーションの根底には、絶対に駅を造らなければならないという使命感、工期と予算は守るというリーダーの確固たる意志があったことは言うまでもない。
阪神・淡路大震災の復旧工事(JR神戸線六甲道駅付近)では、付近のマンションに『おけがのないように』、復旧時には『ありがとう』の横断幕が貼り出されて感動したという三井。「鉄道はみんなの足であり、物流の足です。お客様のための鉄道であることを工事関係者は忘れてはならないのです」。

約77メートルの線路下トンネル設置工事で、各所に変位がないか、進捗に遅れはないかなど慎重な管理が行われている。
工事が始まれば騒音や振動、交通規制で住民の方にご迷惑をかけることになるので、誠意を持って対応するよう所員に徹底していると三井は言う。また、工事が終了してからは、保守が極力少なく済むよう、設計から施工、品質管理までを考えるよう気を配っている。工事は技術こそが品質の要になるが、今、大阪工事所では若手社員の技術力向上を一番の命題として取り組んでいる。
「技術を身に付けるには現場に足を運んで学ぶことが一番です。現場には無数の技術が落ちている。一つでも多くの技術を拾ってきてほしい」。そのための工夫として、若手社員に現場の品質チェックや安全パトロール、安全協議会、他現場への見学などへ参加させている。
「地図に残る仕事の醍醐味、楽しさを後輩に伝えていくことも私の使命です。デジタル時代にアナログも良いところがいっぱいあるんだよと伝えていきたい。昔の良いところを取り入れて、現代にマッチする仕事の仕方をぜひ考えてもらいたいですね」。
現場一筋、これまで多くの人と向き合い続けてきたマネジメントのエキスパートはそう言って笑った。