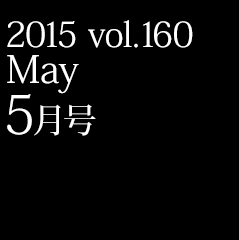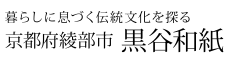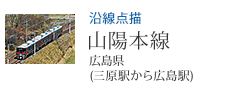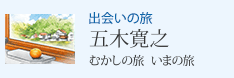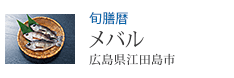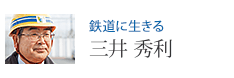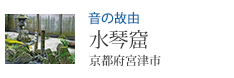- 1932年福岡県生まれ。作家。戦後朝鮮半島から引き揚げる。早稲田大学文学部ロシア文学科中退。1966年『さらばモスクワ愚連隊』で小説現代新人賞、1967年『蒼ざめた馬を見よ』で第56回直木賞、1976年『青春の門』で吉川英治文学賞を受賞。1981年から龍谷大学の聴講生となり仏教史を学ぶ。代表作は『朱鷺の墓』『戒厳令の夜』『風の王国』『蓮如』『百寺巡礼』『大河の一滴』など。ニューヨークで発売された『TARIKI』は2001年度「BOOK OF THE YEAR」(スピリチュアル部門銅賞)に選ばれた。また2002年度第50回菊池寛賞、2009年NHK放送文化賞、2010年長編小説『親鸞』で第64回毎日出版文化賞特別賞を受賞。近著に『親鸞 完結篇』『ゆるやかな生き方』『孤独の力』『杖ことば』『五木寛之の金沢さんぽ』など。
先日、仕事で広島へいった。
飛行機にしようか、それとも新幹線にしようかとずいぶん迷ったのだが、結局、四時間ほどかかる新幹線をえらんだ。行先が福岡だったら空路にしただろう。空港から市内までのじかんが短くてすむからである。
車内で何冊か文庫本を読み、時には原稿を書く。機内で仕事することもあるが、やはり落ち着かない。
しかし、流れるように飛び去っていく車窓からの風景を眺めながら、なにか一種のさびしさのようなものを感じずにはいられなかった。孤独でいられることは、私にとってはありがたいことだ。電話もなく、人と会話する気疲れもない。活字を読み、ときに居眠りもできる。心やすらぐ数時間である。
しかし、と、ふと首をかしげる瞬間がある。何十年も前の列車の旅を回想して、なんとなくため息をついたりするのである。
私がはじめて上京したのは、1952年の春だった。すでに60年以上も昔のことだから、記憶もさだかではない。
当時、博多から東京までの列車の旅は、たぶん24時間以上かかったのではなかったか。特急でそれくらいだから、もし普通列車を乗りついで上京するとしたら、気が遠くなるほどの時間を要したはずだ。
当時、私は両親の故郷である福岡県の筑後地方に住んでいた。そこから久留米へでて、さらに博多へむかう。それだけでも大変だった。いまとちがって、自動車専用道路もない時代である。
博多から東京行きの特急に乗る。そのことだけでも大冒険のような気がしていたのだ。たしか、「玄海」とか、「阿蘇」とかいった列車があったように思う。
その頃の客車は、2人ずつの席が向かいあっていて、四人がいやでも顔をつきあわせることになる。しかも長時間の旅である。ひとりだけ本に読みふけっているわけにはいかない。一晩夜を共にする旅の仲間なのだ。
駅の構内でうろうろして、あわてて乗りこんだ席は、ドアに近い進行方向に向かって右列の席だった。すでに行商人ふうの初老の男と、子どもをつれた中年の婦人が座っていた。
列車が動きだすと、私の隣の男が、気軽な調子で話しかけてきた。大学を受験するために上京するのだ、と答えた私に、自分も通信教育で勉強したことがある、と彼は煙草に火をつけて言った。
「おミカンどうですか」
と、向かい側の席の婦人がミカンをさしだした。
「ありがとう」
私と男は礼を言ってミカンを受けとり、皮をむいた。やがてその婦人も、話の仲間にくわわった。
トンネルにさしかかると、汽笛が鳴る。私はあわてて窓をしめる。開けたままトンネルに入ると、まっ黒なすすが流れこんでくるのだ。
「すみません」
と、そのつど婦人は礼を言った。
やがて話が一段落すると、隣りの男はいびきをかいて眠りはじめた。彼の頭が私の肩にのしかかってくる。何度おし返しても、また頭をあずけてくるのだ。
いくつもいくつもトンネルをくぐり、鉄橋をわたった。ゴトン、ゴトンという線路の音が、ずっと響いていた。時間が流れ、私はこれからの生活に対する漠とした不安のなかで外の風景を眺めていた。
そんな時代のことを思いだしながら新幹線の快適なシートに座っていると、なんとなく大事なものを、どこかに置き忘れてきたような気分になってくるのだ。
独りでいることは、気持ちがいい。本も読めるし、自由に仕事もできる、それを物足りなく思ったりするというのは、現代人のわがままかもしれない。なにかを得ることは、なにかを失うことなのだ、と、最近ふと思ったりするのである。失われたものは、何なのだろうか。