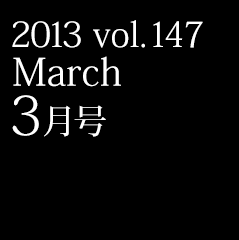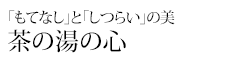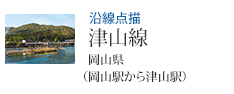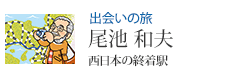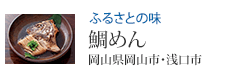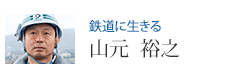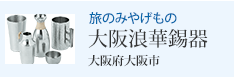お酒の味がまろやかになるといった作用や、防湿性に優れていることから茶葉を新鮮に保つ作用があるといわれる錫器。国内で流通する錫器の6割が大阪府で生産され、その多くが大阪市東住吉区の工房で作られている。
錫器が日本に伝わったのは今から約1,300年前のこと。遣唐使が中国から持ち帰ったといわれ、主に宮中で使われていたそうだ。一般的に使われるようになったのは江戸時代に入ってからで、京都を中心に作られていたが、やがて経済の中心地だった大阪に産地を移した。最盛期の昭和前半には大阪全体で250余名もの錫器職人がいたという。
錫は非常に柔らかい金属で、機械加工が難しいため、鋳造、切削などほとんどの工程が今なお人の手によって行われる。錫独特の銀色の光沢は、こけし削りのような「ロクロ挽き」という作業で丁寧に研磨することによって生まれる。
職人の手により一つひとつ作られている大阪浪華錫器。茶器や和酒器に限らず、タンブラーやワインカップ、 ペンダントトップなど、 時代に合わせてさまざまな器が作られ続けている。


![大阪府大阪市 大阪浪華錫器[おおさかなにわすずき]](img/souvenir_ttl.gif)